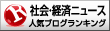村上春樹さんの小説はほとんど同時期に読んでいます。
「風の歌を聴け」というデビュー作で衝撃を受けてから、新作が待ち遠しくてたまらない数十年を過ごしています。
これって幸せなことだな、と思う次第です。勿論「ノルウェーの森」とか「海辺のカフカ」「1Q84」などの長編は読みながら、残りのページ数が少なくなるのを涙しながら(オーバーです)春樹ワールドに浸りますが、短編も最高によろしいのです。
「ノルウェーの森」の下書き(?)になった「蛍」もぐいぐい引き込まれる短編でした。
さて短編の中で私も大好きなのですが、ファンに評価の高いものに「午後の最後の芝生」があります。私は主人公の芝生を刈る姿勢に生き方の基本を感じたし、また暑い夏の午後の感じがとてもよく出ていました。
その「午後の最後の芝生」の冒頭にこのような文章があります。「記憶というのは小説に似ている、あるいは小説というのは記憶に似ている。僕は小説を書き始めてからそれを切実に実感するようになった」
この小説を写真に代えてもピッタリと当てはまります。
「記憶というのは写真に似ている、あるいは写真というのは記憶に似ている」
私が写真を撮るとき、またセレクトするときそのような感じ方がします。また感動する写真はいつも私を揺さぶり、その写真と類似した記憶を想起させるものです。
その意味において、写真は古くなればなるほど光り輝くものになるし、ある家族、ある地方の写真から「その殻を破って」その写真は普遍的なものになります。
村上春樹さんの小説を読みながら、写真のことを考えました。

これは以前ブログで紹介した「長崎」の中の一枚です。
私はこの写真を見ると、18の頃カーフェリーで宮崎を離れ、たった一人で大学に行ったときの不安と希望の混じった記憶が甦ります。