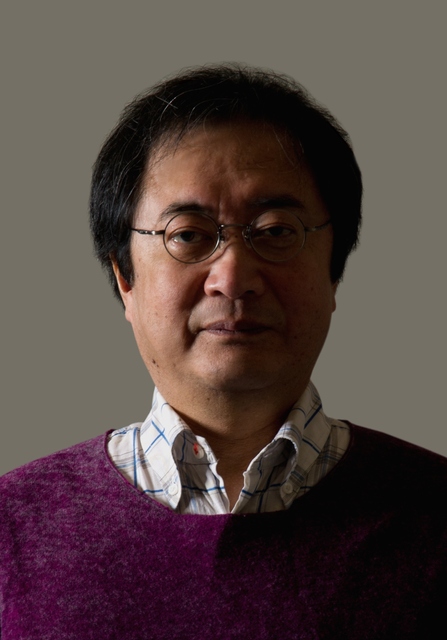洪水の際、どこかで堤防が破壊され河川水が大量に放出され場合、河川全体の水位が急激に下がるものなんです。石狩川のような大河川でも時間はかかるけど、河川全体で徐々に水位が下がってきました。
・・・
堤防が破れて大きな被害を被ったマチは堪(たま)りませんが、その犠牲のおかげで救われたマチやムラは幸運でした。どこの堤防が破れてもおかしくない状況下で、〝堤防同士の我慢比べ”の様相でした。
この時の洪水、150年に一度の豪雨災害だったに違いありません。この後は堤防の強化や遊水池の設置などの対策が講じられましたが、この時ほどの水位に達したことはないのです。
ただ安心してはなりません。地峡温暖化による異常気象が近年多発してます。集中豪雨もその一つです。北海道でもゲリラ豪雨なる事態がたびたび起こっているのです。
元々統計上から北海道や東北は豪雨の少ない扱いを受けてます。台風が上陸する確率が西日本に比べずいぶんと少ないのが理由の一つです。
堤防の高さや下水道管の管径・勾配など、国の基準はその地域により異なります。北海道はその他地域より想定雨量が少なめで、堤防の高さや下水道管の管径・勾配などが決められています。ただこの基準、過去の統計を基準にしたものなので、昨今の異常気象の値は入っていないのです。
ですから、50年前に150年の豪雨に耐えられる、とした河川が30年に一度の豪雨にも耐えられないのでは?って疑問が生じるのも当然です。実際、石狩川の氾濫は30年に一度だ!って言う専門家がいるほどなんです。
150年と30年では大きな違いがあります。150年だと一生に一度災害に出会うかどうかって楽観的に思う人が大半なんだろうけど、30年に一度って言われたら多くの人は実際に洪水被害に遭うんだろう、って心配するはずです。
石狩川の河川管理者である北海道開発局は、堤防の強度を増すための施策を行ってきました。けどそんなんでは40数年前の我慢比べの解消につながりません。河積が変わらないのだから、弱いところから崩壊するのは目に見えています。
遊水池構想があります。すでに近隣のマチで実施されています。40数年前の教訓を生かした優れた治水対策だと思います。
続きます。