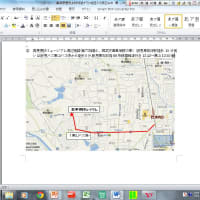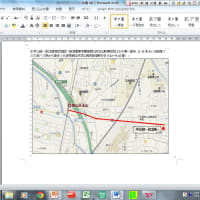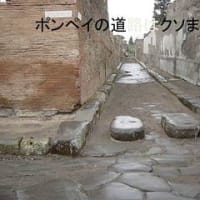2月26・27日と恒例の城柵官衙遺跡検討会が開かれた。
毎年この時期に開催される東北地方の城柵官衙関連遺跡の研究会である。大体宮城県と他の東北地方の諸県諸都市を交替で開催している。今年は秋田県横手市で初めて開催された。

新幹線の車窓から盛岡を過ぎてから

大曲駅

後三年駅

後三年駅を過ぎて横手へ。奥羽本線を南へ進む
横手市には行ったことがなかったのでとても楽しみだったが、行く前から「大雪」が伝えられており,少々心配ではあったが、朝五時に津を出発して新幹線を乗り継いで13時には無事会場に辿り着いた。
噂通りの雪だっtがタクシーの運転手に聞くとこの倍(2m以上)はあったと言うから驚きだ。
途中もっと知り合いに会うかと思ったが意外と会わず、唯一、YKさん親子に会っただけだった。彼女とは確か以前もこの研究会で同じく親子でいらっしゃっていたときに会った気がする。人の子供は直ぐ大きくなると言うその通り、確か赤ん坊だった子供が走り回っていた。何せ彼女とはもう10数年前、ロシアから国境を越えて中国へ入り、渤海の研究ツアーを組んだときからの仲間で、,その当時と変わらぬはつらつとした姿に元気をもらった。
そういえば、渤海のツアーではいろんなハプニングがあったが、最も印象的だったのが東京竜原府(吉林省琿春市)を訪れたときだった。その当時から中国政府は東北地方の支配を合理化するために、歴史をひん曲げ、高句麗や渤海を中国の一地方組織だと言いくるめてきた。これを否定する日本の学者が中国に入ることを妨害することもしばしばであった。
私達はただこれらの遺跡の現状を見学するのが目的だったが、当局はピリピリしていた。事前に見学の許可をもらっていたが、当日になって、急に全て不許可にされた。
「エッツそんな!」
「どうするのこれから??」
と言うことで一同途方に暮れた。そこで市内見学と言うことになったのだが、市内にはろくな遺跡も博物館もない。たまたま公園に辿り着いて、ここで気分転換でもするか、と言うことになり、ほとんど人気のない遊園地で時間をつぶすことになった。その時の団長さんは高橋美久二さんだった。団長自ら子供用の足こぎ車に乗って競争に興じたり、ゴーカート??に乗って園内をぶっ飛ばしたりした。
私は恐る恐る軸の錆びた観覧車に乗って上空から市内を撮影することにした。ホント恐ろしかった。降りてからはYKさんが二人乗りの空中足こぎ自動車に乗ろうと言うから、これも錆びて恐ろしいのだが、二人でくるくる回った。まさに子供に返って一日憂さを晴らしたのを今でも好く覚えている。


さて、研究会だが、今回はいつもの一年間の調査事例報告に加えて、シンポジウム「古代城柵から柵・館へ」と言う特集が組まれた。
この研究会の事例報告はいつも感心するくらい時間通りに、内容も濃く、とても判りやすいのだが、久しぶりに来た今回はちょっと雰囲気が違っていた。もちろん相変わらず、パワーポイントを実にうまく使いこなしてとても判りやすく手際のいい発表もあったのだが、余りに細かいことに拘りすぎて結局時間がなくなり、よく判らない発表もあって少し残念な気がしたのもあった。今ちょうど世代交代の時期で若干うまくいっていないところもあるのかな?と少し不安に思ったことも事実だ。
それでももちろん幾つもの興味深い発表があった。
私が最も興味を抱いたのが赤井遺跡の建物群だった。この遺跡はかなり古い時代に調査に着手された遺跡の一つで、今回が42回目になると言う。古代牡鹿柵・牡鹿郡家に推定されている遺跡である。七世紀中葉からの遺物が出土し、九世紀後半まで使用されたという。
赤井遺跡のある陸奥国牡鹿郡は7世紀中頃上総地域から移った丸子氏との関係の深い遺跡だという。丸子氏はその後牡鹿連に改姓し、さらに道嶋宿禰を名乗るようになる。その本拠地が赤井遺跡周辺であり、赤井遺跡は彼らが支配した牡鹿郡家或いは牡鹿柵でははないかというのである。
この赤井遺跡の所在する大崎平野には関東からの移民により郡が建てられたことが知られているが、赤井遺跡はその東端にあり、仙台に設けられた郡山遺跡などとも深い繋がりのある遺跡だというのである。
とりわけ興味深いのが道嶋氏が「大国造」を名乗ったことであろう。八世紀の国造は神事を掌ったがその中でも「大」を付けてより高い地位を誇示したのである。
そうした歴史的背景をもつ赤井遺跡だけに発見された遺構の解釈が大変興味深いのである。
特に注目したのがこの図に示された総柱建物を材木列と堀で二重に囲う施設である。担当者は他に10棟ほど発見されている総柱建物と同等にみなして牡鹿郡正倉をイメージした倉庫群と考えているようだが、私にはこの堀などに囲繞された総柱建物まで同等に扱うには抵抗があった。

赤井遺跡の特殊な建物群とその囲繞施設。
実は以前にもこの遺跡の西に位置する壇の越遺跡でも非常によく似た構造の施設を見たことがあり、それとの関係が注目された。壇の越遺跡より注目できたのは、この施設群が、さらに外側を堀で囲っていたのではないかとみられたからたからである。仮に上図のような構造であったとすると、この総柱建物は実に3重に囲われていたことになる。この様に見事に二つの施設が外側の溝のど真ん中に来ることがあるだろうか。そしてもう一つ気になるのが、西の溝で囲われた施設が南を空けているのに対し、東の施設は「ロ」字形に閉塞している点だ。これも対照的で面白い。
これが普通の倉庫だろうか?
もちろんだからと言って何か?と問われても類例があるわけではないのだが、「律令国造」を名乗った道嶋氏であるとすると、そうした宗教的な施設とすることはできないのか、と考えたのである。
もちろん道嶋氏が国造になる時期とこれら施設の建設時期がずれており、そうは簡単ではないのだが、いずれにしろ、私にはこれを普通の倉庫群とする解釈には賛成できないのである。

報告者の解釈はこうだ。その根拠は仮に右側の「コ」字形の堀が左側の古い時期のものだとすると左側に2基並列している堀に囲われた遺構群の西(左)隣にある「床束」のある建物と重なってしまうからだという。しかし、どう見てもこの床束のある建物はその右(東)にある総柱建物より柱堀方(抜き取り穴)の規模が異なる。柱の並び方も少し異なっている。そもそもがこちらは普通の側柱建物なのに、右の二つは総柱建物で、全く構造が違う。それを同じ時期と考える方がおかしいのである。
(こんな風に若い人達の報告を批判すると、またどこかから非難の矢が飛んできそうだ。今回、研究会後の「懇親会」の席で東北古代史を背負って立つ若き?(中堅!)の研究者からお小言をもらった。「あんまり若い人を「ダメ」だとか「○○」とか言うべきではありませんよ」と。「ウーン、そうかなー?若者達こそこれまでの研究史を余りに無視する事例が多いのじゃないのかな-?もちろん若い人達の新鮮な脳みそでの思考の方が優れているのだろうが・・・。でも人文学って、結構年寄りの研究でも生きている例は多いのじゃないかな?若けりゃ何でもいいとは思えないのだが・・・?ハハ、でもこう思うところがもう年寄りかな?(笑)STさん忠告有り難う。これから注意しますね。」)
そんな感想を抱いた後で今回の特集が始まった。ただ、私には余りに難解でまだ十分に咀嚼することができないのである。もう少しじっくりとレジュメ集を読んだ上で、後日考えをまとめてみる,とにする。
いずれにしろ相変わらず刺激的な研究会であった。今年の夏には考古学研究会東海例会を三重大学で開催することが決定した。
2010年8月6(土)・7(日)日の二日間、東海地方を中心とした駅路と官道について検討しようと思っている。とても城柵官衙遺跡検討会には及ばないが、少しでも近づけるよう、これから準備に励みたく思っている。
城柵官衙遺跡検討会、やっぱりすごいねと思ったらこいつをポチッと押して下さいね→
雄勝へと 歩を進める兵に 雪の壁
北上の 凍てし流れの 先に蝦夷
白銀の 車窓を共に 柵論議
都より 白銀の世界 兵いずこ
毎年この時期に開催される東北地方の城柵官衙関連遺跡の研究会である。大体宮城県と他の東北地方の諸県諸都市を交替で開催している。今年は秋田県横手市で初めて開催された。

新幹線の車窓から盛岡を過ぎてから

大曲駅

後三年駅

後三年駅を過ぎて横手へ。奥羽本線を南へ進む
横手市には行ったことがなかったのでとても楽しみだったが、行く前から「大雪」が伝えられており,少々心配ではあったが、朝五時に津を出発して新幹線を乗り継いで13時には無事会場に辿り着いた。
噂通りの雪だっtがタクシーの運転手に聞くとこの倍(2m以上)はあったと言うから驚きだ。
途中もっと知り合いに会うかと思ったが意外と会わず、唯一、YKさん親子に会っただけだった。彼女とは確か以前もこの研究会で同じく親子でいらっしゃっていたときに会った気がする。人の子供は直ぐ大きくなると言うその通り、確か赤ん坊だった子供が走り回っていた。何せ彼女とはもう10数年前、ロシアから国境を越えて中国へ入り、渤海の研究ツアーを組んだときからの仲間で、,その当時と変わらぬはつらつとした姿に元気をもらった。
そういえば、渤海のツアーではいろんなハプニングがあったが、最も印象的だったのが東京竜原府(吉林省琿春市)を訪れたときだった。その当時から中国政府は東北地方の支配を合理化するために、歴史をひん曲げ、高句麗や渤海を中国の一地方組織だと言いくるめてきた。これを否定する日本の学者が中国に入ることを妨害することもしばしばであった。
私達はただこれらの遺跡の現状を見学するのが目的だったが、当局はピリピリしていた。事前に見学の許可をもらっていたが、当日になって、急に全て不許可にされた。
「エッツそんな!」
「どうするのこれから??」
と言うことで一同途方に暮れた。そこで市内見学と言うことになったのだが、市内にはろくな遺跡も博物館もない。たまたま公園に辿り着いて、ここで気分転換でもするか、と言うことになり、ほとんど人気のない遊園地で時間をつぶすことになった。その時の団長さんは高橋美久二さんだった。団長自ら子供用の足こぎ車に乗って競争に興じたり、ゴーカート??に乗って園内をぶっ飛ばしたりした。
私は恐る恐る軸の錆びた観覧車に乗って上空から市内を撮影することにした。ホント恐ろしかった。降りてからはYKさんが二人乗りの空中足こぎ自動車に乗ろうと言うから、これも錆びて恐ろしいのだが、二人でくるくる回った。まさに子供に返って一日憂さを晴らしたのを今でも好く覚えている。


さて、研究会だが、今回はいつもの一年間の調査事例報告に加えて、シンポジウム「古代城柵から柵・館へ」と言う特集が組まれた。
この研究会の事例報告はいつも感心するくらい時間通りに、内容も濃く、とても判りやすいのだが、久しぶりに来た今回はちょっと雰囲気が違っていた。もちろん相変わらず、パワーポイントを実にうまく使いこなしてとても判りやすく手際のいい発表もあったのだが、余りに細かいことに拘りすぎて結局時間がなくなり、よく判らない発表もあって少し残念な気がしたのもあった。今ちょうど世代交代の時期で若干うまくいっていないところもあるのかな?と少し不安に思ったことも事実だ。
それでももちろん幾つもの興味深い発表があった。
私が最も興味を抱いたのが赤井遺跡の建物群だった。この遺跡はかなり古い時代に調査に着手された遺跡の一つで、今回が42回目になると言う。古代牡鹿柵・牡鹿郡家に推定されている遺跡である。七世紀中葉からの遺物が出土し、九世紀後半まで使用されたという。
赤井遺跡のある陸奥国牡鹿郡は7世紀中頃上総地域から移った丸子氏との関係の深い遺跡だという。丸子氏はその後牡鹿連に改姓し、さらに道嶋宿禰を名乗るようになる。その本拠地が赤井遺跡周辺であり、赤井遺跡は彼らが支配した牡鹿郡家或いは牡鹿柵でははないかというのである。
この赤井遺跡の所在する大崎平野には関東からの移民により郡が建てられたことが知られているが、赤井遺跡はその東端にあり、仙台に設けられた郡山遺跡などとも深い繋がりのある遺跡だというのである。
とりわけ興味深いのが道嶋氏が「大国造」を名乗ったことであろう。八世紀の国造は神事を掌ったがその中でも「大」を付けてより高い地位を誇示したのである。
そうした歴史的背景をもつ赤井遺跡だけに発見された遺構の解釈が大変興味深いのである。
特に注目したのがこの図に示された総柱建物を材木列と堀で二重に囲う施設である。担当者は他に10棟ほど発見されている総柱建物と同等にみなして牡鹿郡正倉をイメージした倉庫群と考えているようだが、私にはこの堀などに囲繞された総柱建物まで同等に扱うには抵抗があった。

赤井遺跡の特殊な建物群とその囲繞施設。
実は以前にもこの遺跡の西に位置する壇の越遺跡でも非常によく似た構造の施設を見たことがあり、それとの関係が注目された。壇の越遺跡より注目できたのは、この施設群が、さらに外側を堀で囲っていたのではないかとみられたからたからである。仮に上図のような構造であったとすると、この総柱建物は実に3重に囲われていたことになる。この様に見事に二つの施設が外側の溝のど真ん中に来ることがあるだろうか。そしてもう一つ気になるのが、西の溝で囲われた施設が南を空けているのに対し、東の施設は「ロ」字形に閉塞している点だ。これも対照的で面白い。
これが普通の倉庫だろうか?
もちろんだからと言って何か?と問われても類例があるわけではないのだが、「律令国造」を名乗った道嶋氏であるとすると、そうした宗教的な施設とすることはできないのか、と考えたのである。
もちろん道嶋氏が国造になる時期とこれら施設の建設時期がずれており、そうは簡単ではないのだが、いずれにしろ、私にはこれを普通の倉庫群とする解釈には賛成できないのである。

報告者の解釈はこうだ。その根拠は仮に右側の「コ」字形の堀が左側の古い時期のものだとすると左側に2基並列している堀に囲われた遺構群の西(左)隣にある「床束」のある建物と重なってしまうからだという。しかし、どう見てもこの床束のある建物はその右(東)にある総柱建物より柱堀方(抜き取り穴)の規模が異なる。柱の並び方も少し異なっている。そもそもがこちらは普通の側柱建物なのに、右の二つは総柱建物で、全く構造が違う。それを同じ時期と考える方がおかしいのである。
(こんな風に若い人達の報告を批判すると、またどこかから非難の矢が飛んできそうだ。今回、研究会後の「懇親会」の席で東北古代史を背負って立つ若き?(中堅!)の研究者からお小言をもらった。「あんまり若い人を「ダメ」だとか「○○」とか言うべきではありませんよ」と。「ウーン、そうかなー?若者達こそこれまでの研究史を余りに無視する事例が多いのじゃないのかな-?もちろん若い人達の新鮮な脳みそでの思考の方が優れているのだろうが・・・。でも人文学って、結構年寄りの研究でも生きている例は多いのじゃないかな?若けりゃ何でもいいとは思えないのだが・・・?ハハ、でもこう思うところがもう年寄りかな?(笑)STさん忠告有り難う。これから注意しますね。」)
そんな感想を抱いた後で今回の特集が始まった。ただ、私には余りに難解でまだ十分に咀嚼することができないのである。もう少しじっくりとレジュメ集を読んだ上で、後日考えをまとめてみる,とにする。
いずれにしろ相変わらず刺激的な研究会であった。今年の夏には考古学研究会東海例会を三重大学で開催することが決定した。
2010年8月6(土)・7(日)日の二日間、東海地方を中心とした駅路と官道について検討しようと思っている。とても城柵官衙遺跡検討会には及ばないが、少しでも近づけるよう、これから準備に励みたく思っている。
城柵官衙遺跡検討会、やっぱりすごいねと思ったらこいつをポチッと押して下さいね→
雄勝へと 歩を進める兵に 雪の壁
北上の 凍てし流れの 先に蝦夷
白銀の 車窓を共に 柵論議
都より 白銀の世界 兵いずこ