


デジタルネイティブ世代
今日のNHKスペシャル「デジタルネイティブ」を観ていて大変驚かされました。
この人種(あえてこう呼びたくなるような私は、既に出遅れていると思うのですが...)を畏敬の念を抱いて観てしまいました。
彼らは生まれたときからインターネットが存在した世代なのです。
つまりネットワーク社会の申し子なのであります。
そして、あと5年もすれば成人です。(ここで、年齢を意識していることすら彼らから観たら稀有にうつるかもしれません。)
なぜなら、この番組で紹介された一番若い経営者の年齢は15歳だったからです。
彼は、化学の原子記号を覚えるために、ゲームカードにしてしまい、なんと1000万円を荒稼ぎ(あえてこう言わせてください。)したのです。
その発想力と商品化の手法やプロモーション活動はユニークで、ほとんど経費らしい経費をかけずに実現してしまったのです。
またその手法とは、ネットワーク上のSNS(ソーシャルネットワークシステム)を活用し、デザイナーなどのスタッフを集め、プロデュースしながら商品化したという大人顔負けのやり方です。
わずか、15歳の少年がです。(えらくこのことに拘る私は、本当に古いと思っています。)
彼はおそらくビジネス専門のSNSをコミュニティとして捉え、同じ価値観を共有できる仲間を徹底的に調べ、仲間に引き入れたのだと思います。
そして、スタッフの誰もが、自分たちのボスがわずか15歳の少年だと気づくのに、かなりの時間が経過してから知ったということです。
そして、自己の仕事を評価し、それに見合う報酬がもらえるのであれば、例え年下であろうと関係ないと言い切る彼らもデジタルネイティブなのであります。
また、デジタルネイティブに共通することは、社会に対していかに貢献できるかということの方が優先し、自己利益はその後になるケースが多いようです。
高度成長期を過ごし、物欲や金銭欲にまみれた私など、彼らの高邁な精神と比べると足下にも及びません。
近い将来、彼らが世界を支配するかもしれないと、ある本では語られていますが、人が人であるためには何を優先すべきかを、神が人類に対して警鐘を鳴らすために使わしたような気がします。


 ホットなニュース
ホットなニュース


































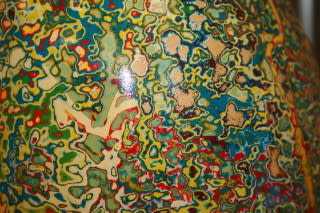










 歴史脈々
歴史脈々

 デジタルネイティブ世代
デジタルネイティブ世代








 受賞者のいない表彰式
受賞者のいない表彰式






