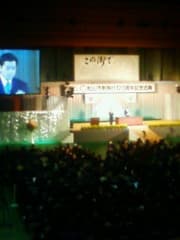今朝の「ガイヤの夜明け」という番組を見ていて気づいたことがある。
それは、既存の概念ではビジネスは難しくなっているということである。
番組の中では、運送会社「ユンクス」の紹介があった。
同社は、数年前から配達後の空の荷台に地元の野菜を集める事業を始めた。
それは、農作物を単に集めるということだけでなく、それを直接販売する産直市(トラック市)を始めてしまった。
消費者は、新鮮で安い農産物を手にして喜んでいる。
これにより、卸商や仲卸の仕事がなくなる。
運送事業者が死活問題だけでこういった事業に進出するのか。
ユンクス社の社長は言う。
「私たちは一生懸命作っている人の思いを知っているから、
一生懸命売るんです。」
過去にその役割を果たしてくれていたのは、まさに仲介事業者ではなかったのか。
自分さえよければいい、そんな考え方だけのビジネスは通用しなくなってきている。
それは、既存の概念ではビジネスは難しくなっているということである。
番組の中では、運送会社「ユンクス」の紹介があった。
同社は、数年前から配達後の空の荷台に地元の野菜を集める事業を始めた。
それは、農作物を単に集めるということだけでなく、それを直接販売する産直市(トラック市)を始めてしまった。
消費者は、新鮮で安い農産物を手にして喜んでいる。
これにより、卸商や仲卸の仕事がなくなる。
運送事業者が死活問題だけでこういった事業に進出するのか。
ユンクス社の社長は言う。
「私たちは一生懸命作っている人の思いを知っているから、
一生懸命売るんです。」
過去にその役割を果たしてくれていたのは、まさに仲介事業者ではなかったのか。
自分さえよければいい、そんな考え方だけのビジネスは通用しなくなってきている。