 夕方より
夕方より 旧暦9月大23日 太陽暦採用記念日
旧暦9月大23日 太陽暦採用記念日昨日Nテレビで旧〝郡山宿本陣〟が7日から15日まで特別公開されているとのことで訪れた。年2回特別公開される。
本陣当主が現住しており普段は見ることが出来ない。市の教育委員会の職員がこの期間出向いて公開の世話をしている。
但し、5人以上のグループで10日前までに事前予約すると見学できる。予約は電話で午前9時から午後5時まで 072-643-4622。月、火、年末年始は休み。



*後日続きを掲載します
 夕方より
夕方より 旧暦9月大23日 太陽暦採用記念日
旧暦9月大23日 太陽暦採用記念日


 時々
時々 木枯らし一号(昨年より16日早い)吹き一転冬の寒さ 旧暦9月大16日
木枯らし一号(昨年より16日早い)吹き一転冬の寒さ 旧暦9月大16日
新島襄邸宅跡(御所の東)
↓邸宅を南から見た風景 パノラマ
*************************************************************************************
御所の南部を散策して
↓大木の傍の碑には「鷹司邸跡」とある
鷹司家について
鎌倉時代以降、天皇を助けて政務をつかさどる摂政・関白の重職を任ぜられた公家の 近衛家・九条家・二条家・一条家・鷹司家 の五家を 「 五摂家 」 ( ごせっけ ) と言い、その1っが鷹司家である。
鷹司家( たかつかさけ ) は、鎌倉中期に藤原北家嫡流の近衛家実の四男兼平を祖とする公家の名家である。
文久三年(1863)八月十八日の蛤御門の変の際、鷹司邸は長州藩兵の放火により炎上。炎の中で久坂玄瑞、寺島忠三郎が刺し違えて果てたと言う。
↓芝生でくつろぐ親子連れ 好天絶好の行楽日和
 日中頗る暑い 旧暦9月大12日 十三夜
日中頗る暑い 旧暦9月大12日 十三夜





 旧暦8月小22日 愈々秋深まる
旧暦8月小22日 愈々秋深まる

 かんかん照りで蒸し暑さなし 旧暦6月小27日
かんかん照りで蒸し暑さなし 旧暦6月小27日
↓今日は「アサガオ」最多の8輪、「水草活花」とのコラージュ
**************************************************
1896(明治29)年枚方市中宮周辺に陸軍の兵器用火薬や砲弾・弾薬を収納する「禁野(きんや)火薬庫」が完成。1938(昭和13)年にはその東に砲弾や爆弾を製造する「枚方製造所」が設置され国内屈指の一大軍需施設となる。
「禁野火薬庫」は1909(明治42)爆発を起こすも死者なし。1939(昭和14)年には大爆発が起こり死傷者696人もの大惨事となる。
その時の写真24枚が市立中央図書館に保管されていることが判明し展示公開されている。(戦時中の軍事機密で埋もれていた)
同時に「ヒロシマ・ナガサキ原爆パネル展」も行われている(20日まで)。
↓枚方市立中央図書館・正面

図書館のあたりから西南にかけての広大な土地が「禁野(きんや)火薬庫」となっていた、幾つかの土塁跡や関連の石碑が残っているが現在は学校、病院、公園、公共施設、店舗、住宅等になつている。
↓毎日新聞8月14日夕刊・第一面の記事
*****************************************************
戦争を知らない子ども達が炎暑を凌ぐために大好きな水遊びに興じている。こんな姿を永遠に続かせねばならない(図書館横の「車塚公園)


 午後
午後 当たるも八卦当たらぬも天気予報 9月上・中旬の気候 旧暦6月小25日
当たるも八卦当たらぬも天気予報 9月上・中旬の気候 旧暦6月小25日 
 朝方気温低くも日中暖かくなる 旧暦3月小4日
朝方気温低くも日中暖かくなる 旧暦3月小4日










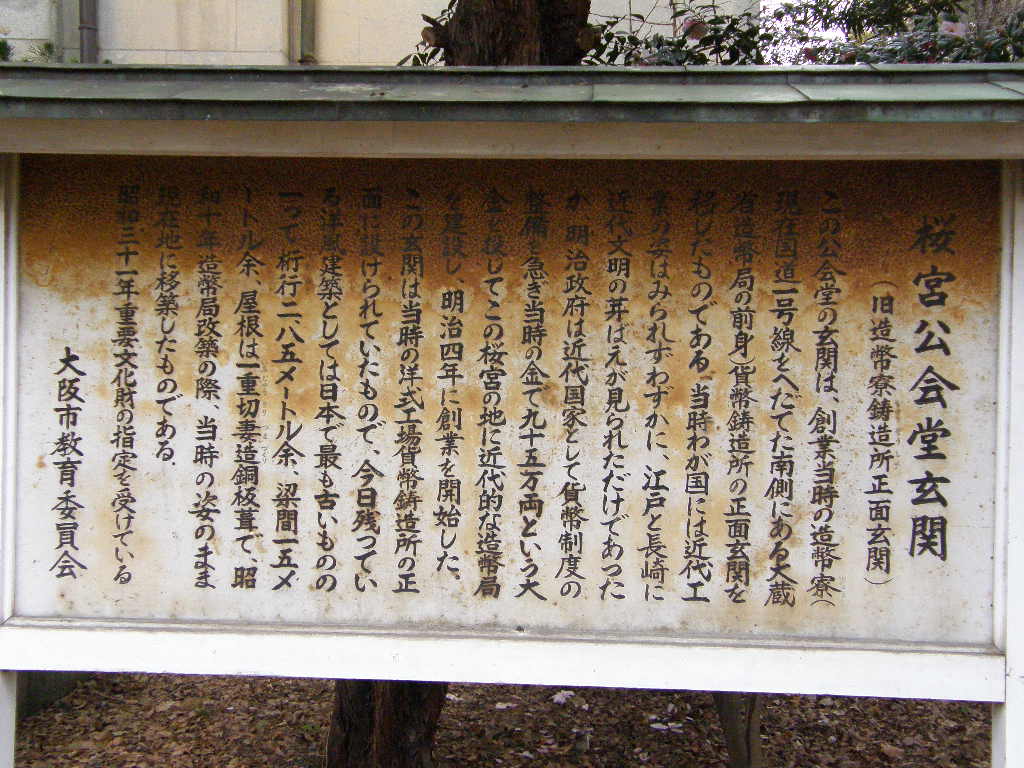

 時々
時々 風稍々強く寒い 旧暦3月小朔
風稍々強く寒い 旧暦3月小朔 



 一時
一時 旧暦7月大15日 敗戦の日
旧暦7月大15日 敗戦の日
巡り巡って63年今日は我国が太平洋戦争で敗れた日である。
「終戦記念日」と呼ぶ向きもあるが、それでは嘗ての無謀な戦争に対する反省の意味が全く欠落している。
310万の戦争犠牲者と英霊に、また諸外国とりわけ莫大な数の無辜のアジアの方々の犠牲者に対し哀悼の誠を捧げます。
下の写真は当時を偲んで、当時とそっくりそのままの製法で南瓜の団子汁を作ってみた、甘味料は一切入っていない、塩味だけだが南瓜の素朴な甘さが味わえて結構美味だった。
恐らく今の贅沢な食生活を思えばとても、このままでは不味くて食べられないだろうと甘い餡も用意していたがその必要は全く無かった。
戦時中や戦争直後は来る日も来る日も南瓜その葉、ナス、キュウリ、サツマイモその蔓・葉、ジャガイモ、虫食いのキャベツ・白菜・春菊、玉葱等が食卓に上り、イナゴや蚕の蛹、食用蛙、兎等々も食べた。幸い海辺に住んでいたので各種魚か食べられたのは有難かった。
飯は麦が殆ど、大豆や高粱が入っていたがそれでも食えれば良いほうだった。戦後何年かして白米が食べられると「銀シャリ」と呼んで、こんなに美味い飯があるのかとつくづく思ったものだ。
あの頃の惨めで哀れで戦戦兢兢として毎日を送っていた日々を思い出すと、今では何かに付け贅沢になってしまって、勿体無い勿体無い。
あと何年かすると、こんな食べ物も食べられなくなる時代が来そうな予感がする、「食 料」「資 源」を巡る戦争が各地で頻発し、世界戦争にまで発展するのではと杞憂する。杞憂に終わって欲しい。
 暑い1日だつた 旧暦4月小25日
暑い1日だつた 旧暦4月小25日
