 時々
時々 朝晩肌寒いが日中暑い 旧暦3月大26日 こどもの日
朝晩肌寒いが日中暑い 旧暦3月大26日 こどもの日
普段内部を見られないが特別公開で見学できた






↑合成がうまくいかず「水桶」が2個見えますが1個で、その右が井戸です、台所を使いやすいように高さも工夫されている。一般家庭の土間は普通「三和土(たたき)」だった



*続 く
 時々
時々 気温稍々低く日陰では肌寒い 旧暦5月大24日
気温稍々低く日陰では肌寒い 旧暦5月大24日
正午、四条鴨川南西の中華料理店4Fより東山を望む、大きい建物は「南座」その左の稍々大きい建物は「北座」のあった場所
≪新 島 襄 旧 邸≫
新島旧邸の特別公開
2012年9月~2013年12月
原則として、毎週火曜日を除く毎日開館 午前10:00~13:00 午後13:00~16:00
休館日 毎週火曜日 年末年始(12月28日~1月5日) 夏期(2013年8月12日~16日)
見学申込 個人・団体ともインターネットによる予約申込 インターネットが使えない場合はFAXでの申込
料金はいらないが東日本大震災復興協力金(募金)を、大勢の監視員や案内人が配置され立派なカラー冊子を貰えるので幾らか入場料を取ればと思う
場所 御所の東
新島旧邸について(同志社社史資料センター・抜粋)
新島襄の私邸で、ボストンの友人、J. M. シアーズの寄付によって建てられました。
この場所は同志社英学校が開校したさいに仮校舎として借家した高松保実邸の跡です。外観はいわゆるコロニアルスタイルの洋風ですが、造りの基本は和風寄棟住宅です。間取りは日本的な田の字型であり、壁は柱を露出させる旧来の真壁造りとなっています。床が高く、三方にべランダをめぐらし窓には鎧戸をつけ、白い壁面に茶褐色の木部を見せる簡素な二階建住宅です。
当時の同志社教員で医師・宣教師でもあったW. テイラーの助言を得ながら、新島襄が設計したとも伝えられています。
日本人のために建てられた和洋折衷の木造二階建て住宅として、また、同志社創立者の旧居としての価値が認められ、昭和60年(1985)に京都市指定有形文化財に指定されました。




*ここの紹介、その後訪れた御所内南西にある「捨翠亭」の掲載を今後随時します
 蒸し暑い 4月大29日 プールで涼む
蒸し暑い 4月大29日 プールで涼む
船の規模[全長224.5m 幅26m 総トン数17,382t 最高速度30.12ノット 旅客定員613名]
↓ 舳 先

 乗船して直ぐ
乗船して直ぐ 2人部屋 上下2段の4人部屋もある
2人部屋 上下2段の4人部屋もある 3人用和室
3人用和室 2人用洋室
2人用洋室 デラックスルーム
デラックスルーム
大人運賃28,500~36,500円 大浴場 露天風呂もある
大浴場 露天風呂もある カフェ
カフェ グリル
グリル キッズルーム
キッズルーム
船内は6階造り 
 大勢の人で混み合う廊下
大勢の人で混み合う廊下
↓ 前窓に雨滴がかかる 操舵室見学は30分待ちでやめた
 駐車場
駐車場
トラック、乗用車216台積載できる
 旧暦4月大27日
旧暦4月大27日
大阪港に停泊している「すずらん」(新日本海フェリー)の船内特別見学会(無料・5000名・希望多数で抽選)
午前の部・・・11:00~13:00 午後の部・・・13:30~15:30
大阪市港区天保山岸壁 ・地下鉄中央線「大阪港駅」より徒歩5分
「すずらん」は6月20日、敦賀-苫小牧航路でデビューする、今日午後6時には出港地に向けて回航するらしい。
午後の部に参加した、2時15分に到着、大阪港船乗り場の広間には幾重にも列が出来ており30分待ちの表示、きっちり30分待って乗船。船内見学に丁度1時間かかる。
後日その様子を掲載したい。
 一時豪雨 一時
一時豪雨 一時 一時
一時 旧暦4月大9日 プールで一泳ぎ
旧暦4月大9日 プールで一泳ぎ
予定しているのに天気予報が外れるのには困る、「当るも八卦、当らぬも天気予報」か。
落語に、こんな話がある或男が出掛ける時天気が気にかかり町内の易者に聞くと「降るような日和じゃない」と言う、男は降らないと思い出掛けると大雨に出あう、易者に文句を言うと「降るような、日和じゃない」と言っただろうと答える。「天気予報でなく天気予想」にしたら・・・
第二無鄰菴(むりんあん)の向かいに〝島津製作所創業記念資料館〟があるので見学する
↓ 館 入 口 蔵のような感じがする

↓ 大正7年~昭和11年にかけて製造されたレントゲン
 国内最古の顕微鏡 天明元(1781)年
国内最古の顕微鏡 天明元(1781)年
↑↓ 沢山ある展示や掲示物の1部 実験できる面白い道具もある
↓ 創業者「島津源蔵」の居室
↓ 「2代目・島津源蔵」の言葉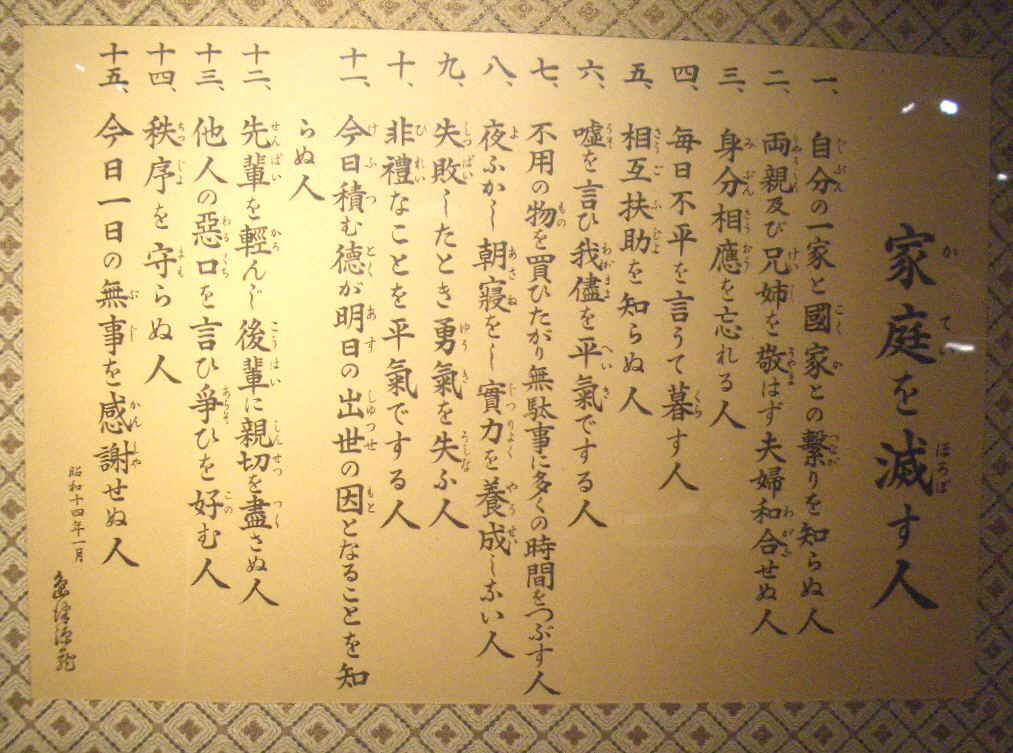

↓ ノーベル賞受賞者「田中 耕一」さんの言葉
 時々
時々 一時粉雪舞う今冬1番の冷え込み 舞鶴積雪86cm、S22年観測以来最大 豊岡90cm 旧暦正月大11日
一時粉雪舞う今冬1番の冷え込み 舞鶴積雪86cm、S22年観測以来最大 豊岡90cm 旧暦正月大11日
大阪府庁舎「正庁の間」が改修されて
現役の都道府県庁舎では全国で最も古い、大阪府庁本館(大阪市中央区)にある式典会場「正庁(せいちょう)」が、建設当時の大正時代の姿に復元された。最近は職員の執務室に使われていたが、橋下徹前知事が昨春に「歴史的価値が高い。府民に本来の姿を見てもらおう」と改修を決定。
府庁本館は1926(大正15)年に完成。正庁は建物中央の5、6階部分にあり、吹き抜け構造で約250平方メートル。天井には計55平方メートルのステンドグラス、壁は金色の獅子や天使のレリーフで装飾されるなど豪華な造りになっている。
かつては府民や職員の表彰など公式行事の際に使用さた。しかし職員数の増加で執務室となり、約20年前からは装飾を覆うように蛍光灯を取り付け、レリーフの一部もペンキで塗られていた。改修費は約4200万円という。
(朝日新聞ネット記事より抜粋) 大阪府庁舎
大阪府庁舎
↑部屋内部をパノラマにしたのでイビツに見える
 シャンデリアとステンドグラス
シャンデリアとステンドグラス 東窓のステンドグラス
東窓のステンドグラス 奉安所
奉安所
 部屋から大阪城 [ガラス窓の金網が写る]
部屋から大阪城 [ガラス窓の金網が写る] 旧庁舎 模型
旧庁舎 模型
*続 く
 一時
一時 旧暦6月大26日
旧暦6月大26日
所用で京都に行く、ついでに、今開催中の「第36回 京の夏の旅 文化財特別公開」の6箇所の内、「並河靖之七宝記念館」と「木戸孝允旧邸」を訪ねた。
他には「下鴨神社 本殿 大炊殿(おおいどの)」「南禅寺 大寧軒」「白沙村荘 橋本関雪記念館」「駒井家住宅」が特別公開されている。 9月30日まで。

表には「馬寄せ」、二階の「虫篭窓」と京町家の外観が特色
 パンフより抜粋
パンフより抜粋
窯 場 現在は使っていない


無数の釉薬と道具が並んでいる
 一時
一時  後
後 旧暦4月小6日
旧暦4月小6日↓大型帆船などの船首に付けられている航海安全の守り神

↓江戸時代の交易品

↓陶器で作られた船

↓「べか車」 最盛期の文政7(1824)年には1678台あつたと言う 板状の車輪が特徴

↓江戸期の「なにわの賑わい」

↓和 舟 菱垣廻船の荷の積み降ろしのために利用された

↓ヨット この場で乗って海での航行を擬似体験出来るようになつていたが、今は休止している

向うに見える繁みは「大阪南港野鳥園」

土日祝日には「コスモスクエアー駅⇒海の時空館⇒大阪南港野鳥園⇒海の時空館⇒コスモスクエアー駅」間のバスあり
 夏日 舞鶴29.5℃ 大阪26.5℃ 旧暦4月小4日
夏日 舞鶴29.5℃ 大阪26.5℃ 旧暦4月小4日《菱 垣 廻 船》
菱垣廻船「浪華丸」は全長約30m、帆柱の長さ約27.5mの実物大に復元された木造船で、江戸時代「天下の台所」と呼ばれていた大阪から、人口の急増した江戸へ生活物資を運んでいた。 復元してから実験的に航行させた。
「浪華丸」には、実際に乗船して船内を見学出来る。 いろいろな角度からの写真を掲載します。






 旧暦4月小3日
旧暦4月小3日入口に展示してある帆船大型模型

↓海底通路


↓海底通路から眺めた海中の模様 ワカメが見える

↓海底通路を通ってドームへ

↓4Fから天井を










