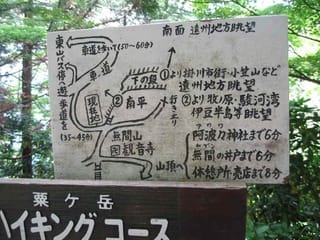遠江33ヶ所観音霊場巡り5-1回目 2010/05/28
3.1k 1.5k 5.5k 0.9k 2.9k 0.9k 5.5k 4.7k 1.4k
金谷駅-26番-25番-23番-21番-20番-19番-27番-28番-菊川駅
45 22 1:21 15 37 11 59 60 14
歩行距離 26.4k
総時間 8時間07分
歩行時間 5時間44分
平均歩行時速 4.6k
--------------------------------------------------
26番 妙国寺へ(石畳)
金谷駅を6時半出発。今日は予想距離が30k以下なので、もっと遅い時間でも良かったがこの時間の電車なら座れる事が分ったので5回とも同じ電車になった。
金谷駅を出て東側に少し下った所にあるガードから旧東海道に入る。早速登り坂が始まり、まだ遍路モードになっていない身体なので、きつく感じてしまう。
前回の遍路では掛川坂があったが、ここは金谷坂と呼ぶらしい。兎も角小夜の中山周辺は坂が多い。

坂の途中に「中山新道・金谷側入口」と書かれた案内板がある。
(中山新道のことは以前このブログでも取り上げて、歩く積りだったが天気が悪くなって中止して、そのままになっている。この道は現在は旧国1と重なる所が多いいが、一部薮漕ぎをする場所があるようなので夏草が生茂っている夏は避け、冬になったら歩いてみようと思っている)
看板には「中山新道とは日本最初の有料道路で、金谷宿から日坂宿までの6.7kを開通して有料道路とした。鉄道が開通するまでは利用者も多く賑ったが、開通後は利用者が減ってしまい、丸9年で有料道路は廃止され国道に編入された」と書かれている。
この看板では中山新道が必要だった理由として「公衆の便宜をはかるため」書いてあるが、実際は中山峠付近の森林の伐採で、材木の搬出に牛馬や荷車も通れる道が必要になったかららしい。
ようは近くにある旧東海道の石畳は牛馬や荷車は通行禁止だったので仕方なく新道を開通したのだろう。
坂が終わりホッとしたのも束の間、次は石畳の坂が始まる。歩こう会でこの石畳を歩くときは皆に遅れまいと必死になって歩くので立札を読むことも写真を撮る事も出来ないが、今日は一人、周囲を見ながら歩く余裕もある。そして毎回感じる石畳への疑問を又もや感じながら歩いていた。

その石畳が終った所に「明治天皇御駐輦址」と彫った石碑が建っていた。「輦」字は読めなかったが、きっと車の事だろうと判断した。明治天皇が自家用車でここに来て景色でも眺めたのだろう思った。しかし考えてみると、それも変だ。石畳は牛馬や荷車は通行禁止なのに自家用車が通れたのか?天皇陛下の事なので禁止も何も無いだろうが、車では通れそうもない。しかし荷車の通れる中山新道や国道はここより離れている場所にある。となると「輦」とは輿のようなものなのか? 疑問は解決しないまま家に持ち帰り「輦」の字を調べてみた。
「人の手で押し、または引く小形の車。2本の柄のついた手押しの一輪車。自家用の人力車」など出ている。さらに
「牛車の通行を禁じた皇居の内郭で乗る手車」ともある。あくまでも車でもって輿ではない。そうなると天皇陛下も大変なものだ。クッションも何も無い車で石畳の上をガタガタしながら乗っていなければならないなんて。明治天皇でなくて良かった。

金谷の石畳を登りきった所で東海道と別れ茶畑の中の道を行く。牧の原の大茶園はこの辺りから始まるのだが、土地が平らなので広さを実感できない。茶畑を見るなら平地より斜面の方が眺めは良い。それにしても大きい貯水タンクが幾つもあるものだ。
今日は八寺打つ予定だがその内四寺はお堂なのか地図に載っていない。昨晩PCのヤフーの地図で調べてあるが、札所付近の道は明確ではなかった。そうなれば仕方ない、兎も角その付近に行ってお墓を探したり寺やお堂らしき屋根を見つけるしかない。それでも駄目なら誰かに聞けばよい。幸い今日は山の寺はないのでその点は気が楽だ。
寺のあるを坂の上から見るとお寺の屋根らしき物が見えた。あとはそれを目指して行って大成功。今日最初の札所は簡単に見つけることが出来た。

26番妙国寺の入口に丸い黒と白の石が左右に置いてある。どちらも剥がれやすい石で先日聞いた馬蹄石かもしれない。だが聞くような人はいなかった。
境内から東海道線が見えるのんびりした札所だ。

25番 岩松寺へ(歩き観音)
今来た道を少し戻り川沿いに北に進む。並列していた東海道線の上りと下りの線路が離れだした。何だろう?と先を見るとトンネルになっていてトンネルが一つしかない。それを見て明治時代は大きなトンネルを掘る技術が無かったのだと一人納得していた。50m離れた場所にもトンネルがあった。覗いてみると穴が二つあり一つは架線が張ってなく廃線になっている。何かの理由で明治時代に掘ったトンネルの一つを止め、50m離れた所の新しくトンネルを掘りなおしたのだろう。でも何故だろう?
何でも気になる私だから、この様な遍路を飽きもせずできるのかもしれないな。

川を渡りサーここからは注意して歩かないと。すぐ古い石の道標があった。25とか岩とか松の字を探すが見当たらない。関係ないか。

次に出てきたのが細い道。簡易な舗装はしてあるが丸石を滑り止めのように置いてある。これでは車やトラクターは通れないから人間専用の道だろう。様子を探りに入ってみる。雰囲気は良かったが、その先は草が生え木が生茂り暗い感じになっている。参道ではないかもしれないが何故か気になりそこも入ってみることに。暗いせいか草は無くなったが枯れた竹が何本も覆いかぶさっている。もうここまで来たら進むしかない。戻っても知れているだろう。

今日は付いている。竹薮が終ると自然石を並べた入口と古仏があった。もう間違いは無い、この道は参道だ
参道と林道と合流した所に札所があった。こう書いていると大分近道なったと思うかもしれないが実際は20mくらいでしかない。しかし距離ではなく気分の問題だ。今日は付いている!
25番札所には「歩き観音」を祀ってあった。歩き観音とは
「山道にひっそりと立っていた観音様を見て里人は「さぞ淋しかろう」と往来の多い小夜の中山峠に観音様を移してやった。ところが翌日里人は驚いた。確かに移した観音様が元の場所に立っていた。足元を見ると土埃で汚れている。これはきっと観音様が自分で歩いて帰ってきたのだろうと「歩き観音」と呼んでお参りをするようになった」
歩き大好きな私には似合っている観音さんだ。丁寧に「延命十句観音経」あげた。

3.1k 1.5k 5.5k 0.9k 2.9k 0.9k 5.5k 4.7k 1.4k
金谷駅-26番-25番-23番-21番-20番-19番-27番-28番-菊川駅
45 22 1:21 15 37 11 59 60 14
歩行距離 26.4k
総時間 8時間07分
歩行時間 5時間44分
平均歩行時速 4.6k
--------------------------------------------------
26番 妙国寺へ(石畳)
金谷駅を6時半出発。今日は予想距離が30k以下なので、もっと遅い時間でも良かったがこの時間の電車なら座れる事が分ったので5回とも同じ電車になった。
金谷駅を出て東側に少し下った所にあるガードから旧東海道に入る。早速登り坂が始まり、まだ遍路モードになっていない身体なので、きつく感じてしまう。
前回の遍路では掛川坂があったが、ここは金谷坂と呼ぶらしい。兎も角小夜の中山周辺は坂が多い。

坂の途中に「中山新道・金谷側入口」と書かれた案内板がある。
(中山新道のことは以前このブログでも取り上げて、歩く積りだったが天気が悪くなって中止して、そのままになっている。この道は現在は旧国1と重なる所が多いいが、一部薮漕ぎをする場所があるようなので夏草が生茂っている夏は避け、冬になったら歩いてみようと思っている)
看板には「中山新道とは日本最初の有料道路で、金谷宿から日坂宿までの6.7kを開通して有料道路とした。鉄道が開通するまでは利用者も多く賑ったが、開通後は利用者が減ってしまい、丸9年で有料道路は廃止され国道に編入された」と書かれている。
この看板では中山新道が必要だった理由として「公衆の便宜をはかるため」書いてあるが、実際は中山峠付近の森林の伐採で、材木の搬出に牛馬や荷車も通れる道が必要になったかららしい。
ようは近くにある旧東海道の石畳は牛馬や荷車は通行禁止だったので仕方なく新道を開通したのだろう。
坂が終わりホッとしたのも束の間、次は石畳の坂が始まる。歩こう会でこの石畳を歩くときは皆に遅れまいと必死になって歩くので立札を読むことも写真を撮る事も出来ないが、今日は一人、周囲を見ながら歩く余裕もある。そして毎回感じる石畳への疑問を又もや感じながら歩いていた。

その石畳が終った所に「明治天皇御駐輦址」と彫った石碑が建っていた。「輦」字は読めなかったが、きっと車の事だろうと判断した。明治天皇が自家用車でここに来て景色でも眺めたのだろう思った。しかし考えてみると、それも変だ。石畳は牛馬や荷車は通行禁止なのに自家用車が通れたのか?天皇陛下の事なので禁止も何も無いだろうが、車では通れそうもない。しかし荷車の通れる中山新道や国道はここより離れている場所にある。となると「輦」とは輿のようなものなのか? 疑問は解決しないまま家に持ち帰り「輦」の字を調べてみた。
「人の手で押し、または引く小形の車。2本の柄のついた手押しの一輪車。自家用の人力車」など出ている。さらに
「牛車の通行を禁じた皇居の内郭で乗る手車」ともある。あくまでも車でもって輿ではない。そうなると天皇陛下も大変なものだ。クッションも何も無い車で石畳の上をガタガタしながら乗っていなければならないなんて。明治天皇でなくて良かった。

金谷の石畳を登りきった所で東海道と別れ茶畑の中の道を行く。牧の原の大茶園はこの辺りから始まるのだが、土地が平らなので広さを実感できない。茶畑を見るなら平地より斜面の方が眺めは良い。それにしても大きい貯水タンクが幾つもあるものだ。
今日は八寺打つ予定だがその内四寺はお堂なのか地図に載っていない。昨晩PCのヤフーの地図で調べてあるが、札所付近の道は明確ではなかった。そうなれば仕方ない、兎も角その付近に行ってお墓を探したり寺やお堂らしき屋根を見つけるしかない。それでも駄目なら誰かに聞けばよい。幸い今日は山の寺はないのでその点は気が楽だ。
寺のあるを坂の上から見るとお寺の屋根らしき物が見えた。あとはそれを目指して行って大成功。今日最初の札所は簡単に見つけることが出来た。

26番妙国寺の入口に丸い黒と白の石が左右に置いてある。どちらも剥がれやすい石で先日聞いた馬蹄石かもしれない。だが聞くような人はいなかった。
境内から東海道線が見えるのんびりした札所だ。

25番 岩松寺へ(歩き観音)
今来た道を少し戻り川沿いに北に進む。並列していた東海道線の上りと下りの線路が離れだした。何だろう?と先を見るとトンネルになっていてトンネルが一つしかない。それを見て明治時代は大きなトンネルを掘る技術が無かったのだと一人納得していた。50m離れた場所にもトンネルがあった。覗いてみると穴が二つあり一つは架線が張ってなく廃線になっている。何かの理由で明治時代に掘ったトンネルの一つを止め、50m離れた所の新しくトンネルを掘りなおしたのだろう。でも何故だろう?
何でも気になる私だから、この様な遍路を飽きもせずできるのかもしれないな。

川を渡りサーここからは注意して歩かないと。すぐ古い石の道標があった。25とか岩とか松の字を探すが見当たらない。関係ないか。

次に出てきたのが細い道。簡易な舗装はしてあるが丸石を滑り止めのように置いてある。これでは車やトラクターは通れないから人間専用の道だろう。様子を探りに入ってみる。雰囲気は良かったが、その先は草が生え木が生茂り暗い感じになっている。参道ではないかもしれないが何故か気になりそこも入ってみることに。暗いせいか草は無くなったが枯れた竹が何本も覆いかぶさっている。もうここまで来たら進むしかない。戻っても知れているだろう。

今日は付いている。竹薮が終ると自然石を並べた入口と古仏があった。もう間違いは無い、この道は参道だ
参道と林道と合流した所に札所があった。こう書いていると大分近道なったと思うかもしれないが実際は20mくらいでしかない。しかし距離ではなく気分の問題だ。今日は付いている!
25番札所には「歩き観音」を祀ってあった。歩き観音とは
「山道にひっそりと立っていた観音様を見て里人は「さぞ淋しかろう」と往来の多い小夜の中山峠に観音様を移してやった。ところが翌日里人は驚いた。確かに移した観音様が元の場所に立っていた。足元を見ると土埃で汚れている。これはきっと観音様が自分で歩いて帰ってきたのだろうと「歩き観音」と呼んでお参りをするようになった」
歩き大好きな私には似合っている観音さんだ。丁寧に「延命十句観音経」あげた。