歩行記録 26-3-19(日)
歩行時間:6時間12分 休憩時間:3時間28分 延時間:9時間40分
出発時間:7時25分 到着時間:17時05分
歩 数: 43、646歩 GPS距離32.6km
行程表
袋井駅 0:17> 40番 0:28> 39番 1:05> 41番 0:20> 42番 0:30> 43番 0:52> 番外 0:30> 44番 0:30>
45番 0:15> 46番 0:08> 47番 0:25> 客番 0:20> 48番 0:07> 49番 0:15> 1番 0:10> 磐田駅
48番 西光寺(樟・楠)


西光寺表門 西光寺本堂
西光寺の地図
福王寺から西に下り今之浦川と加茂川を渡ったら、今度は北の方角にある見付方面に向かう。国道1号の加茂川交差点を
渡ると48番西光寺は左側にあった。
前後に参道も無く周囲を駐車場に囲まれポツンと建っている山門は、何か場違いの感がしないでもなかった。だがこの山門は
山門とは呼ばず 「表門」 と呼ぶようだ。その表門の横に立つ案内板には
「この表門は、徳川家康が別荘として中泉村( 磐田駅南側)に築かせた中泉御殿の表門を移築したものと伝えられています。」
と、云う事は家康もこの門を潜った事があるのだと、感慨を持って門を潜ったが・・・・・・・・
西光寺の山号は 「東福山」 だが、これにも謂れがあった。
「徳川二代将軍秀忠と正室江の五女和子姫が後水尾天皇の皇后となり東福門院と称された。この和子姫が嫁入りの為に京へ
上る途中、西光寺に立寄り七堂伽藍の建立、東福山の山号、阿弥陀三尊仏と地蔵尊を賜わりました。」
成程NHKの大河ドラマ 「江〜姫たちの戦国」 で一躍有名になった、織田信長の妹・お市の方の娘の 「江」 の娘にあやかろうと
して立てた看板が目立つのか。
だがチョット腑に落ちなくて調べてみた。何故って女が結婚する前から東福院なる院号を名乗るなんて不自然じゃないのかな。
で、分かったのは 「後水尾天皇が譲位し、娘に内親王宣下が下された年に院号宣下があり、東福門院の号を賜る。」 となって
いた。マー大して違いはないから問題はないが正確ではなかった。
若い僧侶にご朱印を依頼して朱印帳を手渡したのだが中々戻ってこない。たかが3個の印を押すだけなのに何をやっている
のだ。とイライラし始めたとき別の僧が来たので催促をした。その僧も奥に行ったがすぐ戻ってきた 「今書いてます」 と云う。
書く? 押すの間違いではと思ったが黙っていた。10分ほどして朱印帳を手にした僧が戻り 「空いている場所が1ヶ所しか
なかったので、そこに書いておきました。」 と云う。またしても 「書く」 が出てきたので、慌てて納経帳を確認すると、西光寺の
ページに朱印は打ってなかった。そして最後のペ-ジをめくると、なんとそこに 「薬師如来西光寺」 の筆文字が・・・・
どうやらこの僧は遠江四十九薬師霊場会制定の朱印帳を知らないようだ。仕方ないこれで良しとするか、でも今後の事もある
ので朱印を打つ場所は知らせておこうと、西光寺のページを広げて 「ここに朱印を押すだけでいいようですよ」 と言った。
それを聞いた僧は平謝りになって 「打ってきます」 とまた奥に走って行きました。



楼門? 薙の木 大樟
この門の正式名称は何だろう? 山門とおぼしき物が表門だったので、ならこれは山門か、案内板が無いので一先ず楼門と
しておけば間違いないだろう。
その楼門を潜ると右には楠の大木と薙の木が聳えている。それぞれに案内板があり、薙の木には
「ナギの木は葉は楕円形、縦の方向だけに多数の葉脈があり、横には切れにくくなっている事から、縁結びの印とされています」
フーンそうなんだ。ナギの木が縁結びの木とは知っていたが葉が切れにくいのが謂れの元なのか。一つ物知りになった。
もう1本の楠には 「西光寺の大樟 鐘楼堂(山門)をくぐると」 アッ!ここに楼門の名前があった。矢張りこの楼門は福王寺と
同じように山門と呼ぶのだ。この様に山門らしき物が複数あると、寺により呼び名が違うので分からなくて面倒だ。
「推定樹齢500年の老大樹です。最近は、縁結びのパワースポットの木として有名になり、沢山の人達に参拝されています。」
それ以外にも 「恋愛成就隠れパワースポット」 の看板があり、そこに縁切りの方法も書いてあった。
「悪縁を切りたい時は、ナギの木が(大楠に隠れて)見えない場所から、大楠に向かって願い事を念じ、そのあとナギの木に
同じ願い事を念じてください。」 とある。
ただ、ここで注意しなければならないのは、縁結びの願いはナギの木に念じてから、楠に念じるとと成就するので、念じる順番を
間違えると縁結びが縁切りになってしまう。これからお参りしようと思っている方はくれぐれもご注意を。
ところで楠の案内板に 「楠」 ではなく、わざわざ 「樟」 と書いてあるが、樟と楠は違うものだろうか?
また興味を感じて調べてみた。
「クスノキ(樟、楠)とは、ともにクスノキ科ニッケイ属の常緑高木のことである。一般的にクスノキに使われる「楠」という字は
本来は中国のタブノキを指す字である。
クスノキは各部全体から「樟脳」の香りがする。樟脳とは、すなわちクスノキの枝葉を蒸留して得られる無色透明の固体のことで、
防虫剤や医薬品等に使用される。このため、クスノキに「樟」という字が使われる。クスノキの葉をちぎると、ツンとする 「樟脳」 の
香りがする。クスノキは独特な芳香をもつ事から 「臭し(くすし)木」 が語源です。」
こうしてみると漢字表記の時は 「樟」 の方に軍配は上がりそうだ。よって西光寺の案内板は正しかった。
でも、でもですよ。調べている過程でこんな事も書いてあった。
「クスノキの葉脈の付け根にはダニ部屋と呼ばれる1mmはどのふくらみがあり、そこにダニ(フシダニ)が棲んでいます。」
エッー! 待ってよ。クスノキは防虫剤に使われているのに、何故ダニが棲んでいるのだ。わけが分からなくなった。
しかし 「ダニ部屋」 本当なら、ナギの葉とクスノキの葉を間違って拾うと、ダニを飼う事になってしまう。これは大変だ!
49番 慈恩院(坂の多い街)


慈恩院の山門 慈恩院本堂
慈恩院の地図
磐田の街中は坂が多いが、神戸や熱海のように海に向かう一方向の坂ではなく、登ったり下ったりの坂が多い。
以前東海道を歩いた時は、この先に坂があると思うと事前に身構え準備したものだ。県内なら箱根西坂、薩埵峠、宇津ノ谷峠、
小夜の中山日坂峠、塩見坂などがそうだが、これらの坂に近づくと “どの位の坂なのだ” と挑戦する気になったものだ。
その所為か案外容易に坂を乗り越える事ができた。
一方予備知識が無く現れる坂には案外手こずる事がある。その代表がここ磐田の坂だった。
見付宿の東の袋井宿を出て標高9mの太田川を渡ると磐田原台地の登りになる。台地の上の標高は45mだが、またすぐ
下りになる。今度は17mまで下って次は鈴ヶ森の刑場跡への登りになる。刑場跡の30mに来るとまた下りとなり見付宿を
流れる標高5mの今之浦川を渡る。
いえ、これで終わりではなく次は姫街道の分岐のある西木戸までの軽い登り、そこから西光時の国道1号までの下り、さらに
国分寺跡への登りとアップダウンは続く。
一つ一つの坂は大した事は無いが、幾つも続くアップダウンは疲れた足には案外響いた。
このように磐田の街中に上り下りの多いのは、ここが台地の上とは云え、台地の外れ部分なので土地の起伏があり故に坂が
多くなるのだ。今は台地の南下には広い平野が広がっているが、かってはそこに湾や湖がある湿地地帯で、街道や役所などを
建設することができなかったのだろう。でもなぜこんなに起伏が多い所が国府になったのか疑問は残る。
薬師霊場最後の札所、慈恩院はそんな見付宿の路地の奥にあった。
その山門の前に立ち、まず目を引いたのは 「半僧坊」 の石碑だった。半僧坊と云えば浜松市引佐にある奥山方広寺が有名だが
この慈恩院とは何か関係があるのだろうか? 山門に掛かった額には 「臨済宗妙心寺派」 となっている。確か方広寺は 「臨済宗
方広寺派」 の本山だったはずだ。そして半僧坊とは方広寺を火事から守った守護神だった筈だ。
ご朱印を受ける際に住職に 「何故半僧坊の石碑が有るのですか?」 と聞いてみた。
しかし住職は 「私も興味があったので、先代に聞こうと思っていたが聞き忘れてしまった」との事でした。
この方は僧侶と云うより会社員風で気さくに話ができた。でも僧侶の仕事にはまだ慣れていないのか、ご朱印を頼むと
「判だけならいいけど書くことは出来ない」 と言った。48番西光寺もそうだったが49薬師の納経帳を見た事がないのだろうか。
霊場巡りも最後になると途中で諦めてしまう人が多く、ここまで来る人はいないのだろうか?
半僧坊が気になり調べてみると
「半僧坊信仰が全国に広まったのは明治時代で、方広寺の山火事の際、円明大師(無文元選禅師)の墓と方広寺の鎮守 「半僧坊」
が類焼を免れたことから、半僧坊の威徳によるものという評判が広まり、半僧坊の信仰が全国に広がった。」 そうです。
そうか 「半僧坊」 とは方広寺だけの守り神ではなく、宗派にかかわらず寺の守護神になっているのか。
そう云えば藤枝の奥にある曹洞宗の盤脚院でも半僧坊を祀っていた。
49番を打ち終り、これで遠江薬師の札所49寺と番外、客番2寺、合わせて51寺全てを打ち終り結願(けちがん)を迎える事ができた。
しかしどうと云う感激は湧いてこない。初めて霊場巡りをしたのは10年ほど前に、マイカーで四国88カ所を10日ほどで廻ったのだが、
その時は88番大窪寺で感激して涙ぐんでしまった。
翌年今度は歩き遍路で36日掛けて廻ったのだが、その時の感激は期待に反して薄いものだった。信仰心の薄い私は霊場巡りを
スタンプラリーのようにして廻っているので、仏様が感激と云うご利益を私には授けてくれなくなったのだろう。
でも、でもですよ、今回の約霊場巡りでは、般若心経だけでなく 「延命十句観音経」 を唱えていたら、いつの間にか暗唱できるように
なっていた。これが今回のご利益と思えば仏様はまだ私を見放してはいない。
「観世音。南無仏。与仏有因。与仏有縁。仏法相縁。常楽我浄。朝念観世音。暮念観世音。念念従心起。念念不離心。」
(かんぜおん、なむぶつ、よぶつういん、よぶつうえん、ぶっぽうそうえん、じょうらくがじょう、ちょうねんかんぜおん、
ぼねんかんぜおん、ねんねんじゅうしんき、ねんねんふりしん)
「南無大慈大悲観世音菩薩、種々重罪、五逆消滅、自他平等、即身成仏」
(なむだいじだいひかんぜおんぼさつ、しゅじゅじゅうざい、ごぎゃくしょうめつ、じたびょうどう、そくしんじょうぶつ)
意味? 私は門前の小僧と同じですので無理な事は聞かないでください。
*************** ================ ******************
satoさん、まだこのブログを見てくれているのでしょうか。
satoさんに催促されたのは去年の4月ですから、1年がかりで約束を果たした事になります。
遍路の観歩記を再開した時は、当時の事を覚えているか心配でしたが、写真やメモや地図を見ると不思議に思いだすものですね。
これなら今現在私には認知症の恐れはないと思いますが、時々日にちや曜日を忘れることが・・・・・・
しかし今日が何日で何曜日も関係ないオールサンデーの年金生活者にとっては、不要なデータで仕方ないかも。
歩行時間:6時間12分 休憩時間:3時間28分 延時間:9時間40分
出発時間:7時25分 到着時間:17時05分
歩 数: 43、646歩 GPS距離32.6km
行程表
袋井駅 0:17> 40番 0:28> 39番 1:05> 41番 0:20> 42番 0:30> 43番 0:52> 番外 0:30> 44番 0:30>
45番 0:15> 46番 0:08> 47番 0:25> 客番 0:20> 48番 0:07> 49番 0:15> 1番 0:10> 磐田駅
48番 西光寺(樟・楠)


西光寺表門 西光寺本堂
西光寺の地図
福王寺から西に下り今之浦川と加茂川を渡ったら、今度は北の方角にある見付方面に向かう。国道1号の加茂川交差点を
渡ると48番西光寺は左側にあった。
前後に参道も無く周囲を駐車場に囲まれポツンと建っている山門は、何か場違いの感がしないでもなかった。だがこの山門は
山門とは呼ばず 「表門」 と呼ぶようだ。その表門の横に立つ案内板には
「この表門は、徳川家康が別荘として中泉村( 磐田駅南側)に築かせた中泉御殿の表門を移築したものと伝えられています。」
と、云う事は家康もこの門を潜った事があるのだと、感慨を持って門を潜ったが・・・・・・・・
西光寺の山号は 「東福山」 だが、これにも謂れがあった。
「徳川二代将軍秀忠と正室江の五女和子姫が後水尾天皇の皇后となり東福門院と称された。この和子姫が嫁入りの為に京へ
上る途中、西光寺に立寄り七堂伽藍の建立、東福山の山号、阿弥陀三尊仏と地蔵尊を賜わりました。」
成程NHKの大河ドラマ 「江〜姫たちの戦国」 で一躍有名になった、織田信長の妹・お市の方の娘の 「江」 の娘にあやかろうと
して立てた看板が目立つのか。
だがチョット腑に落ちなくて調べてみた。何故って女が結婚する前から東福院なる院号を名乗るなんて不自然じゃないのかな。
で、分かったのは 「後水尾天皇が譲位し、娘に内親王宣下が下された年に院号宣下があり、東福門院の号を賜る。」 となって
いた。マー大して違いはないから問題はないが正確ではなかった。
若い僧侶にご朱印を依頼して朱印帳を手渡したのだが中々戻ってこない。たかが3個の印を押すだけなのに何をやっている
のだ。とイライラし始めたとき別の僧が来たので催促をした。その僧も奥に行ったがすぐ戻ってきた 「今書いてます」 と云う。
書く? 押すの間違いではと思ったが黙っていた。10分ほどして朱印帳を手にした僧が戻り 「空いている場所が1ヶ所しか
なかったので、そこに書いておきました。」 と云う。またしても 「書く」 が出てきたので、慌てて納経帳を確認すると、西光寺の
ページに朱印は打ってなかった。そして最後のペ-ジをめくると、なんとそこに 「薬師如来西光寺」 の筆文字が・・・・
どうやらこの僧は遠江四十九薬師霊場会制定の朱印帳を知らないようだ。仕方ないこれで良しとするか、でも今後の事もある
ので朱印を打つ場所は知らせておこうと、西光寺のページを広げて 「ここに朱印を押すだけでいいようですよ」 と言った。
それを聞いた僧は平謝りになって 「打ってきます」 とまた奥に走って行きました。



楼門? 薙の木 大樟
この門の正式名称は何だろう? 山門とおぼしき物が表門だったので、ならこれは山門か、案内板が無いので一先ず楼門と
しておけば間違いないだろう。
その楼門を潜ると右には楠の大木と薙の木が聳えている。それぞれに案内板があり、薙の木には
「ナギの木は葉は楕円形、縦の方向だけに多数の葉脈があり、横には切れにくくなっている事から、縁結びの印とされています」
フーンそうなんだ。ナギの木が縁結びの木とは知っていたが葉が切れにくいのが謂れの元なのか。一つ物知りになった。
もう1本の楠には 「西光寺の大樟 鐘楼堂(山門)をくぐると」 アッ!ここに楼門の名前があった。矢張りこの楼門は福王寺と
同じように山門と呼ぶのだ。この様に山門らしき物が複数あると、寺により呼び名が違うので分からなくて面倒だ。
「推定樹齢500年の老大樹です。最近は、縁結びのパワースポットの木として有名になり、沢山の人達に参拝されています。」
それ以外にも 「恋愛成就隠れパワースポット」 の看板があり、そこに縁切りの方法も書いてあった。
「悪縁を切りたい時は、ナギの木が(大楠に隠れて)見えない場所から、大楠に向かって願い事を念じ、そのあとナギの木に
同じ願い事を念じてください。」 とある。
ただ、ここで注意しなければならないのは、縁結びの願いはナギの木に念じてから、楠に念じるとと成就するので、念じる順番を
間違えると縁結びが縁切りになってしまう。これからお参りしようと思っている方はくれぐれもご注意を。
ところで楠の案内板に 「楠」 ではなく、わざわざ 「樟」 と書いてあるが、樟と楠は違うものだろうか?
また興味を感じて調べてみた。
「クスノキ(樟、楠)とは、ともにクスノキ科ニッケイ属の常緑高木のことである。一般的にクスノキに使われる「楠」という字は
本来は中国のタブノキを指す字である。
クスノキは各部全体から「樟脳」の香りがする。樟脳とは、すなわちクスノキの枝葉を蒸留して得られる無色透明の固体のことで、
防虫剤や医薬品等に使用される。このため、クスノキに「樟」という字が使われる。クスノキの葉をちぎると、ツンとする 「樟脳」 の
香りがする。クスノキは独特な芳香をもつ事から 「臭し(くすし)木」 が語源です。」
こうしてみると漢字表記の時は 「樟」 の方に軍配は上がりそうだ。よって西光寺の案内板は正しかった。
でも、でもですよ。調べている過程でこんな事も書いてあった。
「クスノキの葉脈の付け根にはダニ部屋と呼ばれる1mmはどのふくらみがあり、そこにダニ(フシダニ)が棲んでいます。」
エッー! 待ってよ。クスノキは防虫剤に使われているのに、何故ダニが棲んでいるのだ。わけが分からなくなった。
しかし 「ダニ部屋」 本当なら、ナギの葉とクスノキの葉を間違って拾うと、ダニを飼う事になってしまう。これは大変だ!
49番 慈恩院(坂の多い街)


慈恩院の山門 慈恩院本堂
慈恩院の地図
磐田の街中は坂が多いが、神戸や熱海のように海に向かう一方向の坂ではなく、登ったり下ったりの坂が多い。
以前東海道を歩いた時は、この先に坂があると思うと事前に身構え準備したものだ。県内なら箱根西坂、薩埵峠、宇津ノ谷峠、
小夜の中山日坂峠、塩見坂などがそうだが、これらの坂に近づくと “どの位の坂なのだ” と挑戦する気になったものだ。
その所為か案外容易に坂を乗り越える事ができた。
一方予備知識が無く現れる坂には案外手こずる事がある。その代表がここ磐田の坂だった。
見付宿の東の袋井宿を出て標高9mの太田川を渡ると磐田原台地の登りになる。台地の上の標高は45mだが、またすぐ
下りになる。今度は17mまで下って次は鈴ヶ森の刑場跡への登りになる。刑場跡の30mに来るとまた下りとなり見付宿を
流れる標高5mの今之浦川を渡る。
いえ、これで終わりではなく次は姫街道の分岐のある西木戸までの軽い登り、そこから西光時の国道1号までの下り、さらに
国分寺跡への登りとアップダウンは続く。
一つ一つの坂は大した事は無いが、幾つも続くアップダウンは疲れた足には案外響いた。
このように磐田の街中に上り下りの多いのは、ここが台地の上とは云え、台地の外れ部分なので土地の起伏があり故に坂が
多くなるのだ。今は台地の南下には広い平野が広がっているが、かってはそこに湾や湖がある湿地地帯で、街道や役所などを
建設することができなかったのだろう。でもなぜこんなに起伏が多い所が国府になったのか疑問は残る。
薬師霊場最後の札所、慈恩院はそんな見付宿の路地の奥にあった。
その山門の前に立ち、まず目を引いたのは 「半僧坊」 の石碑だった。半僧坊と云えば浜松市引佐にある奥山方広寺が有名だが
この慈恩院とは何か関係があるのだろうか? 山門に掛かった額には 「臨済宗妙心寺派」 となっている。確か方広寺は 「臨済宗
方広寺派」 の本山だったはずだ。そして半僧坊とは方広寺を火事から守った守護神だった筈だ。
ご朱印を受ける際に住職に 「何故半僧坊の石碑が有るのですか?」 と聞いてみた。
しかし住職は 「私も興味があったので、先代に聞こうと思っていたが聞き忘れてしまった」との事でした。
この方は僧侶と云うより会社員風で気さくに話ができた。でも僧侶の仕事にはまだ慣れていないのか、ご朱印を頼むと
「判だけならいいけど書くことは出来ない」 と言った。48番西光寺もそうだったが49薬師の納経帳を見た事がないのだろうか。
霊場巡りも最後になると途中で諦めてしまう人が多く、ここまで来る人はいないのだろうか?
半僧坊が気になり調べてみると
「半僧坊信仰が全国に広まったのは明治時代で、方広寺の山火事の際、円明大師(無文元選禅師)の墓と方広寺の鎮守 「半僧坊」
が類焼を免れたことから、半僧坊の威徳によるものという評判が広まり、半僧坊の信仰が全国に広がった。」 そうです。
そうか 「半僧坊」 とは方広寺だけの守り神ではなく、宗派にかかわらず寺の守護神になっているのか。
そう云えば藤枝の奥にある曹洞宗の盤脚院でも半僧坊を祀っていた。
49番を打ち終り、これで遠江薬師の札所49寺と番外、客番2寺、合わせて51寺全てを打ち終り結願(けちがん)を迎える事ができた。
しかしどうと云う感激は湧いてこない。初めて霊場巡りをしたのは10年ほど前に、マイカーで四国88カ所を10日ほどで廻ったのだが、
その時は88番大窪寺で感激して涙ぐんでしまった。
翌年今度は歩き遍路で36日掛けて廻ったのだが、その時の感激は期待に反して薄いものだった。信仰心の薄い私は霊場巡りを
スタンプラリーのようにして廻っているので、仏様が感激と云うご利益を私には授けてくれなくなったのだろう。
でも、でもですよ、今回の約霊場巡りでは、般若心経だけでなく 「延命十句観音経」 を唱えていたら、いつの間にか暗唱できるように
なっていた。これが今回のご利益と思えば仏様はまだ私を見放してはいない。
「観世音。南無仏。与仏有因。与仏有縁。仏法相縁。常楽我浄。朝念観世音。暮念観世音。念念従心起。念念不離心。」
(かんぜおん、なむぶつ、よぶつういん、よぶつうえん、ぶっぽうそうえん、じょうらくがじょう、ちょうねんかんぜおん、
ぼねんかんぜおん、ねんねんじゅうしんき、ねんねんふりしん)
「南無大慈大悲観世音菩薩、種々重罪、五逆消滅、自他平等、即身成仏」
(なむだいじだいひかんぜおんぼさつ、しゅじゅじゅうざい、ごぎゃくしょうめつ、じたびょうどう、そくしんじょうぶつ)
意味? 私は門前の小僧と同じですので無理な事は聞かないでください。
*************** ================ ******************
satoさん、まだこのブログを見てくれているのでしょうか。
satoさんに催促されたのは去年の4月ですから、1年がかりで約束を果たした事になります。
遍路の観歩記を再開した時は、当時の事を覚えているか心配でしたが、写真やメモや地図を見ると不思議に思いだすものですね。
これなら今現在私には認知症の恐れはないと思いますが、時々日にちや曜日を忘れることが・・・・・・
しかし今日が何日で何曜日も関係ないオールサンデーの年金生活者にとっては、不要なデータで仕方ないかも。













































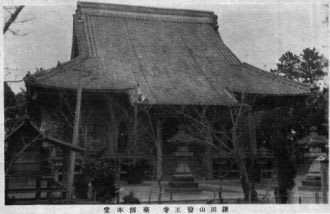
















































 こけらと
こけらと カキです。
カキです。





























