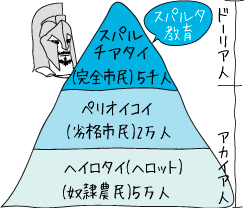ヴァイオラ:おなたのお人柄は分かりました、気位が高すぎます。
だがたとえあなたが悪魔だとしても、実にお美しい。
私の主人はあなたを愛しております。あのような愛には
報いてあげなければなりません、たとえあなたが
並ぶものなき美人であっても。
オリヴィア: どのように愛してくださるの?
ヴァイオラ: 神をあがめるように恋焦がれ、涙は滝のごとく、
切ないうめき声は嵐のごとく、ため息は火を吹かんばかり。
公爵: だからおまえも年下の女を恋人を持べきだ。
さもないとおまえの愛は長続きしないぞ。
女とはバラの花、その美しさははかないいのちだ、
散っていくのも一瞬、咲かないかのうちだ。
ヴァイオラ:それが女です、悲しいことにそれが女です、
花の盛りと見えるときが、散り行くときとおんなじです。
セバスチャン: ありがとう、アントーニオ、
おれにはありがとうと言うほか何の俺もできない、
ほんとうにありがとう。このようにせっかくの好意が
ただの言葉でしか報いられない例はよくあること、
だが、おれの財産がおれの真心のど豊かであれば
ちゃんとお礼がしたい気持ちはわかってくれ。
だがたとえあなたが悪魔だとしても、実にお美しい。
私の主人はあなたを愛しております。あのような愛には
報いてあげなければなりません、たとえあなたが
並ぶものなき美人であっても。
オリヴィア: どのように愛してくださるの?
ヴァイオラ: 神をあがめるように恋焦がれ、涙は滝のごとく、
切ないうめき声は嵐のごとく、ため息は火を吹かんばかり。
(第一幕第五場)
公爵: だからおまえも年下の女を恋人を持べきだ。
さもないとおまえの愛は長続きしないぞ。
女とはバラの花、その美しさははかないいのちだ、
散っていくのも一瞬、咲かないかのうちだ。
ヴァイオラ:それが女です、悲しいことにそれが女です、
花の盛りと見えるときが、散り行くときとおんなじです。
(第二幕第四場)
セバスチャン: ありがとう、アントーニオ、
おれにはありがとうと言うほか何の俺もできない、
ほんとうにありがとう。このようにせっかくの好意が
ただの言葉でしか報いられない例はよくあること、
だが、おれの財産がおれの真心のど豊かであれば
ちゃんとお礼がしたい気持ちはわかってくれ。
(第三幕第三場)