一人の女性の生き様を、桜になぞらえて描く。桜の24時間を八つに分断して、十代から八十代までのその女性の生きた軌跡を描き切った小説、それが『花の影』。夫を捨ててまで一緒に版画画家と暮らした母親と同様に、版画画家の息子と恋に落ちたものの、互いのすれ違いから結婚することなく、男の影を引きずりつつ、影の存在として一生を終えた幸せな女性の物語は、こんな具合に桜になぞらえられている。
十八歳のとき
夜のすみに、僅かに白さが感じられるほどの時刻であった。
二十四歳のとき
午後六時の桜は、ごく薄い靄の中に居た。どこか、もったいぶってみえるのは、用心深さのせいであった。朝の桜は、これからの自分になにが起こってくるのかまるでわかっていない。
やがて陽が靄のふちを通ってオレンジ色に輝きだすと、花は初々しさに満ちた。若い自信と不安が、花の両側にある。それが、この時刻の花の魅力のようであった。
三十五歳の時
午前九時の桜は、細い雨の中で、なにかに耐えているようにみえた。
もっとも、濡れた花の色は一層、うす紅を増し、花片にはお雨をはじき返すほどの弾力があった。
この季節の雨は、花の美しさにしっとしているようなところがあって、きれいに咲いた花の上に限って容赦なく振り続ける。
それでも、花は、毅然とした貌を決してうつむけなかった。
四十歳のとき
正午の桜はこの時期にしては明るすぎるほどの日差しの中で、あでやかに咲いていた。
薄紅色の小さな花は、一本の枝に丸く群がるように咲き誇っているのに、どこか寂びしげにみえるよは、広すぎるほどの空と入り組んだ備前の海を背景にしている所為かもしれなかった。
五十一歳のとき
午後三時の桜は、どこかで自分の運命を甘受しているようなところがあった。
やがて訪れてくる夕暮を待つ間の、ほのかな倦怠の中で放心したように人生をみつめていることが多い。その貌は、常に寂しげだったが、寂しさが身についてしまった落ち着きがある。そして、花は、自分がもう満開のときを過ぎているのに気が付いていた。
六十一歳のとき
夕暮れの桜は、漸く強くなりはじめた風の中にあった。
たそがれに、花は白く、まだ色も香もある風情であったが、桜はそれを恥じるかのように、貌をそむけている。
夜の暗さの近づくのを、花が強風に耐えながら、ひとすら待ち続けているようであった。
七十歳のとき
午後九時の桜は、月光の中にあった。そのせいか、花は昼よりも蒼味を帯びて見える
夜の帳は桜の周囲に会った余計なものを少しずつ闇の中に包み込んでいた。
それは、花にとって、わずらわしさはなくなったものの、なにかした物足りない、寂しげな気分であった違いない。
それでも、桜の老樹は大地にしっかり根を下ろし、梢の花は玲瓏と光り輝いていた。
八十二歳のとき
真夜中の桜は、無数の星を頂いていた。
或る星は、間近く光、或る星ははるか彼方の大空から桜を見守っていた。
星かありを花片に受けて、桜は闇の中でしらじらと気品に満ちている。
そして、花はすでにちるための身支度をはじめていた。
この春に、なにかし残したことがありはしないかと、静かに自分の周辺をみつめながら、やがて来る風を穏やかに待っている気配であった。
十八歳のとき
夜のすみに、僅かに白さが感じられるほどの時刻であった。
二十四歳のとき
午後六時の桜は、ごく薄い靄の中に居た。どこか、もったいぶってみえるのは、用心深さのせいであった。朝の桜は、これからの自分になにが起こってくるのかまるでわかっていない。
やがて陽が靄のふちを通ってオレンジ色に輝きだすと、花は初々しさに満ちた。若い自信と不安が、花の両側にある。それが、この時刻の花の魅力のようであった。
三十五歳の時
午前九時の桜は、細い雨の中で、なにかに耐えているようにみえた。
もっとも、濡れた花の色は一層、うす紅を増し、花片にはお雨をはじき返すほどの弾力があった。
この季節の雨は、花の美しさにしっとしているようなところがあって、きれいに咲いた花の上に限って容赦なく振り続ける。
それでも、花は、毅然とした貌を決してうつむけなかった。
四十歳のとき
正午の桜はこの時期にしては明るすぎるほどの日差しの中で、あでやかに咲いていた。
薄紅色の小さな花は、一本の枝に丸く群がるように咲き誇っているのに、どこか寂びしげにみえるよは、広すぎるほどの空と入り組んだ備前の海を背景にしている所為かもしれなかった。
五十一歳のとき
午後三時の桜は、どこかで自分の運命を甘受しているようなところがあった。
やがて訪れてくる夕暮を待つ間の、ほのかな倦怠の中で放心したように人生をみつめていることが多い。その貌は、常に寂しげだったが、寂しさが身についてしまった落ち着きがある。そして、花は、自分がもう満開のときを過ぎているのに気が付いていた。
六十一歳のとき
夕暮れの桜は、漸く強くなりはじめた風の中にあった。
たそがれに、花は白く、まだ色も香もある風情であったが、桜はそれを恥じるかのように、貌をそむけている。
夜の暗さの近づくのを、花が強風に耐えながら、ひとすら待ち続けているようであった。
七十歳のとき
午後九時の桜は、月光の中にあった。そのせいか、花は昼よりも蒼味を帯びて見える
夜の帳は桜の周囲に会った余計なものを少しずつ闇の中に包み込んでいた。
それは、花にとって、わずらわしさはなくなったものの、なにかした物足りない、寂しげな気分であった違いない。
それでも、桜の老樹は大地にしっかり根を下ろし、梢の花は玲瓏と光り輝いていた。
八十二歳のとき
真夜中の桜は、無数の星を頂いていた。
或る星は、間近く光、或る星ははるか彼方の大空から桜を見守っていた。
星かありを花片に受けて、桜は闇の中でしらじらと気品に満ちている。
そして、花はすでにちるための身支度をはじめていた。
この春に、なにかし残したことがありはしないかと、静かに自分の周辺をみつめながら、やがて来る風を穏やかに待っている気配であった。











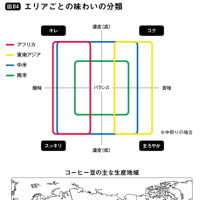








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます