
『顧客価値マーケティング入門 強い企業は絶えず顧客視点で考える』 岡本正耿・著、生産性出版、2003年11月。
物事を考える大前提を根本的に変えるのは、そう簡単ではない。なぜなら、今日の仕事は従来の考え方で行っており、その思考と行動を取りながら、新しい考え方に変えなければならないからである。実際に今日の製品は生産志向で作られているから、何とか無理して押し込み販売をしている。しかし、明日のためには顧客志向で売れるものを作ろうとする。そこで、企業の対応は大きく2つに分かれるようだ。ひとつは、完全に従来の生産志向や事実前提の考え方・やり方を否定する方法である。顧客志向のビジョンを新たに作り、そのビジョン実現の方向にすべてを変革してしまう。このやり方には、勇気と徹底が不可欠だが、成功した例も多く、うまくいく可能性が高い。
もうひとつのやり方は、基本的な考え方や仕事の仕方は従来と変わらず、表面的には顧客志向を標榜するというものである、実際には思考の前提が変わっていないから、物事は事実前提、内部的には効率追求で物事の話し合いが行われている。しかし、対外的には「お客様本位」と表明されている組織や、あるいは販売部門や顧客サービス部など、顧客と接点の多い部門では顧客志向を何とかしようとする。しかし、設計や生産部門、人事や財務部門が昔のままの効率追求、事実前提のままで考えているから、企業目的の二重構造が起きてしまう。いっていることとやっていることが違う、右手と左手の動きが伴わないのである。
いまだ生産志向で、無理やりの押し込み販売が通用しないのは当然であるが、この建前としての顧客志向と本音としての生産志向のダブル・スタンダードは企業のなかに随所にロスを生み出す。実際には変革する意思がないのに、無目的に行われている顧客満足度調査、顧客ニーズの有無が不確かなままの大量生産の垂直立ち上げなど、目的のあいまいさが生み出す混乱は企業収益をひどく圧迫している。 (p.14~15)
薬局は医薬分業率の向上で、量的拡大から質的拡大への転換、単なる薬局から「医療提供施設」への転換、会社から真の薬局への転換、医薬品の供給から安全管理への重心移動、など大きな転換期にある。
しかしいまだに処方せん獲得のための量的拡大思考で変化を乗り切ろうとしている向きが多々見受けられる。それが無理な出店やM&Aに現れている。
体質変換、時代の変化への抵抗か。現場には「変われ」と言いつつ、自分たちは変化しない上層部の問題。トップから本気を見せなきゃ、二重構造が顕著になるだけだ。事態の悪化はますます深刻になる。
一気に、全面的に転換を図る。しかし変わりたくないトップ層は、自らに英断を下せない。対外的に、社会的に、その地位にい続けることが許されないきっかけや引き金が起こらなければ、自浄作用は働かない。
社会がスピード感のある変化をして、ついていけなくなる現実をこれでもかというくらい見せつけられて、さぁどうなるだろうか。
物事を考える大前提を根本的に変えるのは、そう簡単ではない。なぜなら、今日の仕事は従来の考え方で行っており、その思考と行動を取りながら、新しい考え方に変えなければならないからである。実際に今日の製品は生産志向で作られているから、何とか無理して押し込み販売をしている。しかし、明日のためには顧客志向で売れるものを作ろうとする。そこで、企業の対応は大きく2つに分かれるようだ。ひとつは、完全に従来の生産志向や事実前提の考え方・やり方を否定する方法である。顧客志向のビジョンを新たに作り、そのビジョン実現の方向にすべてを変革してしまう。このやり方には、勇気と徹底が不可欠だが、成功した例も多く、うまくいく可能性が高い。
もうひとつのやり方は、基本的な考え方や仕事の仕方は従来と変わらず、表面的には顧客志向を標榜するというものである、実際には思考の前提が変わっていないから、物事は事実前提、内部的には効率追求で物事の話し合いが行われている。しかし、対外的には「お客様本位」と表明されている組織や、あるいは販売部門や顧客サービス部など、顧客と接点の多い部門では顧客志向を何とかしようとする。しかし、設計や生産部門、人事や財務部門が昔のままの効率追求、事実前提のままで考えているから、企業目的の二重構造が起きてしまう。いっていることとやっていることが違う、右手と左手の動きが伴わないのである。
いまだ生産志向で、無理やりの押し込み販売が通用しないのは当然であるが、この建前としての顧客志向と本音としての生産志向のダブル・スタンダードは企業のなかに随所にロスを生み出す。実際には変革する意思がないのに、無目的に行われている顧客満足度調査、顧客ニーズの有無が不確かなままの大量生産の垂直立ち上げなど、目的のあいまいさが生み出す混乱は企業収益をひどく圧迫している。 (p.14~15)
薬局は医薬分業率の向上で、量的拡大から質的拡大への転換、単なる薬局から「医療提供施設」への転換、会社から真の薬局への転換、医薬品の供給から安全管理への重心移動、など大きな転換期にある。
しかしいまだに処方せん獲得のための量的拡大思考で変化を乗り切ろうとしている向きが多々見受けられる。それが無理な出店やM&Aに現れている。
体質変換、時代の変化への抵抗か。現場には「変われ」と言いつつ、自分たちは変化しない上層部の問題。トップから本気を見せなきゃ、二重構造が顕著になるだけだ。事態の悪化はますます深刻になる。
一気に、全面的に転換を図る。しかし変わりたくないトップ層は、自らに英断を下せない。対外的に、社会的に、その地位にい続けることが許されないきっかけや引き金が起こらなければ、自浄作用は働かない。
社会がスピード感のある変化をして、ついていけなくなる現実をこれでもかというくらい見せつけられて、さぁどうなるだろうか。










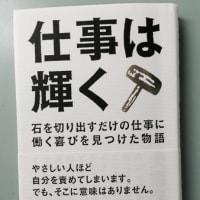
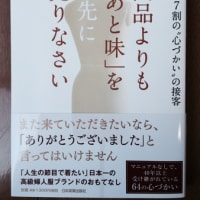
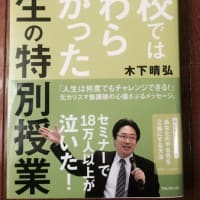
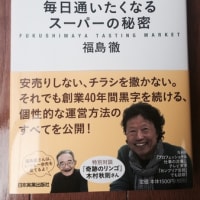
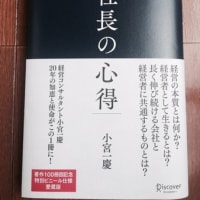
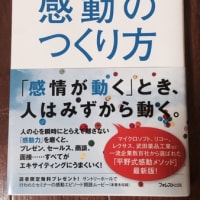
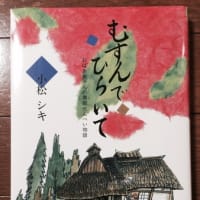
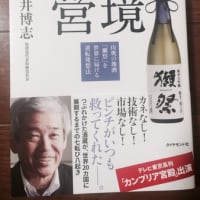
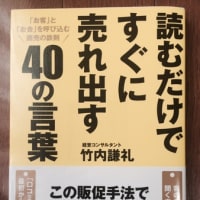
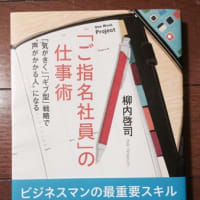






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます