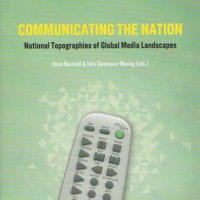正直、初めてヒッチハイクで旅をするのは、かなりの勇気がいた。ある種の恥ずかしさと同時に、大丈夫だろうか、という不安もあった。
しかし丁度この頃、電波少年というテレビ番組の企画で、猿岩石やパンヤオのヒッチハイクでの旅をやっていた。私は猿岩石の方は見ていなかったのだが、パンヤオがヒッチハイクにてアフリカ大陸を縦断する旅の様子はテレビで見ており、随分刺激を受けていた。
そして、何よりもケルアックの「路上」の世界が、私の頭の中にこびりついていた。あんな風に格好いい旅をしてみたい、生活が旅と一致する様な人生を送ってみたい。アメリカでの危険と隣り合わせのヒッチハイクに比べれば、日本でのヒッチハイクはきっと安全だし、まず大丈夫だろう、そう思って勇気を振り絞った。
コンビニでノートと太めのペンを買ってきて、一番最初に、確か「浜松」と書いたと記憶している。静岡だと近すぎるし、名古屋だと遠すぎると思われるかもしれない、そう思って「浜松」と、見開き2ページのノートにでかでかと書いたのだった。
そして、小田原市内の、高速道路へと続く道路で、ヒッチハイクを開始した。「浜松」と書かれたノートを頭上に高く掲げ、一生懸命笑顔を振りまいた。この笑顔には、何とかして車に停まってもらいたい、という思いと、何とかして目的地まで行くんだ、という自分を奮い立たせる思いが、交錯していた。
不安がまだ拭えていない、開始してから15分くらい経った時のことだった。一台の赤い小型車が、私を通り過ぎて30メートルほどした所で、路肩に付けてハザードを点滅させた。やった、一代目だ!そう思うと、私は車の所まで一目散に駆けて行った。
「珍しいな、ヒッチハイクなんて。浜松までは行かないけれど、途中までて良かったら乗せていくよ」
そう言って、30歳くらいの若い男性が、記念すべきヒッチハイク1代目の車となった。
「でも、猿岩石のおかげで、ヒッチハイクが市民権を得てよかったね。あの番組が無かったら、僕も君みたいなヒッチハイクの男性を乗せなかったと思うよ」
この男性は、そう言うと、立て続けに自分の話を始めた。彼はちょうど私と同じくらいの学生時代の時、随分と世界を旅したそうで、その世界旅行の様子をダイジェスト版で話して聞かせてくれた。ヒッチハイクの旅デビューの1代目の車としては、上出来だと思った。そして何よりも神奈川の海岸沿いの道路の景色が美しく、ヒッチハイクの開始地点としてはとても適した場所だと思った。話を聞きながら、この調子なら何とかなりそうだ、そう自信を付けた。
確か熱海を過ぎた辺りの所だったと思う、この男性は私に別れを告げると、高速の入り口で降ろしてくれた。よし、この調子だ、そう思って、また「浜松」と書かれたノートを広げ、ヒッチハイクを開始した。
その約20分後、次に停まってくれたのは、赤いホンダのスポーツカーだった。
「シートが無いからちょっと乗り心地が悪いかもしれないけれど、それでも良い?」
運転席から、おとなしい感じの細身の男性ドライバーが聞いてきた。助手席には、やはり大人しそうな女性が乗っており、何故か後部座席が取り除かれていて、2シーターの車の様な仕様となっていた。取り除かれた後部座席の所に、斜めに2本のパイプが渡してあり、乗車した私は、仕方なくそのパイプに捕まってバランスを取ることとなった。座席が無いので、仕方なく地べたにそのまま座り、両手でパイプを握っていたのだが、彼らがどうしてこんな車に乗っているのか分からず、一体何なのだろい?そう疑問に思っていた。
さらに、高速道路に入るやいなや、この車は警察に捕まってしまった。私は気付かなかったのだが、この車にはナンバープレートが付いていなかったのである。
「ナンバープレート、どうしたんですか?」
警察官がそう訪ねると、
「いやー、ちょっと前にぶつけた時に外れてしまって、そのままになってるんです。ほら、これがナンバーと外れてしまった部品です。すぐ直すので、勘弁してもらえますか?」
「違反は違反だから、書類はちゃんと書いてもらう。ナンバーもすぐに付け直す様に。それと、後ろのこの男は、誰だ?」
「いやー、旅の人で、ヒッチハイクをしているのをさっき拾ったのです」
「本当か?」
警官は私に訪ねたので、必死に
「本当です。さっき、乗せてもらいました」
と答えた。私はなんだか訳が分からないのだが、私も怪しまれているのでは、と思うと、不安な気持ちになり、即座に返答したのだった。
そういうやりとりがあった後、この男性は違反チケットを切られてしまったのだが、警官とのやりとりを終えると、彼の会話の雰囲気が変わってきた。彼の話しっぷりが、急に男っぽくなってきたのだ。
「いやー、チケット切られちゃったねー。でも大丈夫。俺達はもう高速の上!」
「きゃあ!」
女性も、なんだかはしゃいでいる。
「よーし、じゃあ、飛ばすよー」
「いやーん!」
何だ?何だ?
そう思うやいなや、この男性は、フルアクセルで東名高速道路を走り始めた。本当のフルアクセルだ。
比較的空いている東名高速道路上、周りの車をごぼう抜きにして行く。それにしても、私の座っている後部座席は、もの凄い振動とエンジン音で、どうなっているのか、訳が分からない。しかし、相当なスピードが出ていることだけは確かだ。ちょこっと中腰になってスピードメーターを見てみると、なんと時速240キロ!これはヤバイ、事故ったら死ぬな、後部座席のパイプに必死に捕まっていた私は、そう思った。
「きゃあ、もっともっと!」
「抜いちゃうよー。飛ばしちゃうよー。ほらほらー」
この男性、「こち亀」の本田警部みたいな人であった。先程までの大人しいキャラクターは陰を潜め、完全に目がイってしまい、別人と成り果てていた。そして、この時の私には、全く余裕が無かった。周りの車とのスピードの差がありすぎて、これは、下手したら、大変な事故になりかねない。とにかく、怖い!
そう思った矢先、車は突然スピードを落とし、次のインターチェンジで停車した。80キロくらいにスピードを落としただけで、私は周りの景色が止まってみえるほどだった。
「驚いた?驚かせちゃったら、ごめんね。走り屋ってのは、すぐ捕まっちゃうから、こうやってこまめに高速を降りるんだよ。いやー、楽しかったね」
「楽しかったー。サイコー、きゃあ!素敵!」
はあ、まったくどうなるかと思ったが、とりあえず無事で良かったし、目的地に向かってそれなりに進んだ気がする。そして何よりも、日本の高速を240キロとは、とても貴重な体験ができた。
この日はこんな調子で車を乗り継いで行き、浜松を過ぎた辺りの高速道路のインターチェンジのベンチに寝袋を広げ、そのまま野宿した。生まれて初めての野宿、そんな中、しとしとと降り始めた雨が、どことなく私の不安を煽った。朝日と共に目覚めると、どうも背中が痛く、疲れが全然取れていないことに気付いた。ああ、普段のベッドでの睡眠というのは疲れが取れるものなんだなぁ、そんな普通のことに気付かされた。
次の日も、「名古屋」とか「四日市」と掲げたノートを掲げてヒッチハイクを続けた。二日目となったせいか、ちょっと慣れて余裕が出てきて、楽しんでヒッチハイクができる様になってきた。
この日本国内ヒッチハイクの旅では、合計25台の車に乗車した。平均すると、大体20分で1台の車が止まるくらいのペースでヒッチハイクを続けることができた計算だ。やはり旅行好きの若い人や、専門職の人で好奇心旺盛な人が載せてくれるパターンが多かったが、何と言っても一度に長距離を稼げるのは、運搬用のトラックだった。トラックドライバーの人も見た目は怖いが愛嬌のある人が多く、その人の人柄を引き出して話をすれば、とても旅が面白くなる、そんなことに気が付いた。
そんな中、私の中の意外な才能が開花した。私は、どんな人とも上手く会話を発展させることができる様になったのだ。若い人だったら、彼らの興味関心のありそうなこと、専門職の人なら、その仕事について、旅が好きな人なら、彼らの今までの旅の話、そんな話を上手く引き出せる様になっていた。私も自分で関心したのだが、この2週間の旅の間、私はほぼ無休でしゃべり続けていた。一日平均して10時間程度、明石屋さんまか、と思うくらい話し続けていて、あごが痛くだった程だった。しゃべらないとその場が持たず、乗せてくれた人に申し訳ないから、というのが一点だが、頑張って面白い話をすると、「お前、腹減っているか?」という話になり、そのまま食事をご招待してもらえる、そんなパターンが多いことに気付いた。手持ちのお金が限られている中、食費が浮く、というのは本当に助かることだった。
そんな中、こんなトラックドライバーさんがいた。30歳前半、茶髪のどちらかと言うと寡黙な方で、義理人情のの世界に生きてそうな、ガッシリとした人だった。
「お前、何歳や」
「19です」
「若いなあ。ええ年やなぁ。やっぱり、それくらいの年やなぁ」
そう言うと、彼はしばらく遠くを眺めていた。あまり話したそうな雰囲気の人ではなかったので、彼の様子を見ながら、助手席に座った私は、私はぽつりぽつりと話を進めて行った。だんだん彼も心を開いてくれた様で、自分の身の上話をする様になってきた。
「お前、お腹すいとるか?俺が好きなおばちゃんの定食屋っちゅうのが、この近くにあるねん。おごってやるから、一緒に行こか?」
「ありがとうございます。それでは、ご馳走になりたいと思います。」
「ほな、行こうか」
そう答えると、どうやらトラックドライバーがたまるらしい、高速道路近くの定食屋に連れてってくれた。
「ここは鯖の煮付けが美味いんや。これにしとき」
「はい、ありがとうございます」
「兄さん、この子どうしたん?」
定食屋のおばちゃんがドライバーさんに尋ねた。
「こいつ、ヒッチハイクしとんねん。珍しいから、途中まで乗せてこう思うて、拾うたんや」
「そう、あんたも優しい所があるんだねぇ」
「あたりまえや。人として当然や」
そんな話をしているうちに、ドライバーさんはどうやらエンジンがかかってきた様だった。
「今晩はもう、一緒にトラックに寝ればええから、今日は一緒に飲もうや」
「ありがとうございます。もしよろしかったら、ご一緒させて下さい」
そう言うと、私たちは、日本酒をちびちび飲み始めた。
「実はなぁ・・・」
「はい?」
「俺なぁ、お前の顔を初めてみた時から、思ってたんやけれど、顔がどっか、俺の弟に似とんねんなぁ」
「そうですか?弟さんは、どんな方なんですか?」
そう聞くと、彼はお猪口の中に一杯になっていた日本酒を、一気に飲み干した。私は、すかさず、店のおばちゃんに熱燗を一つ追加で頼み、すぐさまお酌をすると、話を聞くモードへと入った。
「うちの弟は、家族でも自慢の弟やった。うちは2人兄弟さかい、俺と弟だけや。俺は才能もなんもなかったから、こんな仕事しているんやけれど、弟は立派やった。野球が上手くて、甲子園に出たんや」
「それは凄いですね」
「そや、自慢の弟やった。地元でも有名で、将来はプロ野球選手になるんやないか、みんなそう思うてた。わいの家族の中で初めてやったんやが、大学ちゅう所にも行ったんや。俺も期待しとった。金銭的には大変やったけど、両親も俺も、一生懸命支えたんや」
「それは、良い家族ですね。弟さんも、きっと喜んだでしょう」
「それがや、あいつ、東京の大学行った途端にグレてしもうて、野球もやめて、それからどないな訳か、音信普通にやってしまったんや。俺も両親も、それはえらい心配したで。そしたら、家族の友人が、東京で弟を見かけたゆうやないか!」
「おお、それで、弟さんは元気だったんですか?」
「それがや、あいつ、どうやら新宿のホストクラブで働いとるらしいんや。その話聞いたら、両親とも、体壊してもうて、もううちの子やない、そんな息子を育てた記憶は無い、ゆうて、それから俺も一度も会っとらんのや」
「もしかしたら人違いかもしれませんよ。そのホストクラブを訪ねて確かめてみてはどうですか?」
「いや、人違いやない。その友人が、確かめてくれたっちゅうねん。確かに弟やったそうや。。。俺の弟、どないなってしもうたねん。それがなぁ、俺の弟、お前と同じ19のはずやさかい。お前を見取ったらなぁ、弟の姿と被って、悲しゅうて、悲しゅうて。。。うわぁぁぁぁぁぁんんんんんんーーー」
このドライバーさんは、大声を上げて、定食屋の中で泣いてしまった。おばちゃんも、周りの客も、私達を心配そうに見つめている。どうすることもできながったが、私はドライバーさんの肩を組んで、必死に慰めた。
「きっと、弟さんは、戻ってきますよ。自分が間違っていた、そう思って更正するはずです。その時を待ちましょう」
「そんな時が来るやろうか」
「来ます。きっと来ますって。だから、そんなに泣かないで。大丈夫ですって」
そうやって慰めて、そのまま、その晩は随分と深酒をした記憶がある。定食屋を出ると、ドライバーさんは、トラックの中で、ハンドルの上に足を組んだまま寝てしまい、私は助手席のシートをめいっぱい倒して、そこで寝込んだ。みんないろんな思いを抱えて仕事しているんだな、そう思いながら、長距離のトラックドライバーになった様な、不思議な夜を過ごした。
そのドライバーさんには、次の日、三重県の辺りまで乗せてもらった。
「今度、東京行く機会があったら、また飲もうな」
「そうですね。またご一緒しましょう」
そんな会話をして、がっちりと握手をして別れた。私は連絡先を聞かれなかったので、またどこかで会えたら良いね、そういうメッセージとして受け止めた。
さあ、那智の瀧まで、もうすぐだ。
しかし丁度この頃、電波少年というテレビ番組の企画で、猿岩石やパンヤオのヒッチハイクでの旅をやっていた。私は猿岩石の方は見ていなかったのだが、パンヤオがヒッチハイクにてアフリカ大陸を縦断する旅の様子はテレビで見ており、随分刺激を受けていた。
そして、何よりもケルアックの「路上」の世界が、私の頭の中にこびりついていた。あんな風に格好いい旅をしてみたい、生活が旅と一致する様な人生を送ってみたい。アメリカでの危険と隣り合わせのヒッチハイクに比べれば、日本でのヒッチハイクはきっと安全だし、まず大丈夫だろう、そう思って勇気を振り絞った。
コンビニでノートと太めのペンを買ってきて、一番最初に、確か「浜松」と書いたと記憶している。静岡だと近すぎるし、名古屋だと遠すぎると思われるかもしれない、そう思って「浜松」と、見開き2ページのノートにでかでかと書いたのだった。
そして、小田原市内の、高速道路へと続く道路で、ヒッチハイクを開始した。「浜松」と書かれたノートを頭上に高く掲げ、一生懸命笑顔を振りまいた。この笑顔には、何とかして車に停まってもらいたい、という思いと、何とかして目的地まで行くんだ、という自分を奮い立たせる思いが、交錯していた。
不安がまだ拭えていない、開始してから15分くらい経った時のことだった。一台の赤い小型車が、私を通り過ぎて30メートルほどした所で、路肩に付けてハザードを点滅させた。やった、一代目だ!そう思うと、私は車の所まで一目散に駆けて行った。
「珍しいな、ヒッチハイクなんて。浜松までは行かないけれど、途中までて良かったら乗せていくよ」
そう言って、30歳くらいの若い男性が、記念すべきヒッチハイク1代目の車となった。
「でも、猿岩石のおかげで、ヒッチハイクが市民権を得てよかったね。あの番組が無かったら、僕も君みたいなヒッチハイクの男性を乗せなかったと思うよ」
この男性は、そう言うと、立て続けに自分の話を始めた。彼はちょうど私と同じくらいの学生時代の時、随分と世界を旅したそうで、その世界旅行の様子をダイジェスト版で話して聞かせてくれた。ヒッチハイクの旅デビューの1代目の車としては、上出来だと思った。そして何よりも神奈川の海岸沿いの道路の景色が美しく、ヒッチハイクの開始地点としてはとても適した場所だと思った。話を聞きながら、この調子なら何とかなりそうだ、そう自信を付けた。
確か熱海を過ぎた辺りの所だったと思う、この男性は私に別れを告げると、高速の入り口で降ろしてくれた。よし、この調子だ、そう思って、また「浜松」と書かれたノートを広げ、ヒッチハイクを開始した。
その約20分後、次に停まってくれたのは、赤いホンダのスポーツカーだった。
「シートが無いからちょっと乗り心地が悪いかもしれないけれど、それでも良い?」
運転席から、おとなしい感じの細身の男性ドライバーが聞いてきた。助手席には、やはり大人しそうな女性が乗っており、何故か後部座席が取り除かれていて、2シーターの車の様な仕様となっていた。取り除かれた後部座席の所に、斜めに2本のパイプが渡してあり、乗車した私は、仕方なくそのパイプに捕まってバランスを取ることとなった。座席が無いので、仕方なく地べたにそのまま座り、両手でパイプを握っていたのだが、彼らがどうしてこんな車に乗っているのか分からず、一体何なのだろい?そう疑問に思っていた。
さらに、高速道路に入るやいなや、この車は警察に捕まってしまった。私は気付かなかったのだが、この車にはナンバープレートが付いていなかったのである。
「ナンバープレート、どうしたんですか?」
警察官がそう訪ねると、
「いやー、ちょっと前にぶつけた時に外れてしまって、そのままになってるんです。ほら、これがナンバーと外れてしまった部品です。すぐ直すので、勘弁してもらえますか?」
「違反は違反だから、書類はちゃんと書いてもらう。ナンバーもすぐに付け直す様に。それと、後ろのこの男は、誰だ?」
「いやー、旅の人で、ヒッチハイクをしているのをさっき拾ったのです」
「本当か?」
警官は私に訪ねたので、必死に
「本当です。さっき、乗せてもらいました」
と答えた。私はなんだか訳が分からないのだが、私も怪しまれているのでは、と思うと、不安な気持ちになり、即座に返答したのだった。
そういうやりとりがあった後、この男性は違反チケットを切られてしまったのだが、警官とのやりとりを終えると、彼の会話の雰囲気が変わってきた。彼の話しっぷりが、急に男っぽくなってきたのだ。
「いやー、チケット切られちゃったねー。でも大丈夫。俺達はもう高速の上!」
「きゃあ!」
女性も、なんだかはしゃいでいる。
「よーし、じゃあ、飛ばすよー」
「いやーん!」
何だ?何だ?
そう思うやいなや、この男性は、フルアクセルで東名高速道路を走り始めた。本当のフルアクセルだ。
比較的空いている東名高速道路上、周りの車をごぼう抜きにして行く。それにしても、私の座っている後部座席は、もの凄い振動とエンジン音で、どうなっているのか、訳が分からない。しかし、相当なスピードが出ていることだけは確かだ。ちょこっと中腰になってスピードメーターを見てみると、なんと時速240キロ!これはヤバイ、事故ったら死ぬな、後部座席のパイプに必死に捕まっていた私は、そう思った。
「きゃあ、もっともっと!」
「抜いちゃうよー。飛ばしちゃうよー。ほらほらー」
この男性、「こち亀」の本田警部みたいな人であった。先程までの大人しいキャラクターは陰を潜め、完全に目がイってしまい、別人と成り果てていた。そして、この時の私には、全く余裕が無かった。周りの車とのスピードの差がありすぎて、これは、下手したら、大変な事故になりかねない。とにかく、怖い!
そう思った矢先、車は突然スピードを落とし、次のインターチェンジで停車した。80キロくらいにスピードを落としただけで、私は周りの景色が止まってみえるほどだった。
「驚いた?驚かせちゃったら、ごめんね。走り屋ってのは、すぐ捕まっちゃうから、こうやってこまめに高速を降りるんだよ。いやー、楽しかったね」
「楽しかったー。サイコー、きゃあ!素敵!」
はあ、まったくどうなるかと思ったが、とりあえず無事で良かったし、目的地に向かってそれなりに進んだ気がする。そして何よりも、日本の高速を240キロとは、とても貴重な体験ができた。
この日はこんな調子で車を乗り継いで行き、浜松を過ぎた辺りの高速道路のインターチェンジのベンチに寝袋を広げ、そのまま野宿した。生まれて初めての野宿、そんな中、しとしとと降り始めた雨が、どことなく私の不安を煽った。朝日と共に目覚めると、どうも背中が痛く、疲れが全然取れていないことに気付いた。ああ、普段のベッドでの睡眠というのは疲れが取れるものなんだなぁ、そんな普通のことに気付かされた。
次の日も、「名古屋」とか「四日市」と掲げたノートを掲げてヒッチハイクを続けた。二日目となったせいか、ちょっと慣れて余裕が出てきて、楽しんでヒッチハイクができる様になってきた。
この日本国内ヒッチハイクの旅では、合計25台の車に乗車した。平均すると、大体20分で1台の車が止まるくらいのペースでヒッチハイクを続けることができた計算だ。やはり旅行好きの若い人や、専門職の人で好奇心旺盛な人が載せてくれるパターンが多かったが、何と言っても一度に長距離を稼げるのは、運搬用のトラックだった。トラックドライバーの人も見た目は怖いが愛嬌のある人が多く、その人の人柄を引き出して話をすれば、とても旅が面白くなる、そんなことに気が付いた。
そんな中、私の中の意外な才能が開花した。私は、どんな人とも上手く会話を発展させることができる様になったのだ。若い人だったら、彼らの興味関心のありそうなこと、専門職の人なら、その仕事について、旅が好きな人なら、彼らの今までの旅の話、そんな話を上手く引き出せる様になっていた。私も自分で関心したのだが、この2週間の旅の間、私はほぼ無休でしゃべり続けていた。一日平均して10時間程度、明石屋さんまか、と思うくらい話し続けていて、あごが痛くだった程だった。しゃべらないとその場が持たず、乗せてくれた人に申し訳ないから、というのが一点だが、頑張って面白い話をすると、「お前、腹減っているか?」という話になり、そのまま食事をご招待してもらえる、そんなパターンが多いことに気付いた。手持ちのお金が限られている中、食費が浮く、というのは本当に助かることだった。
そんな中、こんなトラックドライバーさんがいた。30歳前半、茶髪のどちらかと言うと寡黙な方で、義理人情のの世界に生きてそうな、ガッシリとした人だった。
「お前、何歳や」
「19です」
「若いなあ。ええ年やなぁ。やっぱり、それくらいの年やなぁ」
そう言うと、彼はしばらく遠くを眺めていた。あまり話したそうな雰囲気の人ではなかったので、彼の様子を見ながら、助手席に座った私は、私はぽつりぽつりと話を進めて行った。だんだん彼も心を開いてくれた様で、自分の身の上話をする様になってきた。
「お前、お腹すいとるか?俺が好きなおばちゃんの定食屋っちゅうのが、この近くにあるねん。おごってやるから、一緒に行こか?」
「ありがとうございます。それでは、ご馳走になりたいと思います。」
「ほな、行こうか」
そう答えると、どうやらトラックドライバーがたまるらしい、高速道路近くの定食屋に連れてってくれた。
「ここは鯖の煮付けが美味いんや。これにしとき」
「はい、ありがとうございます」
「兄さん、この子どうしたん?」
定食屋のおばちゃんがドライバーさんに尋ねた。
「こいつ、ヒッチハイクしとんねん。珍しいから、途中まで乗せてこう思うて、拾うたんや」
「そう、あんたも優しい所があるんだねぇ」
「あたりまえや。人として当然や」
そんな話をしているうちに、ドライバーさんはどうやらエンジンがかかってきた様だった。
「今晩はもう、一緒にトラックに寝ればええから、今日は一緒に飲もうや」
「ありがとうございます。もしよろしかったら、ご一緒させて下さい」
そう言うと、私たちは、日本酒をちびちび飲み始めた。
「実はなぁ・・・」
「はい?」
「俺なぁ、お前の顔を初めてみた時から、思ってたんやけれど、顔がどっか、俺の弟に似とんねんなぁ」
「そうですか?弟さんは、どんな方なんですか?」
そう聞くと、彼はお猪口の中に一杯になっていた日本酒を、一気に飲み干した。私は、すかさず、店のおばちゃんに熱燗を一つ追加で頼み、すぐさまお酌をすると、話を聞くモードへと入った。
「うちの弟は、家族でも自慢の弟やった。うちは2人兄弟さかい、俺と弟だけや。俺は才能もなんもなかったから、こんな仕事しているんやけれど、弟は立派やった。野球が上手くて、甲子園に出たんや」
「それは凄いですね」
「そや、自慢の弟やった。地元でも有名で、将来はプロ野球選手になるんやないか、みんなそう思うてた。わいの家族の中で初めてやったんやが、大学ちゅう所にも行ったんや。俺も期待しとった。金銭的には大変やったけど、両親も俺も、一生懸命支えたんや」
「それは、良い家族ですね。弟さんも、きっと喜んだでしょう」
「それがや、あいつ、東京の大学行った途端にグレてしもうて、野球もやめて、それからどないな訳か、音信普通にやってしまったんや。俺も両親も、それはえらい心配したで。そしたら、家族の友人が、東京で弟を見かけたゆうやないか!」
「おお、それで、弟さんは元気だったんですか?」
「それがや、あいつ、どうやら新宿のホストクラブで働いとるらしいんや。その話聞いたら、両親とも、体壊してもうて、もううちの子やない、そんな息子を育てた記憶は無い、ゆうて、それから俺も一度も会っとらんのや」
「もしかしたら人違いかもしれませんよ。そのホストクラブを訪ねて確かめてみてはどうですか?」
「いや、人違いやない。その友人が、確かめてくれたっちゅうねん。確かに弟やったそうや。。。俺の弟、どないなってしもうたねん。それがなぁ、俺の弟、お前と同じ19のはずやさかい。お前を見取ったらなぁ、弟の姿と被って、悲しゅうて、悲しゅうて。。。うわぁぁぁぁぁぁんんんんんんーーー」
このドライバーさんは、大声を上げて、定食屋の中で泣いてしまった。おばちゃんも、周りの客も、私達を心配そうに見つめている。どうすることもできながったが、私はドライバーさんの肩を組んで、必死に慰めた。
「きっと、弟さんは、戻ってきますよ。自分が間違っていた、そう思って更正するはずです。その時を待ちましょう」
「そんな時が来るやろうか」
「来ます。きっと来ますって。だから、そんなに泣かないで。大丈夫ですって」
そうやって慰めて、そのまま、その晩は随分と深酒をした記憶がある。定食屋を出ると、ドライバーさんは、トラックの中で、ハンドルの上に足を組んだまま寝てしまい、私は助手席のシートをめいっぱい倒して、そこで寝込んだ。みんないろんな思いを抱えて仕事しているんだな、そう思いながら、長距離のトラックドライバーになった様な、不思議な夜を過ごした。
そのドライバーさんには、次の日、三重県の辺りまで乗せてもらった。
「今度、東京行く機会があったら、また飲もうな」
「そうですね。またご一緒しましょう」
そんな会話をして、がっちりと握手をして別れた。私は連絡先を聞かれなかったので、またどこかで会えたら良いね、そういうメッセージとして受け止めた。
さあ、那智の瀧まで、もうすぐだ。
 | 十九歳の地図・蛇淫 他―中上健次選集〈11〉 (小学館文庫)中上 健次小学館このアイテムの詳細を見る |