最初の数カットの美しさ。
アメリカの田舎の道路沿いの、雑草の茂る場所に立つ3枚のビルボード。
薄曇りのもやにおおわれた何気ない風景がほんとうにきれいで、
ここで流れる曲「庭の千草」も美しい。
(アイルランド民謡?「夏の名残のばら(The Last Rose of Summer)」とも)
昔、わたしのバイオリンの先生の先生が、発表会の時に弾いてくれた曲で、
この曲にまつわる、ご自分のやさしい思い出の話をされて、
またその演奏がとてもよくて、わたしも涙が出たのを覚えてる。
35歳で初めてバイオリンをマレーシアで始めたわたしは、その後日本帰国後にも
いい先生に数年習い、子供達と一緒に初めて発表会に出ることになったのだけど、
その年から始めてここまで弾けるようになったのはとても立派ですと褒めてくださった。
すごく一生懸命練習してたのでうれしかった。
直に習ったことはないんだけど、大好きな先生の先生は、素敵な年配でした。
そのきれいな風景シーンのあと、場面が変わり、街の広告屋に入っていく主人公が出てくる。
この場面のカメラもよくて、期待が高まる。この後はもう最後まで引き込まれ
その後のドラマがもう、いちいち深いというか複雑に絡んで話が進んでいく様が、もうすごい手練れ。
いろんな人間の少しずつの行き過ぎや執念が引き起こす事件たち。
短絡な暴力男さえ、きっちり深く造形され、その作りの丁寧さに参りました。
人物造形いおいては類型的なものをどんどん外しているんだけど、
外していると感じさせない説得力があるんです。リアリティというか。
実際の人間はそうそう類型的ではないものですからね。
この映画のあとに続けて「グレイテスト・ショーマン」を見たんですよ。
「グレイテスト・ショーマン」も悪くはなかったんだけど、見てる間、
あーこんなの見てる間に「スリービルボード」の感動が薄まっちゃうー!と焦るくらい
「スリービルボード」は良かったのです。名作。
そして、ラストがまた絶妙な切り取り具合というか突き放し具合というか、
この先どうなるのかは観客の方へ投げかけられている形で終わります。
こうなるに決まってる、こういう意味だよね、とか決めつけてしまえない感じで
あれこれ想像はするし、こうなってほしいとは思うけど、
人間って因業だからなぁと思ったり、いやいや、信じようと思ったり。
でも、あまり希望のない話だし、救いもあると言うよりは、ない方が近いけど、
あと味を悪くしすぎない余韻は残ります。うまいなぁ。
いやー。本当にいい映画。
自分の好みは、ヨーロッパの短編小説みたいな映画なんですけど、
素晴らしい素晴らしいアメリカ文学を読んだ後みたいな気分になる。
もう好みかどうかとか吹っ飛んで、いい映画を見た充実感でいっぱいになりました。
お話は、ミズーリ州の田舎町で、娘をレイプされ殺された女性が
警察の怠慢を糾弾するかのような挑発的立て看板を3枚立てる。
「レイプされて殺された」「犯人逮捕はまだ?」「なぜ? ウィロビー署長」。
犯人を捕まえるために手段を選ばない女性、
強く優しく、町の人に愛されている警察署長、
警察署長を慕っているが、差別的で暴力的な警察官の3人が主な登場人物で
3枚の看板が町にもたらす軋轢、行き違い、暴力、事件などを、
3人それぞれの人生とともに描いていく。
ここからめっちゃネタバレになります。
ネタバレ嫌な人は、映画見てから読んで。笑
・
・
・
・
・
3人の主な登場人物について思うこと。
まず、ミルドレッド。アカデミー主演女優賞とったフランシス・マクドーマンド。
この人、冒頭シーンの強引で強気なやりとりや硬い表情を見ても、
悲しい事件で心を閉ざした人なのだなぁと、共感しかけるんですよ、最初のうちは。
それなりに努力してくれる署長に対して厳しすぎるし、彼の事情を思うとちょっと冷たすぎるとも思うけど
それでも癒えない傷があるのだと思えばまだ理解できた。
最初の方では、少し極端でも、特に人に危害を加えるものではないように見えたし。
でも後半はもう無理でしたねぇ。
嘘はつく、暴力もどんどんやる。手段を選ばない。
正義のためでも、死んだ娘のためでさえなく、これはもう、ただの執念ですね。
執念に支配されてて誰をどう傷つけても構わないくらいの勢いだから。
たとえば小人症男性の好意を、高飛車に利用したあげく突き放すのもひどいけど
あれは相手が小人症だからではなく、彼女は誰でもあんな風に利用するわけで
そういう点では、そこに差別はないので、そこはまだ許せた。(嫌な感じだけど)
それより、わたしが特に無理と思ったのは、彼女の息子のことです。
町中がミルドレッドを憎む中で、彼は学校でもひどい目にあう。
そしてそれ以前に彼自身も姉が無残に殺されたことはつらくて、
まだ消化できていないのに、執着の塊になっている母親のせいで
姉の死を忘れる余地がまったくなく、常につらいことを意識させられ続けている。
ミルドレッドの執着は死んだ娘のためということになっているのだろうけど、
それが生きている息子を傷つけていることもわかってて、それなのにやめないのね。
自分は間違っていない、あるいは間違ってても許されることなんだという狂信。
すっかり後回しにされてる、この息子がかわいそうでかわいそうで。
この子は母に反発するシーンも多いけど優しい子で、ところどころ、
それでも親子の繋がりの見えるようなシーンもあって、
母親はもう少しこの息子のこと考えてあげたらいいのにと何度も思った。
下手したら息子も死んでしまうよ。母のせいで、それ、って。
ただ、狂信的な人間は、最も苦手なもののひとつだけど、
わずかながらでも、彼女の優しいところ、話の通じるところも見せているので
とことん嫌いにはなれないんですね。そういうところが映画としてうまい。
次に警察署長。
予告編で見るよりずっと、いい人。いい男。
最初のシーンではマッチョな警官にしか見えなかったけど、
暴力的な部下の警官を止めて諭しながらも、彼のいいところも見抜いているし
ミルドレッドの名指しの非難にも、彼女を憎みはせず、公正に対処しようとする。
そして家族との関わりの部分は、とてもいいです。
強くて優しい、アメリカの理想の父親みたいな人。
それで病気で死んでしまって、彼の残した手紙が、それぞれ泣かせるんだけど
ここでね、わたしは彼のちょっと意地悪なところを思うんですよ。
ミルドレッドへの手紙で、町中に愛されてた自分の自殺で
町中からの憎悪がミルドレッドに向かうことが、わかってたんですよね、彼は。
それで、ミルドレッドに犯人を捕まえられな語っことを謝り釈明しつつ、また
自分の自殺は君には関係ないことだと書きつつ、
でも町の人はそう思わない人も多いだろうから君は苦労するだろう、だけどまあ、
頑張ってね〜、みたいなことが書いてあって(うろ覚え、違ってたらごめん)
聖人君子のような、よくできた包容力と許しの力を持ってる人だけど
生きている人へのちょびっとの意地悪は、見せるんだなぁと。
今から死ぬ人間にとって、生きてる人間の苦労なんて大したことないのかもしれません。
それで、そういうちょっとの意地悪にも、ユーモアがある。
そういうところがあるからこそ、この人のキャラクターにも深みが出るのですね。
そして、アカデミー助演男優賞をとったサム・ロックウェル演じる警官。
いやはや、彼は本当に良かった。最終的に主演女優以上に良かったと思います。
単細胞でかっとしやすく暴力的で、無自覚ながらこてこての差別主義者の警官。
超超超嫌いなタイプです。なのに、なんとも憎めない・・・。
彼も最初のシーンではなんて嫌なやつ!と思うんです。
途中まではいちいち憤慨してしまうほどバカで勝手で暴力的な最低男なんですけどね、
でも、子犬がなつくように署長に心酔し、
彼以上の差別主義的短絡的な上に、支配的な母親と一緒に暮らす独身で、
(最初母親じゃなく同僚か何かのおっさんと思った雰囲気)
その生活の中でね、ああこの母親に育てられてこうなっちゃったんだ、
そしておそらくゲイなんだけど、そんなの母親にもマッチョな警察仲間にも
この古い土地のコミュニティの中にも受け入れられることではないので、
自分自身、自覚しないよう、気づかないようにしているんだ、という
彼の辛い部分も見えてきて、憎めなくなってしまったんです。
憎めなくというか、映画を見ている自分の視点が、彼らと同じところではなく
ちょっと上空から、神様の近くからの視点で見るような感じになってきて、
ダメな人の憎むべき忌まわしいところさえ、人間だものなぁと少し思うように。
そして後半になると変わっていくというか、彼の優しいところが出てきます。
死んだ署長からの手紙ひとつで改心したわけじゃなく、
その後の病院内での、許しを知ってる人の優しさに触れたりして、
考えを改めるようになるんです。とはいえ別人になるわけじゃないと思うけど。
他の登場人物、ミルドレッドの息子や元夫、署長の妻も丁寧に描かれていると思う。
映像も音楽もいいけど、中心になる3人だけでなく、主な登場人物みんなを
それぞれ多面的な描かれ方で描いている脚本が、やっぱり素晴らしい。
人間って本当にいろんな面が、表にも裏にも上にも奥にもあるものなんだよなぁ、
状況によって見える面はいろいろだから、
そこで誤解や理解や思いやりや憎悪やたくさんのことが入り混じって起こり、
どの人の人生も複雑なんだよなぁ、ということを、しっかり見せてくれた映画。












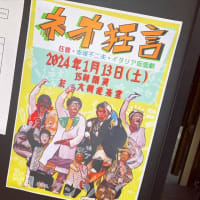





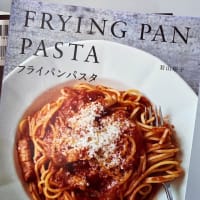

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます