わたしのティルダ・スウィントンが主演してるので内容もよく知らないまま見たけど、
なかなか大変な映画でした。
まず長回しが長い・・・。日本語変だけど、いやほんと長いのよ。
この長回しに関しては、台湾と中国の監督二人を思い出したのだけど、
ビー・ガン監督のように長回しでどんどん舞台が変わり映像も流れていくようなタイプではなく、
ツァイ・ミンリャン監督の「楽日」みたいな長回し。
うっかり寝落ちしてうとうとして起きてもまだ同じ場所から同じシーンのままって感じ。
中々観客に我慢を強いるやつです。これ映画館だから見れたけど、
家で見てたら早回しするし、そうするとこの映画の値打ちはほとんど消えてしまうから、
映画館で見るための映画ですね。
二人の監督を思い出したのは長回しだけでなく、南米コロンビアの景色や自然の中に
少し東南アジアの気配があるからかもしれない。気候は似てるのかな?
そして、物語や説明はなく、謎だけはあるけどそれに向かって何かが進み謎が解明されることもなく、
よくわからないまま終わる映画なので、スッキリした答えの欲しい人にはもどかしいかもしれません。
そしてティルダはハマり役。彼女の静かで乾いて中性的で、簡素でひんやりして
個性を押し出さない佇まいがこの映画にとても馴染んでる。(そしてその個性が逆にすごい)
人の物語ではないんですね、人も景色の一部みたいに
人と人が話すようなシーンでも顔のアップがほとんどなく、
やや俯瞰で距離を持って撮られているのは、特に誰にも共感したり感情移入したりせずに
自分の物語ではない別の世界を外側から見ている感じです。
そして何よりもこれは「音」の映画。
音の映画というと聾学校が舞台の佳作を2本「ミルコの光」(イタリア)と「イマジン」(ポーランド)を思い出すのだけど
耳の聞こえない人たちの間で目と耳の感覚を研ぎ澄ませられるこの2本に比べて、
「メモリア」はむしろ聞こえすぎる人の聞く非日常的な音で、
耳の中でも普段使わない音を聞く部分を刺激され緊張の中で他のあらゆる音も繊細に拾わされる感じ。
長いし途中うとうとしたところもあったけど、退屈はせずに見られました。
予告編を見るとイメージ先行の映像作品のように見えるけど
辻褄を考えなければ、一応物語のようなものはあります。
主人公の旅のあてどなさは、外側から見ると、生きていくのってこういう感じか?とも思う。
世界は謎で、何か大きな得体の知れないものもあって、人は彷徨いながら答えを探して、
見つかったり見つからなかったり、でも結局その過程だけでいいのかも、というようなことを思う。
映画には一応の答えのようなものもあるけど、はっきりはしません。
お話は、ある女性が頭の中の不快な爆音に悩んで眠れなくなり、その正体を突き止めようと
医者や考古学者や、音を作る仕事の人などを訪ねながら、そこの人々と話し
そしてたどり着いた森の中?で不思議な体験をして・・・というもの。
こういう映画は見る人を選ぶ。
わたしは年に60本くらい映画館で見る中で人と見るのは2、3本ですが
これは聴覚過敏に苦しんできた人と見ました。
冒頭しばらくの不快な音の続く間は、その人が苦しくないか気になって
わたしもしんどかったけど、見終わった後で、そこは辛かったけど見てよかったと言われでほっとした。
その人と最後に見た映画だけど、その人と見て良かったと思う。












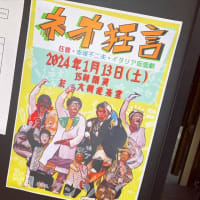





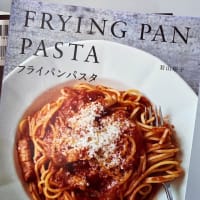

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます