ヴァンサン・カッセルは、エレガントでセクシーな悪魔や、
無駄に魅力的でダメな男の役が本当に素敵だけど、
この映画のゴーギャンの役は、ヨレヨレの汚いおじいさんで、
目だけが異様にギラッとしてて、見てて結構疲れました。
ヴァン・サンカッセルが男の色気や粋や悪さやダメさの味わいを封印して
芸術家というただの人間(狂気はあるかもしれないけど)になってるのが、
男としての彼を好きなわたしにはもったいないようなもどかしいような。
ゴッホは日本でもとてもポピュラーで、
その人生についても本や映画やいろんな情報を見てきて知ってるけど、
ゴーギャンがどんな感じの男だったかはよく知らなかったことに気づきました。
タヒチとそこの娘たちを描いた絵の印象が強いけど、
彼自身についてはほとんど知らなくて、ゴッホ経由の脇役的にしか知らなかった。
イタい困ったやつであるゴッホにあきれてアルルを去ったゴーギャンと思ってたけど
ゴーギャンも大概困った人だったのですねぇ。
ヨーロッパ人の南洋への憧れや、植民地での白人特権階級として
貧乏絵描きでも、もっと気楽にヒャッホーって感じで行ったのかと思ってたけど
やっぱりパリのような大都会の人にとって南洋の島への移住はおおごとだったのね。
かなりの決意で、パリを去ったようでした。
家族は付いてきてくれず、といっても、そもそも家族を養えてたわけでもないし、
なんだか逃避行っぽいタヒチ行きに見えました。
でも、タヒチにはもう夢の原始生活はなく、すでにヨーロッパ人が入り込み
ヨーロッパ文明からの影響があちこちに見られるようになっていることに失望。
植民地支配側の人間のくせに、勝手なものだなぁ、とは思いました。
独自の文明が衰退したのは、ヨーロッパ人が入ってきたせいで、
ヨーロッパ人の持ち込んだのは画一化された工業製品だけではなく
キリスト教の布教で原始的な宗教も消えつつあったのでした。
ヨーロッパ人からの感染病で原住民の人口も随分減ってたらしい。
それに苛立つゴーギャン。でも、やっぱり勝手な理屈ですよね、
現地の人たちのために苛立ってるのではなく、自分の憧れのために、だしね。
芸術バカとしか言えない人で、何よりも芸術。絵のことしか考えてない人。
エゴイストといえばエゴイストなんだけど、彼自身も「芸術」のしもべとして
振り回されているわけなので、本人にはどうしようもない、のは理解できるけど。
タヒチで彼と一緒に暮らす少女のポーズをとるシーンなどは、
本当に彼の絵そのままで美しくよく再現されています。
この少女の役の子も、いきいきと伸びやかで、とても美しい。
後半ゴーギャンが嫉妬から?彼女を閉じ込めるようなことをするけど
この辺はフィクションなのかな。
しかし、その後パリに戻っても、再びタヒチにいっても、
その次のマルティニークでも、常に現地の十代の少女を「妻」にしてたみたいで、
それを思うと、映画でどんなに芸術一筋に見えたにしても
支配国側の傲慢な白人オヤジというイメージで見てしまう。
絵は素晴らしいし、時代的な背景もあるけど、なんだかなぁ。
ゴーギャンは10代の頃は商船で世界中周り、海軍にも2年いて、そのあと
株式仲買人として成功していたんですね。元々は裕福だったんです。
でも1882年にパリの株式市場大暴落で、仲買人としても痛手を受け
絵を本業にするようになり貧窮したらしい。
この映画の後、パリに戻った後はなんだかんだいってもまだマシになって
そこそこ落ち着いた生活ができるようになったみたいなので、
この映画は一番貧しく評価もされないどん底の時期を描いているのですね。
どん底の果てに夢や理想から敗退するかのような明るさのない船出の、
この映画の終わり方はとてもいいのです。
画家本人もここで死んでたら、すがすがしかったのに、と勝手なことを思う。
うちにゴーギャンの画集はないんだけど、図書館で少し見てみたら、
若い頃は好みでなかったけど、今はかなり好きです。じっくり見てみたい。












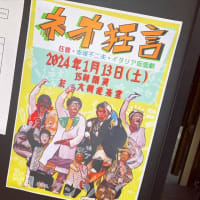





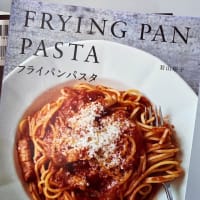

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます