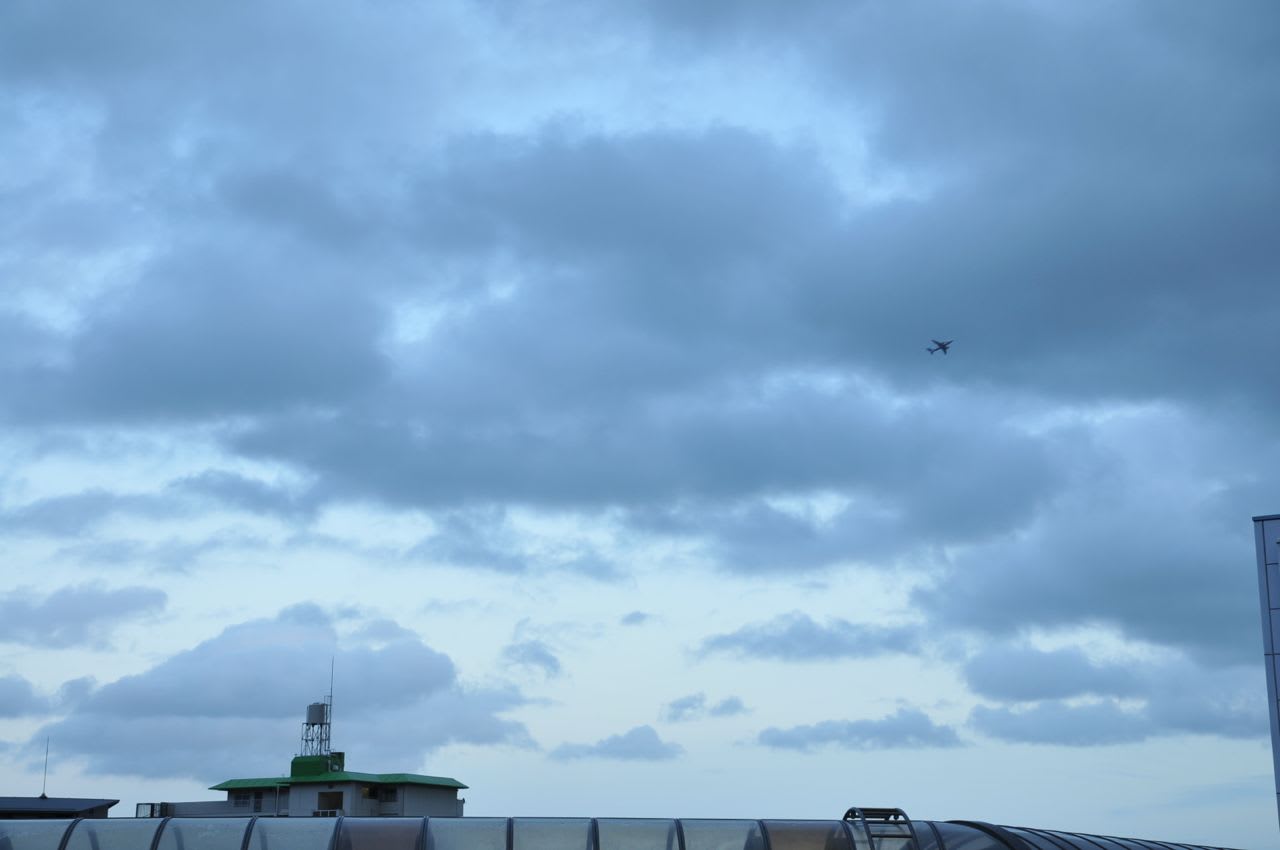自分はいつも、俳句をやってみたいと思いつつ
ご存知のように(笑)言葉が多い人間なので中々できない。
マレーシアに住んでいたときは日本語に餓えてて
日本の新聞衛星版の詩歌の投稿ページなどじっくり見ていました。
そこで勉強しようと思っても
何しろ四季がない常夏の国なので季語が遠くて難しかった。
帰国後、たまにうんうんひねってみると「盛りだくさんすぎ」と言われたりして
やっぱり言葉の多い理屈っぽい人間のままで、
そろそろ風通しのいい人間になりたいものです・・・。
それで、ときどき俳句や短歌の本も読みますが
いつまでたっても入門書を読んでいます。
「あなたの俳句はなぜ佳作どまりなのか」辻桃子
この人の書いた入門書っぽいのを前にも1冊読んだ気がする。
でもこの文庫は、とてもわかりやすいです。
わたしが未熟でまだ読む目をもってないからだろうけど
たまに、添削された句よりされる前の句の、
作者の言いたかったことの方が、大事なように思えることもあるけど、
それでも、その添削の理由にはいちいち納得させられます。
理屈になっとくできるのと、それを実践できるかは別ですから
ほほう!と思ってもきっと俳句は詠めないままだと思うけど。
みんなただ行きて死ぬ。私たちはその一瞬を一句に書き留めているだけだ。
切ないから「たのしい」と言って笑っているのだと言うことを、忘れないで。
てふてふに獣の顔のありにけり 辻桃子
ーーーーーーーーー
目玉焼き目玉幾つや避暑終る 大川桃鬼
「避暑終わる」の季がロマンチックに流れがちなのを「目玉幾つ」ととぼけたので俳味が濃くなり寂しさがにじみ出た。甘い叙情に「寂しい滑稽」が加わったら「鬼に金棒」だと思う。
ーーーーーーーーー
.....こういう季語の使い方はどんな場合も説明的だ。「・・・だから」と簡単に理由、理屈のつくものは詩ではないと肝に銘じておこう。俳句とはわけのわからないナンセンスなものであるゆえに、人間存在のわけの解らなさに直感的に突き刺さるものなのだ。
写生と言うのがどういうものなのか少しわかった気がするし
(「写生に徹せよ」というのは、「徹底的な写生の果てに、このような幻想を至らせたい」がゆえである。)
とにかく削ぐ、説明しては行けない、でも意味不明な抽象もよくない、
というようなことが、非常によくわかります。
「短歌があるじゃないか」 穂村弘/東奈緒子/沢田康彦
穂村さんの本は何冊か持ってる。仲良くなれそうに思う。笑
現代短歌は読むのは好きだけど自分でしようとは思わないです。
ちょっとセンチに流れやすい地のままがでそうなのがいやなのかな。
もっと刈り込んだ端正な形が好きなのでしょう。
この本はアマチュアの方の短歌を3人で対談風にあれこれ語ったものです。
敷居の低い短歌入門書と書かれている。
本当に何十年たっても入門書を読んでいるわたしです(笑)。
斎藤茂吉などがそうであるように、近代短歌というのは一人称で、結婚したら結婚の歌、子どもができたら子ども、お母さんが死んだら悲しみの歌を、というふうに日記みたいな連続性を持っているわけですよね。(穂村)
ーーーーーーーーーーーー
例えば歌人の水原紫苑さんにとっては「能」とかの世界がこれなんですよね。必ず人が死んで、死者との交感になる。生きてるもの同士ではこの世界はもうだめだから、片方が死んでいなければ本当の愛の世界は成就しないみたいなたちばとかもありうると。(穂村)
魚食めば魚の墓なる人の身か手向くるごとくくちづけにけり 水原紫苑
こんなにもふたりで空を見上げてる 生きてることがおいのりになる 穂村弘
ーーーーーーーーーーーー
大切なことをひとりで成し遂げにゆくときのための名前があるの 穂村弘
というように名前をつけるのはひとつの呪術なんですよね。
ーーーーーーーーーーーー
熱帯夜。ゴキブリの中みは赤と黄いろと緑。 穂村弘
天国の5秒手前にいる君をおくりとどけるアインシュタインの舌 伴水
わたしたち家につかない気がするわフロント・ガラスにふる鱗たち 加藤治郎
荷車に春のたまねぎ弾みつつ アメリカを見たいって感じの目だね 加藤治郎
雪を見て飲むあついお茶 わたしたちなんにも持たずにここに来ちゃった
東直子
ご存知のように(笑)言葉が多い人間なので中々できない。
マレーシアに住んでいたときは日本語に餓えてて
日本の新聞衛星版の詩歌の投稿ページなどじっくり見ていました。
そこで勉強しようと思っても
何しろ四季がない常夏の国なので季語が遠くて難しかった。
帰国後、たまにうんうんひねってみると「盛りだくさんすぎ」と言われたりして
やっぱり言葉の多い理屈っぽい人間のままで、
そろそろ風通しのいい人間になりたいものです・・・。
それで、ときどき俳句や短歌の本も読みますが
いつまでたっても入門書を読んでいます。
「あなたの俳句はなぜ佳作どまりなのか」辻桃子
この人の書いた入門書っぽいのを前にも1冊読んだ気がする。
でもこの文庫は、とてもわかりやすいです。
わたしが未熟でまだ読む目をもってないからだろうけど
たまに、添削された句よりされる前の句の、
作者の言いたかったことの方が、大事なように思えることもあるけど、
それでも、その添削の理由にはいちいち納得させられます。
理屈になっとくできるのと、それを実践できるかは別ですから
ほほう!と思ってもきっと俳句は詠めないままだと思うけど。
みんなただ行きて死ぬ。私たちはその一瞬を一句に書き留めているだけだ。
切ないから「たのしい」と言って笑っているのだと言うことを、忘れないで。
てふてふに獣の顔のありにけり 辻桃子
ーーーーーーーーー
目玉焼き目玉幾つや避暑終る 大川桃鬼
「避暑終わる」の季がロマンチックに流れがちなのを「目玉幾つ」ととぼけたので俳味が濃くなり寂しさがにじみ出た。甘い叙情に「寂しい滑稽」が加わったら「鬼に金棒」だと思う。
ーーーーーーーーー
.....こういう季語の使い方はどんな場合も説明的だ。「・・・だから」と簡単に理由、理屈のつくものは詩ではないと肝に銘じておこう。俳句とはわけのわからないナンセンスなものであるゆえに、人間存在のわけの解らなさに直感的に突き刺さるものなのだ。
写生と言うのがどういうものなのか少しわかった気がするし
(「写生に徹せよ」というのは、「徹底的な写生の果てに、このような幻想を至らせたい」がゆえである。)
とにかく削ぐ、説明しては行けない、でも意味不明な抽象もよくない、
というようなことが、非常によくわかります。
「短歌があるじゃないか」 穂村弘/東奈緒子/沢田康彦
穂村さんの本は何冊か持ってる。仲良くなれそうに思う。笑
現代短歌は読むのは好きだけど自分でしようとは思わないです。
ちょっとセンチに流れやすい地のままがでそうなのがいやなのかな。
もっと刈り込んだ端正な形が好きなのでしょう。
この本はアマチュアの方の短歌を3人で対談風にあれこれ語ったものです。
敷居の低い短歌入門書と書かれている。
本当に何十年たっても入門書を読んでいるわたしです(笑)。
斎藤茂吉などがそうであるように、近代短歌というのは一人称で、結婚したら結婚の歌、子どもができたら子ども、お母さんが死んだら悲しみの歌を、というふうに日記みたいな連続性を持っているわけですよね。(穂村)
ーーーーーーーーーーーー
例えば歌人の水原紫苑さんにとっては「能」とかの世界がこれなんですよね。必ず人が死んで、死者との交感になる。生きてるもの同士ではこの世界はもうだめだから、片方が死んでいなければ本当の愛の世界は成就しないみたいなたちばとかもありうると。(穂村)
魚食めば魚の墓なる人の身か手向くるごとくくちづけにけり 水原紫苑
こんなにもふたりで空を見上げてる 生きてることがおいのりになる 穂村弘
ーーーーーーーーーーーー
大切なことをひとりで成し遂げにゆくときのための名前があるの 穂村弘
というように名前をつけるのはひとつの呪術なんですよね。
ーーーーーーーーーーーー
熱帯夜。ゴキブリの中みは赤と黄いろと緑。 穂村弘
天国の5秒手前にいる君をおくりとどけるアインシュタインの舌 伴水
わたしたち家につかない気がするわフロント・ガラスにふる鱗たち 加藤治郎
荷車に春のたまねぎ弾みつつ アメリカを見たいって感じの目だね 加藤治郎
雪を見て飲むあついお茶 わたしたちなんにも持たずにここに来ちゃった
東直子