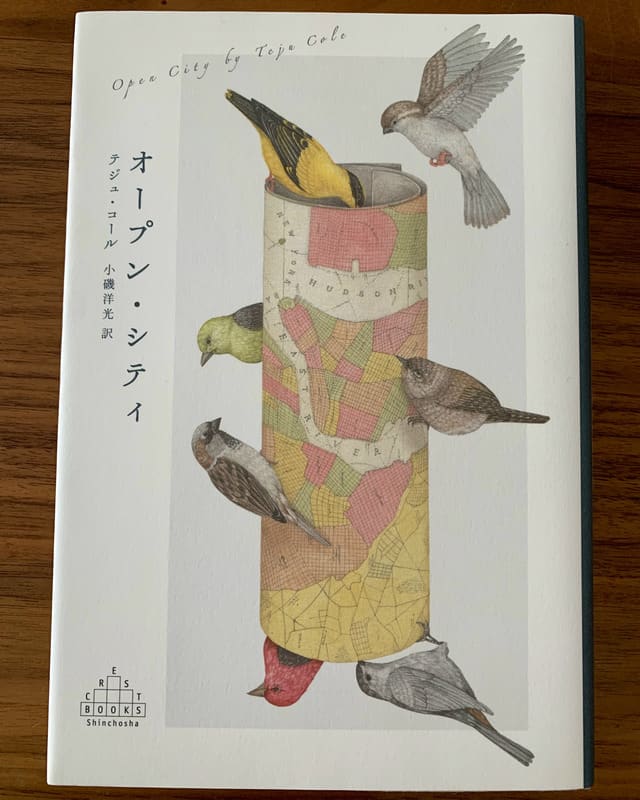読書会の映画「ジェーンオースティンの読書会」での読書会に憧れてから
mixiのコミュ(サークルみたいなコミュニティ)で古典文学を読む会をやったり、
日本最大となる読書会の京都でのイベントに参加したり、(これは数人ずつのテーブルに分かれ
作家がゲストで来たり、各テーブルにファシリテーターがいる大掛かりなイベント読書会)
やはり京都ベースで安定して20人以上集まることもある真面目な読書会にも時々参加したり、
そしてハンナ・アーレント「人間の条件」を3人で読む会に誘われて半年かけて読んだり
いろんな読書会に参加してきました。
それぞれやり方も人数も読む本もほんとうにいろいろですが
そのあと「苦海浄土」読書会を1年近くかけてうちで3人でやって、
3人いれば立派に読書会になるなぁと思うようになりました。
また、最近よく聴いているポッドキャストは学生時代にリアルに読書会をしていた2人が
中年になってまた今度はリモートで本についておしゃべりする読書会を配信しているもので、
3人どころか2人でも読書会になるやん!と、認識を新たにした。
知らない同士10人20人の会と、よく知ってる相手と2人の会では
全然違うタイプの読書会になるけど、どんな読書会でも本読んで話すのは楽しい。
人が2人いればいろんなことができるものだな。
最近、2年かかった2度目のハンナ・アーレント「人間の条件」zoom読書会が終わり
新訳のでた源氏物語8巻で8回の読書会にも参加してて、
長編小説も読書会なら読めるし、達成感や充実感が生活のアクセントになることも実感した。
それで今度は、大好きな高野文子の「黄色い本」というコミックで気になっていた
「チボー家の人々」を読むことにしたのだけど、舞台は120年前、
書きはじめられたのも100年くらい前という古い本だし、
翻訳も70年前くらいに終わったという古さで、しかも今時はやらないタイプの小説…
一緒に読んでくれる人を探せなくて、結局いつも映画の話をしている友達2人に
頼み込んで読んでもらうことに。
読書会楽しいのになぁ・・・
(まあ13巻あると聞くと怖気付くのが普通か・・・)
そういえばもう10年近く毎月続いている映画の会も、
映画館で各自見てきた課題映画について月に一度集まって話す会で、読書会の映画版と言える。
すごく楽しく続けていますが、この会は最初からずっと会を録音してPodcastにしてたので
今回の読書会も録音してみることにしました。
気楽に脱線しながらのおしゃべりで長くなると聞きにくいので
最初に各自の近況と、最近読んだ本などの話題、そして課題分のざっくり感想など
3人で最初の20分くらいだけ、最初に録ることにしてみます。
第一回を先日行いましたが、
会の最中にノーベル文学賞をハン・ガンが受賞したことがわかり盛り上がりました。
3人とも大好きな作家だったのでとても喜ばしくて盛り上がりました。
「チボー家の人々」もノーベル文学賞を取っているので、いっそううれしい。
10月から始めたので終わるのは来年の11月かな。
「苦海浄土」読書会の時のようにうちにきてもらってもいいんだけど
ちゃんと座ってメモ取ったりする必要もなく気楽におしゃべりできそうなので、
各回順番で誰か推薦のお店でご飯を食べながらということにしました。
読書もご飯も、毎月楽しもう。
最後に最近読んだ「読書会の教室」という本から少し引用します。
2人いればいろんなことができるなぁと思ったものの、
この本を読んでると少人数のコミュニケーションで気をつけることもあるというのはわかる。
わたしたちは少人数でもクローズなつもりはなく、どなたでも歓迎したいと思ってるけど
読書会に限らずどんなコミュニティでも言えることだなと思ったので以下に引用。
ただ、こういう配慮の背景に置かれがちな、素朴なクローズドネス批判には疑いを持ちます。コミュニケーションはオープンであるべきで、誰でも参加できることこそが大事だという価値観は根強いでしょう。他方で、クローズドなこと自体が悪いわけでもないんですよ。権威主義に陥ってカルト化するのがダメなだけで。内輪であるというのは、私たちは時間と場所を共有してきたし、その歴史があるということです。そういう歴史があるコミュニティでは、安心して言いっぱなし、聞きっぱなしができる。気をつけるべきは。不寛容や無配慮であって、読書会が内輪的になること自体は避けられないし、避けるべきことでもないんじゃないかと思います。
mixiのコミュ(サークルみたいなコミュニティ)で古典文学を読む会をやったり、
日本最大となる読書会の京都でのイベントに参加したり、(これは数人ずつのテーブルに分かれ
作家がゲストで来たり、各テーブルにファシリテーターがいる大掛かりなイベント読書会)
やはり京都ベースで安定して20人以上集まることもある真面目な読書会にも時々参加したり、
そしてハンナ・アーレント「人間の条件」を3人で読む会に誘われて半年かけて読んだり
いろんな読書会に参加してきました。
それぞれやり方も人数も読む本もほんとうにいろいろですが
そのあと「苦海浄土」読書会を1年近くかけてうちで3人でやって、
3人いれば立派に読書会になるなぁと思うようになりました。
また、最近よく聴いているポッドキャストは学生時代にリアルに読書会をしていた2人が
中年になってまた今度はリモートで本についておしゃべりする読書会を配信しているもので、
3人どころか2人でも読書会になるやん!と、認識を新たにした。
知らない同士10人20人の会と、よく知ってる相手と2人の会では
全然違うタイプの読書会になるけど、どんな読書会でも本読んで話すのは楽しい。
人が2人いればいろんなことができるものだな。
最近、2年かかった2度目のハンナ・アーレント「人間の条件」zoom読書会が終わり
新訳のでた源氏物語8巻で8回の読書会にも参加してて、
長編小説も読書会なら読めるし、達成感や充実感が生活のアクセントになることも実感した。
それで今度は、大好きな高野文子の「黄色い本」というコミックで気になっていた
「チボー家の人々」を読むことにしたのだけど、舞台は120年前、
書きはじめられたのも100年くらい前という古い本だし、
翻訳も70年前くらいに終わったという古さで、しかも今時はやらないタイプの小説…
一緒に読んでくれる人を探せなくて、結局いつも映画の話をしている友達2人に
頼み込んで読んでもらうことに。
読書会楽しいのになぁ・・・
(まあ13巻あると聞くと怖気付くのが普通か・・・)
そういえばもう10年近く毎月続いている映画の会も、
映画館で各自見てきた課題映画について月に一度集まって話す会で、読書会の映画版と言える。
すごく楽しく続けていますが、この会は最初からずっと会を録音してPodcastにしてたので
今回の読書会も録音してみることにしました。
気楽に脱線しながらのおしゃべりで長くなると聞きにくいので
最初に各自の近況と、最近読んだ本などの話題、そして課題分のざっくり感想など
3人で最初の20分くらいだけ、最初に録ることにしてみます。
第一回を先日行いましたが、
会の最中にノーベル文学賞をハン・ガンが受賞したことがわかり盛り上がりました。
3人とも大好きな作家だったのでとても喜ばしくて盛り上がりました。
「チボー家の人々」もノーベル文学賞を取っているので、いっそううれしい。
10月から始めたので終わるのは来年の11月かな。
「苦海浄土」読書会の時のようにうちにきてもらってもいいんだけど
ちゃんと座ってメモ取ったりする必要もなく気楽におしゃべりできそうなので、
各回順番で誰か推薦のお店でご飯を食べながらということにしました。
読書もご飯も、毎月楽しもう。
最後に最近読んだ「読書会の教室」という本から少し引用します。
2人いればいろんなことができるなぁと思ったものの、
この本を読んでると少人数のコミュニケーションで気をつけることもあるというのはわかる。
わたしたちは少人数でもクローズなつもりはなく、どなたでも歓迎したいと思ってるけど
読書会に限らずどんなコミュニティでも言えることだなと思ったので以下に引用。
ただ、こういう配慮の背景に置かれがちな、素朴なクローズドネス批判には疑いを持ちます。コミュニケーションはオープンであるべきで、誰でも参加できることこそが大事だという価値観は根強いでしょう。他方で、クローズドなこと自体が悪いわけでもないんですよ。権威主義に陥ってカルト化するのがダメなだけで。内輪であるというのは、私たちは時間と場所を共有してきたし、その歴史があるということです。そういう歴史があるコミュニティでは、安心して言いっぱなし、聞きっぱなしができる。気をつけるべきは。不寛容や無配慮であって、読書会が内輪的になること自体は避けられないし、避けるべきことでもないんじゃないかと思います。