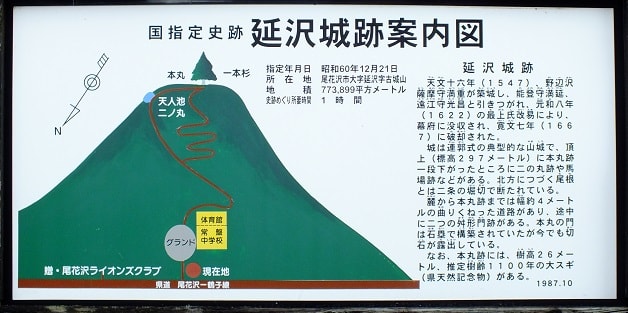1月14日、尾花沢市大字鶴子の花笠高原荘で常盤地区の「新春を語る会」という役員等が集まる祝賀会で「畑沢の宣伝」をしてきました。地区の各区長の外に、市の特別職の方々、教育関係者がおられました。初めてお会いする人が多いはずなのですが、以前からお会いしたことがあるような錯覚を覚えました。同じ故郷であることが、そうさせるのでしょう。初めから親しみを持てました。いい時間を頂戴しました。
祝賀会の中で、尺八とビオラの演奏がありました。尺八が甲高く「ヒョーン」と響くと、侘びと寂(さび)の世界へ入ります。ビオラの心地よいリズムと音色が、夢の世界へ誘います。音楽音痴の私でさえ感激しました。できれば、常盤地区の総ての方に聞いていただきたいと思いました。まして、小学生、中学生、高校生が、常盤地区で聞くことができれば、故郷に対する印象ががらっと変わり素晴らしいものになるはずです。故郷への思いを育むには、いい思い出を作ってあげることが必要です。私の子ども時代は、故郷の苦しい所だけを見せられていました。そのために、故郷の良さに気付くまでに非常に長い時間を要してしまいました。
祝賀会が終わって、いざ帰ろうとしたときに、何処に帰るべきか迷いが生じました。1月11日ごろから寒波が襲来していて、連日、尾花沢市内は大雪が降っていました。その中でも14日はホワイトアウト状態になるほどの大雪でした。花笠高原荘から山形へ帰るのは、極めて危険な状態です。迷った挙句、畑沢の小屋に泊まることにしました。事前に天気予報を見て、山形へ帰れないことも予想してそれなりの準備をしていました。冬山用のダウンジャケット、寝袋、炊事道具、米などです。若い時は、しばしば登山していたのですが、最近は1年間に1回も登らないときの方が多くなりました。山の道具は、この様な時しか役に立ちません。山小屋気分で泊まることにしました。
小屋には薪ストーブがあります。寒さはしのげます。燃料は、私のリフォーム作業で生じた木の廃材が沢山あります。

静まり返った小屋は眠気を誘い、9時過ぎには眠くなり寝袋に潜り込みました。雪道の運転で疲れ果て、直ぐに寝入ってしまいました。
翌日、3時半ごろ、まだ真っ暗な中に除雪車の音が聞こえて目を覚ましました。路上駐車していましたので、除雪作業の邪魔をしては申し訳ないと思って、窓から道路を見ましたが除雪した形跡はありません。不思議に思っていると、30分以上も経った頃に再び除雪車の音がしました。急いで窓から道路を覗いたところ、小型の除雪車が除雪しないでそのまま通行していきました。除雪車の横には「尾花沢市」と書かれていました。道路を除雪しなかった理由が分かりました。私の実家の前の道路は、県道です。除雪車は県道の除雪に来たのではなかったのです。別の目的で畑沢へ来ていました。
下ってきた除雪車が、進行を止めて何やら作業を始めました。見ると、県道から奥まった所にある住宅の入り口へ向かって除雪しています。これで、除雪車の謎が総て分かりました。尾花沢市は、道路から離れた所に建っているお宅のために、小型の除雪車で除雪しているのです。今、高齢化が進み、さらに高齢者だけの世帯が増えて、冬の除雪は困難を極めています。困難だけならまだいいのかもしれません。完全に除雪できない状態のお宅が数多くなりました。このように、市の事業として除雪していただいて大いに助かっているはずです。東京オリンピックの会場作りでは、アスリートファーストだから何千億円とか何百億円などとおっしゃっていますが、畑沢に来たこの除雪車の事業費と比較すると、同じ日本なのかと思いたくなります。お金は、この様に使ってもらいたいものです。

5時台になると、今度は県道を除雪しながら除雪車が南へ向かって登っていきました。除雪車の脇には「山形県」と書かれています。登る時に片側を除雪し、下る時に反対側を除雪しました。ところが、30分ほど経過した時に再び山形県の除雪車が除雪のために登ってきました。「さっき除雪したばかりなのに」と不審な気持ちになりながらも、路上駐車した自動車を移動するために外へ出て驚きました。ものの30分の間に、さらにどっさり積もっていました。除雪が必要な状態になっていたのです。そして、雪はまだ激しく降り続いていました。不審な気持ちを抱いた自分が情けなくなり、逆に作業されている方々の御苦労ぶりに頭が下がりました。
そんなことで、いつもの生活ならまだまだ寝ている時間帯ですが、目が覚めてしまい、ついでにお腹が空いてきました。登山気分を味わう炊事をすることにしました。ガスのコンロ(登山用語では「ストーブ」と言います。)に一人用のコッヘル(アルミ製の鍋)を載せて、上段でお湯、下段で御飯を作りました。おかずはレトルトカレーです。それなりに美味しい朝食でした。スープはないので、ぬるま湯をごくり。

朝食を食べ終わると、また眠くなり、寝袋に潜ると直ぐに寝入り、目が覚めた時は8時近くになっていました。外は明るく山の上には青空が広がっていました。山里は、山々から太陽が顔を出すまで時間がかかります。それでも、太陽が昇る山と反対側の山の端がキラキラと太陽光を浴びていました。天気予報を裏切って、私のために「晴れて」くださったようです。早速、小屋の屋根に梯子を架けて、雪降ろしです。小屋は二階建てですから、高所恐怖症の私には怖い場所です。しかし、「俺がやらねば」と意気込んで登りました。雪は柔らかいので、作業は順調です。やがて、一人で雪降ろししていることを心配して、尾花沢から義兄が駆けつけてくれました。瞬く間に終わりかなと思っていたところ、最後の雪の層が、とても固くなりました。力を入れないとスコップが刺さりません。もう、汗だくになりながら11時ごろに完了です。義兄が準備して下さった鍋焼きうどんを腹いっぱい御馳走になりました。
畑沢から山形へ出発したのですが、道路は危険極まりない状態が続いていました。路面は固い雪で覆われ、両側には除雪作業で除けられた雪が道幅を極端に狭くしています。おまけにホワイトアウト状態ですから、運転は真剣そのもの。林崎を走行中に雪の塊に前の方を突っ込んだ自動車が一車線を塞ぐように横向きに停車していました。事故かなと思いましたが、そうではなくて単なるスリップ状態に陥っただけのようです。ところが、高齢の御婦人がスコップも持たずに足で雪を掻いています。これでは何ともならないと思い、お手伝いをすることにしました。スコップで前輪の周りの雪を掻き、籾殻を撒いてスリップ止めにし、運転を替わって雪から脱出することができました。後で御夫婦に聞いたところ四駆だったそうです。やはり四駆はいいようです。
これまで、私の自動車が苦境にあった時に、何度も助けてもらいました。今回、少しだけ恩返しできました。でも、まだまだ借りが残っています。いつになると返せるでしょうか。