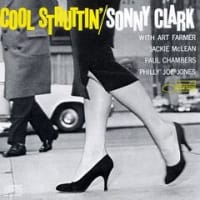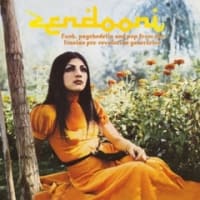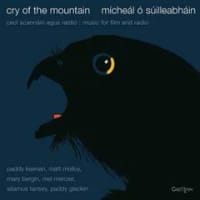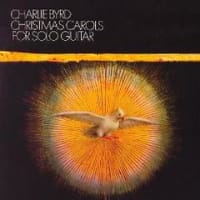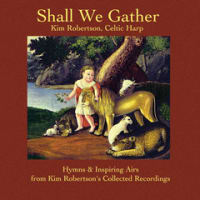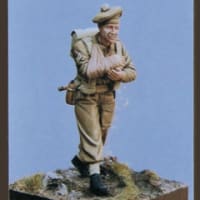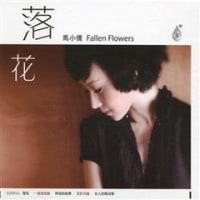ウエブ上でいろいろお付き合いいただいている”ちあきなおに”さんから、先日、あのマレンコフ氏が亡くなった事を教えていただいた。ウ~ム・・・と感慨に浸るほどのかかわりもなかった人だが。というかそもそもこれで、逢ったことさえないまま終わってしまったことになる人だが。享年84歳。まあ、大往生といえようか。
マレンコフ氏は東京は新宿の裏町の飲み屋街に生きたギター流しの最後の生き残りの一人だった。あるいは夜の裏通りのヌシ、伝説の人。
ネットで調べてみると、流しを始めたのは昭和24年のことだそうな。一度はカタギの仕事に付きながら、音楽への情熱病みがたく流しの生活に身を投じた。いずれは歌手としてデビューなど夢見ていたのだろうか。
ギターを抱えて飲み屋を渡り歩き、「どうです、一曲?」と酔客の歌の伴奏をする。三曲でいくら、なんて形のチップを受け取る。
客が歌おうとする曲が分厚い歌本の何ページにあるかすべて記憶していたとか、リクエストされて弾けない曲はなかったとか、さまざまな伝説。紅灯の巷をギター一本で半世紀以上も生き抜いて来たのだから、それはさまざまな逸話も生まれたろう。
先に書いたとおり、私は飲み屋街でマレンコフ氏に遭遇したことはないし、だから彼のギターで歌う機会もなかった。どのようなタッチのギターだったのか、一度生で聴いてみたかったが。残念ながら、私は新宿のゴールデン街などを取材したドキュメンタリー番組の片隅で何度か彼の姿を見た記憶があるだけだ。
あっと。これこそもっと早く書くべきだったが、マレンコフとはもちろん呼び名で、氏はコテコテの日本人である。若き日、当時のソ連の首相マレンコフに相貌が似ているからと付けられたあだ名であり、そいつがそのまま通称となった。活躍した場所が場所、時代が時代だけに、思想的背景とかあるのかと思えばそうではない、その肩すかしの感じがなんとなしに楽しい。
マレンコフ氏の生涯を捉えたドキュメンタリー映画が製作途上と聞いたが、さて、どのようなものか。彼の身の内にあった喜怒哀楽というのは、どんなものだったのだろう。
マレンコフ氏とは出会えなかった私だが、なにしろ盛り場生まれの盛り場育ち、彼ら流しの生態というものには、それなりに親しんではいる。彼らはこの世を支配する効率的銭もうけのシステムの狭間に生まれた余白みたいな盛り場の夢のあわいに幻のように現われ、酒臭い空気の中を泳ぐように生きていた。
妙に上気した気配の漂う盛り場の夜のトバクチ。灯り始めのネオンサインの下、申し訳なさそうでいてふてぶてしくもある、みたいな不思議な間合いの後ろ姿を見せながら店の暖簾を掻き分ける彼らの姿は、子供の頃の記憶の中にも映画の一場面のようにある。
そういえば私は一度、ドサクサまぎれに流しとしてギャラを受け取ったことがある。夜の酒場で知り合いの流しとギター談義をしていたら、彼らの仲間と勘違いされ、ご指名がかかってしまったのだ。
相手はヤ○ザの幹部で、「違います」とか言って機嫌をそこねるのもヤバかったので、ちょうど知っている曲でもあったので、その場のノリで一曲、伴奏をあい勤めてしまった。何、こっちだってもともとはバンドマンだ。
で、その分のチップをポケットに押し込まれたのだが、流しの兄さんの「いいから貰っておきなさいよ」という真剣過ぎる口ぶりが可笑しくて、いまだはっきりと覚えている。
そんな彼らの姿も、カラオケの普及により、まるでカウンターにこぼれた水をお絞りで拭き取ったように一瞬で消え去ってしまった。