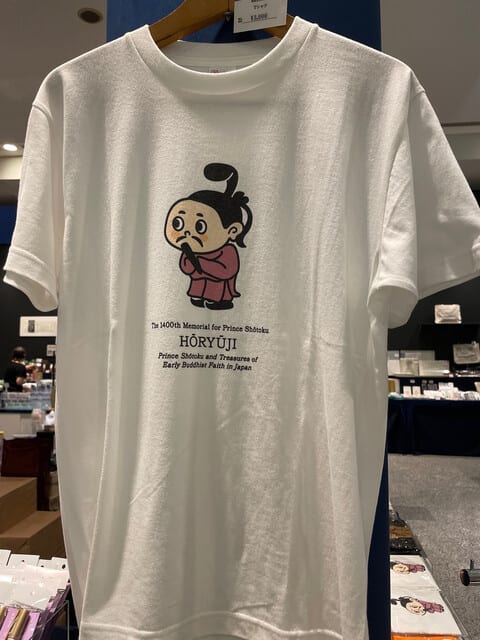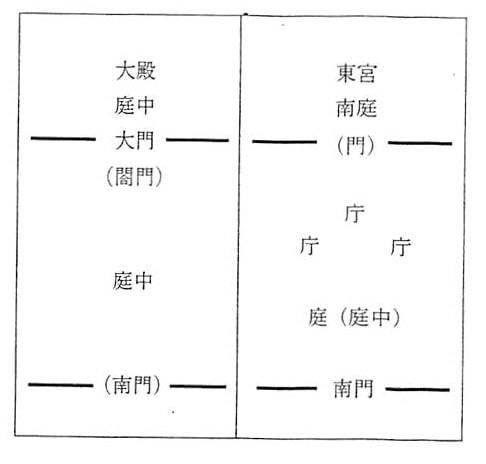これに対して、太子の伊予来訪を否定する点は同じでも、学術的に検討していて有益な本がありますので、かなり前の出版になりますが、紹介しておきましょう。
松原弘宣『熟田津と古代伊予国』「第三章 神話・伝承にみえる伊予国 第一節 聖徳太子の伊予遊行伝承について、第三節 聖徳太子の伊予来訪伝承の背景について」
(創風社出版、1992年)
です。愛媛大学で瀬戸内を中心とした水上交通史などを専門とする松原氏は、古代における伊予国に関する様々な記述を検討した後、聖徳太子来訪伝承を取り上げます。
まず、碑文については、後漢時代の張衡の「温泉賦」や北周の王褒の「温泉碑」の文言に基づいていることから、そうした文章がまとめられている文献、つまり、「類書」と呼ばれる用例百科事典を利用していると見ます。そして、その類書として、東アジア諸国で広く用いられた『芸文類聚』を想定するのです。
『芸文類聚』100巻は、初唐の武徳7年(推古32年、624年)の完成であって太子の没後であり、日本にもたらされたのはそれより後ですので、太子の時代にこうした碑文が書かれるはずはないとします。
また、舒明天皇の伊予来訪は『日本書紀』に記されるものの、聖徳太子の来訪は『日本書紀』にも『上宮聖徳法王帝説』にも見えないことを重視します。さらに、碑文に記される「法興」という年号については、法隆寺金堂の釈迦三尊像銘に記されるのと同じだが、年号が用いられるのは後代のことであり、この時、23歳である太子が「法王大王」と呼ばれるのは不自然とします。
そして、このような伝承が生まれた背景として、奈良中期の『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』によれば法隆寺が讃岐・伊予に荘園や倉を多数持っていたこと、またこの地の寺の遺跡から法隆寺式の瓦が出ていることを指摘し、豪族を含めたこの地と法隆寺の結びつきが強まっていく中で、太子の来訪伝説が形成されたと見るのです。
文献に基づく穏当な見解ですが、問題もいくつかあります。一つは、『芸文類聚』の利用を当然のこととしている点です。美文の詩文を作る場合、百科事典的な類書に収録された詩文を参考にするのは良くあることですが、そうした類書は『芸文類聚』に限りません。
『芸文類聚』以前に、南朝の梁では『華林遍略』、北朝の北斉では『華林遍略』を修訂した『修文殿御覧』などが編纂されています。この20年ほどでそうした類書の研究が日本・中国で大いに進み、『日本書紀』が利用していた類書についても、池田昌広さんなどが解明しています。
南北朝期から隋唐にかけては、国家が編纂したこうした大部の類書(『華林遍略』は720巻)とは別に、これらを略抄した簡略版の類書も流行しており、これは仏教類書においても同様であって、一般の類書も仏教類書も、そうした様ざまな類書の断片が敦煌写本から発見されています。
ですから、厩戸皇子関連の記事を含め、『日本書紀』その他が類書を利用しているのは事実ですが、だからといって湯岡碑文が『芸文類聚』に依っていると断定することはできないのです。
聖徳太子の場合、『日本書紀』で太子関連記事を書いた編者、ないしその素材となった文献の作者も、類書の「聖」の項目を利用した可能性がありますが、「憲法十七条」自体、その可能性があることは、かつて論文で触れました。
次に、舒明天皇と違って『日本書紀』に厩戸皇子の伊予来訪が記されていない点ですが、すべての事柄が『日本書紀』に記されているわけではありませんし、舒明天皇の行動は厩戸皇子の事績を受け継ぐ形でおこなわれている場合が多いことは、このブログで取り上げた鈴木明子氏の論文が指摘しています(こちら)。
また、法興年号を含む釈迦三尊像銘については、釈迦三尊像と一体のものとして作成されたことは、東野治之氏が論証しており、美術史学者も像や光背を推古朝のものとみなすのが通説になっています。
「法王」という呼称は不自然だとする点については、以前、このブログで湯岡碑文をとりあげ、これは『維摩経』の「法王」に基づくものであり、椿の大木がアーチを作っている光景にふさわしい用法であることを説明しておきました(こちらとこちら)。
という状況ですので、松原氏のこの本は、愛媛大学教授ならではのこの地の歴史や交通史に関する記述は有益であるものの、聖徳太子の伊予来訪説否定については、最新の研究成果からすると確実な論拠を示せていない、ということになります。
【付記:2021年8月13日】
冒頭で、九州王朝説派のトンデモ本を「珍説奇説」コーナーで紹介したと書いたのですが、そのトンデモ本を批判した白方勝氏の論文を「論文・研究書」コーナーで紹介していましたので、訂正します。