前回の浜田氏の論文は、佐藤長門氏の合議制に関する論文を引用していました。この論文は、佐藤氏の『日本古代王権の構造と展開』(吉川弘文館、2009年)に収録されている「倭王権における合議制の史的展開」です。
ただ、佐藤氏はこの主張に基づき、更に詳しく論じた論文を最近発表されているため、そちらを紹介しておきます。
佐藤長門「六世紀の王権ー専制王権の確立と合議制ー」
(仁藤敦史編『古代王権の史実と虚構』、竹林舎、2019年)
です。
佐藤氏は、稲荷山古墳出土の鉄剣銘の発見により、それまで氏族連合体制であった畿内が、雄略によって軍事的専制王権に転じたとされ、この時期が古代史の画期とみなされるようになったことから話を始めます。そして、倭の五王については続柄が明らかでない例があるのに対して、6世紀になると大王位がひとつの王統で独占され、世襲王権が成立したことに注意します。
継体天皇については、妃たちの出身から見て、越前・近江・尾張・美濃などの首長と広範囲な交流を持っていて有力な存在だったが、雄略の娘と仁賢天皇の間に生まれた手白香皇女をめとって王位継承の正統性を保証しており、安閑天皇と宣化天皇も仁賢天皇の皇女をめとっていることは、継体の王統が新たな大王家として正統性の保持に腐心していた証拠とします。
この時期の王権については諸説がありますが、佐藤氏は、全国的な内乱は生じていないものの、大王位をめぐって王権内部で深刻な対立が生じていたことは認められるとします。
そして、欽明天皇以後は、意図的に王統を欽明の子孫に限定し、その継承資格者は大王宮から独立した宮(皇子宮)を経営して経験をつんだ大兄がなり、大王の没後は、年齢や人間的資質が重視されて、同一世代の大が年齢淳に即位し、それが尽きると次の世代に移行する形になったことを再確認します。
敏達天皇が亡くなると、その皇子たちでなく、敏達と同世代であった大兄の用明天皇が即位し、敏達の妹である間人を后としているのは、まさにその方式によります。
佐藤氏は、大王のもとで個人や集団が特定の職務をになうようになったが、体系的な統治システムではなかったため、管轄権を分与された有力階層を統合する中枢機構が必要になったとします。
さらに、王権が世襲化されると、大王のもとに一体であるべき群臣たちが、sれぞれ意中の後継候補の王族をいただくことにより、王権分裂の危機も生じたため、不断の意志確認の場が設定されたのであって、それが合議制だったと推測します。
仏教公伝については、実際には受動的な伝来ではなく、『隋書』倭国伝が「仏法を敬い、百済に求めて仏経を得」たと記すように、自発的な導入であったとしたうえで、ともかく重要な事案なので合議が行われたのだと論じます。これは重要ですね。
このように、重要な役割を果たした合議制ですが、貴族共和制ではないとします。大王の視点からは、意志決定に有力階層を関与させて遂行を保証させ、大王の意志を全体の意思とさせる機関であり、また群臣側からすれば、共同利害を体現する大王を核として結集することにより、自らの地位を保証してもらう機関が合議制であったとするのです。
その群臣の範囲については、
1.史料に大臣・大連・大夫と明記されていること
2.それ以外でも、群臣とわかる記載がされていること
3.その活動が一代限りでなく、数代にわたっていること
という3条件を満たした氏族を恒常的な群臣とみなすとし、蘇我氏、大伴氏、物部氏、阿倍氏、中臣氏、巨勢氏、平群氏、紀氏をあげています。
これ以外には、敏達天皇における三輪氏など、大王との個人的関係のあった氏族、渡来系氏族・僧侶、有力な氏族の傍系氏族なども、大王の召集や議題の種類によっては合議に参加することがあったとします。大兄たちもそれぞれの宮系を代表して参画していたと推測するのですが、これは異論もありそうです。
律令制導入以後の8世紀前半にあっても、1年ごとの議政官は10名を越えていないことからすれば、行政組織が未発達で政務が細分化されていない倭国にあっては、群臣の合議はこの程度の人数を越えなかったと推測します。
結論としては、群臣のメンバーが容易に変動している点から見て、合議制を氏族勢力の牙城とみなすことはできないというのが、佐藤氏の結論です。
そして、大王後継候補である大兄が経験を積む場であった皇子宮は、その同母集団の家政機関であり、農業経営・地域開発の拠点であるとともに、「王権から依託された仕奉集団を管轄する執務遂行センター」であったと見るのが妥当とします。
これは群臣宅の場合も同様であって、こうした皇子宮・群臣宅が大王宮と有機的に結びついて王権中枢を形成していたのが当時の状況であったと見るのです。
いずれにしても、律令体制すら当初は完全には実施できなかったのですから、まして6世紀から7世紀半ば頃までの状況については、律令制の前段階とか律令制とは反対の状況などとして簡単に割り切るのは実状に合わないということですね。
ただ、佐藤氏はこの主張に基づき、更に詳しく論じた論文を最近発表されているため、そちらを紹介しておきます。
佐藤長門「六世紀の王権ー専制王権の確立と合議制ー」
(仁藤敦史編『古代王権の史実と虚構』、竹林舎、2019年)
です。
佐藤氏は、稲荷山古墳出土の鉄剣銘の発見により、それまで氏族連合体制であった畿内が、雄略によって軍事的専制王権に転じたとされ、この時期が古代史の画期とみなされるようになったことから話を始めます。そして、倭の五王については続柄が明らかでない例があるのに対して、6世紀になると大王位がひとつの王統で独占され、世襲王権が成立したことに注意します。
継体天皇については、妃たちの出身から見て、越前・近江・尾張・美濃などの首長と広範囲な交流を持っていて有力な存在だったが、雄略の娘と仁賢天皇の間に生まれた手白香皇女をめとって王位継承の正統性を保証しており、安閑天皇と宣化天皇も仁賢天皇の皇女をめとっていることは、継体の王統が新たな大王家として正統性の保持に腐心していた証拠とします。
この時期の王権については諸説がありますが、佐藤氏は、全国的な内乱は生じていないものの、大王位をめぐって王権内部で深刻な対立が生じていたことは認められるとします。
そして、欽明天皇以後は、意図的に王統を欽明の子孫に限定し、その継承資格者は大王宮から独立した宮(皇子宮)を経営して経験をつんだ大兄がなり、大王の没後は、年齢や人間的資質が重視されて、同一世代の大が年齢淳に即位し、それが尽きると次の世代に移行する形になったことを再確認します。
敏達天皇が亡くなると、その皇子たちでなく、敏達と同世代であった大兄の用明天皇が即位し、敏達の妹である間人を后としているのは、まさにその方式によります。
佐藤氏は、大王のもとで個人や集団が特定の職務をになうようになったが、体系的な統治システムではなかったため、管轄権を分与された有力階層を統合する中枢機構が必要になったとします。
さらに、王権が世襲化されると、大王のもとに一体であるべき群臣たちが、sれぞれ意中の後継候補の王族をいただくことにより、王権分裂の危機も生じたため、不断の意志確認の場が設定されたのであって、それが合議制だったと推測します。
仏教公伝については、実際には受動的な伝来ではなく、『隋書』倭国伝が「仏法を敬い、百済に求めて仏経を得」たと記すように、自発的な導入であったとしたうえで、ともかく重要な事案なので合議が行われたのだと論じます。これは重要ですね。
このように、重要な役割を果たした合議制ですが、貴族共和制ではないとします。大王の視点からは、意志決定に有力階層を関与させて遂行を保証させ、大王の意志を全体の意思とさせる機関であり、また群臣側からすれば、共同利害を体現する大王を核として結集することにより、自らの地位を保証してもらう機関が合議制であったとするのです。
その群臣の範囲については、
1.史料に大臣・大連・大夫と明記されていること
2.それ以外でも、群臣とわかる記載がされていること
3.その活動が一代限りでなく、数代にわたっていること
という3条件を満たした氏族を恒常的な群臣とみなすとし、蘇我氏、大伴氏、物部氏、阿倍氏、中臣氏、巨勢氏、平群氏、紀氏をあげています。
これ以外には、敏達天皇における三輪氏など、大王との個人的関係のあった氏族、渡来系氏族・僧侶、有力な氏族の傍系氏族なども、大王の召集や議題の種類によっては合議に参加することがあったとします。大兄たちもそれぞれの宮系を代表して参画していたと推測するのですが、これは異論もありそうです。
律令制導入以後の8世紀前半にあっても、1年ごとの議政官は10名を越えていないことからすれば、行政組織が未発達で政務が細分化されていない倭国にあっては、群臣の合議はこの程度の人数を越えなかったと推測します。
結論としては、群臣のメンバーが容易に変動している点から見て、合議制を氏族勢力の牙城とみなすことはできないというのが、佐藤氏の結論です。
そして、大王後継候補である大兄が経験を積む場であった皇子宮は、その同母集団の家政機関であり、農業経営・地域開発の拠点であるとともに、「王権から依託された仕奉集団を管轄する執務遂行センター」であったと見るのが妥当とします。
これは群臣宅の場合も同様であって、こうした皇子宮・群臣宅が大王宮と有機的に結びついて王権中枢を形成していたのが当時の状況であったと見るのです。
いずれにしても、律令体制すら当初は完全には実施できなかったのですから、まして6世紀から7世紀半ば頃までの状況については、律令制の前段階とか律令制とは反対の状況などとして簡単に割り切るのは実状に合わないということですね。










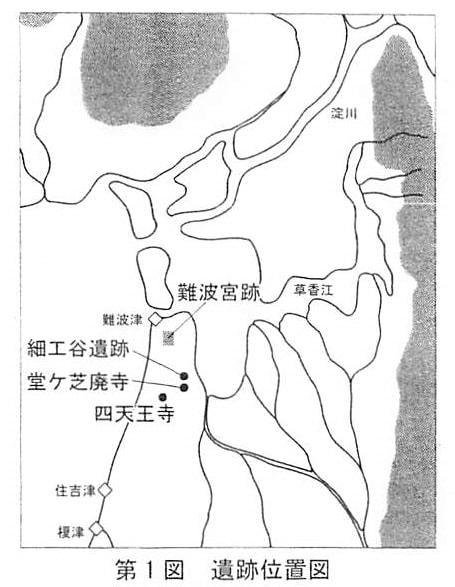
 (為)や
(為)や  (所)のように、右にくるっと旋回する軽快で曲線的な書風で知られますが、それどころではなく、1980年代に流行した変体少女文字を思わせる丸文字となっておりました。
(所)のように、右にくるっと旋回する軽快で曲線的な書風で知られますが、それどころではなく、1980年代に流行した変体少女文字を思わせる丸文字となっておりました。




