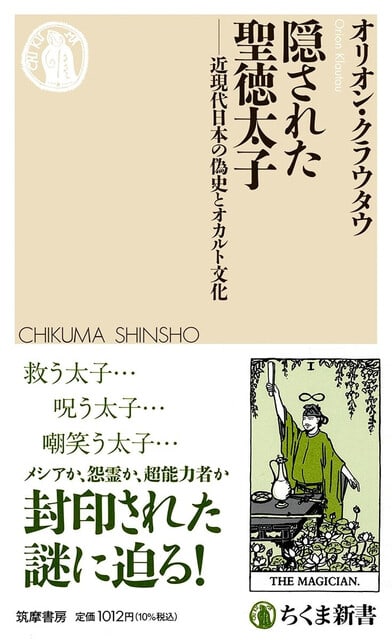このブログでは、聖徳太子に関する諸分野の最新の研究成果を紹介するとともに、大山誠一の聖徳太子虚構説を詳細にわたって批判したうえ、法隆寺は聖徳太子の怨霊を鎮めるための寺と論じた梅原猛(こちら)、ノストラダムスの大予言シリーズで人気になって聖徳太子をその類の予言者とした五島勉(こちら)、日本をキリスト教国家にしようとした蘇我氏が邪魔な聖徳太子を暗殺したと妄想した田中英道の本(こちら)なども取り上げ、論評してきました。その類の「あぶない」聖徳太子論を取り上げて分析した面白い本が刊行されました。
オリオン・クラウタウ『隠された聖徳太子―近現代日本の偽史とオカルト文化』
(筑摩書店、ちくま新書1794、2024年5月)
です(クラウタウさん、有り難うございます)。
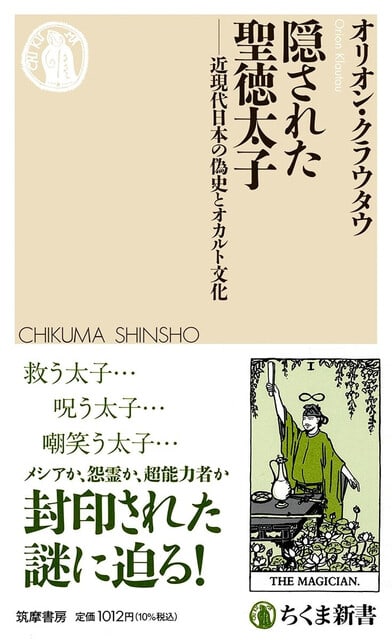
クラウタウさんのこうした研究については、以前、このブログで論文を紹介したことがあります(こちら)。今回の本はその拡張版ですね。その時も今回も、論文や研究書紹介のコーナーでなく、【珍説奇説】コーナーでとりあげていますが、これは、そうした話題に関心を持つ人の目につきやすいようにと思っての配置です。面白い話題満載なので楽しんで読めるものの、中身はきわめて学術的な研究書です。
現在は東北大学准教授であるクラウタウさんとは、彼がまだ龍谷大学アジア仏教文化センターの研究員をしていた頃から、近代仏教研究仲間として親しくしており、私は現在は彼が代表を務めている科研費研究「憲法作者としての聖徳太子」の共同研究者にもなっています。「あとがき」でも触れられているように、本書はこのブログについても数カ所で言及してくれています。
内容は以下の通り。
【目次】
まえがき
序 隠されたものへの視点―偽史から聖徳太子を考える
第一章 一神教に染まる聖徳太子
第一節 学術界における聖徳太子とキリスト教の「事始め」
第二節 秦氏はユダヤ教徒だった―佐伯好郎の業績によせて
第三節 フィクションへの展開―中里介山の聖徳太子観
第二章 乱立するマイ太子像
第一節 池田栄とキリスト教の日本伝来
第二節 聖徳太子と戦後日本のキリスト教
第三節 司馬遼太郎と景教
第三章 ユダヤ人論と怨霊説
第一節 手島郁郎と一神教的古神道
第二節 梅原猛と怨霊説の登場
第三節 怨霊meets景教―梅原猛『塔』について
第四章 オカルト太子の行方
第一節 漫画の中のオカルト太子―山岸凉子『日出処の天子』
第二節 予言者としての聖徳太子の再発見
結 隠された聖徳太子の開示
あとがき
以上です。
「まえがき」では、現在の聖徳太子研究の状況に簡単に触れた後、太子関係の本には、隠された「秘密」を明らかにしたと称する本が多く、「隠された『真実』」が分かれば、太子の意味も、また日本の歴史全体も明らかになるとしている、と述べます。そう主張する者たちは、自分は資料調査や分析を通じ、アカデミックな研究者にはない鋭い洞察力で秘密を解いたと称するのです。
そうした書物が1990年代の終わりから増えていくのは、古代史学者である大山誠一の聖徳太子虚構説と無縁ではなく、従来の聖徳太子観を大胆に否定した大山の主張は、陰謀説を掲げる多くの「トンデモ本」にインスピレーションを与えたとクラウタウさんは説きます。
なお、『隠された聖徳太子』という題名は、立命館大学の哲学の教授職を辞し、筆で喰わねばならなくなったため、恐るべき「秘密」を解明したと称する非学問的でセンセーショナルな聖徳太子論を書いてベストセラーとなり、以後のトンデモ本に影響を与えた梅原猛の『隠された十字架』を踏まえたものでしょう。東北大学の美術史の教授であって現在は名誉教授の田中英道も同類ですが、クラウタウさんは大学教員などの肩書きや地位が一般社会に与える力にも注意します。
クラウタウさんは、聖徳太子は古代以来、日本人の心を動かしたからこそ、様々な偉業をおこなったとされたのであり、太子に関わる「偽史」を含めた「異説」はそれぞれの時代の人々の願望を反映したものであるため、「異説」に秘められた意図を検討することによって、聖徳太子のもう一つの「歴史」を描きたいと述べます。
「偽史から聖徳太子を考える」というサブタイトルがついてる「序」では、クラウタウさんは「偽史」について最近の研究状況から説明します。中国においては、正統とされる王朝が作成した史書が「正史」であり、そうでない王朝や政権が作成した史書は「偽史」と呼ばれていました。
日本でも、明治以後になって「発見された」という形で出現した『上記(うえつふみ)』『竹内文書』『九鬼文献』などの偽書が、第二次大戦中の超国家主義的な状況の中で「偽史」として切りすてられました。ところが、それらの文献は一九七〇年代のオカルトブームの中で関心を集めるようになり、「古史古伝」とか「超古代史」と呼ばれて消費されるようになったのです。
今日言う「偽史」は、これらの偽書を含むだけでなく、そうした偽書を真実と見て語られる言説も含みます。さらに、東大出身でプラトンやバイロンなど西洋の哲学・文学の翻訳で評価されたものの、明治の終わり頃から『古事記』『日本書紀』の記述に基づいて世界の古代文明はすべて日本が起源だと主張した木村鷹太郎(1870-1931)のように、権威ある文献に基づきつつトンデモ説を述べる書物なども含むようになっているのです。
そうした偽史に関する最近の研究成果をまとめた小澤実の『近代日本の偽史言説』では、「チンギスハンは源義経だ」「イエス・キリストは日本で死んだ」「東北に古代王朝が存在していた」「フリーメイソンの陰謀で世界は支配されている」「ユダヤ人が世界転覆を狙っている」といった幅の広い言説が偽史の例としてあげられています。
クラウタウさんは、さらに、学界で評価されている(ないし、世間でそうみなされている)学者の研究が偽史を生む背景となる場合もあることに注意します。つまり、まともな学者が学界で承認されない珍説を唱えるようになることもあるうえ、学問的であるものの意外な主張をした研究が世間に刺激を与え、それを材料にしてトンデモ説が生まれることもあるのであって、学問と偽史の境目ははっきりしない場合があるとするのです。
クラウタウさんは、そうした例として、古田武彦をあげます。古田は、親鸞に関する詳細な文献研究などで評価されていたものの、1971年の『「邪馬台国」はなかった』(朝日新聞社)によって多くの反論を招きながらマスコミに注目されるようになりました。
後には、古代津軽王朝の存在を説く『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』を、自説に有利な真書とみなし、その研究成果を踏まえて昭和薬科大学の教員という立場で1990年に『真実の東北王朝』を刊行し、話題になりました。『東日流外三郡誌』については、戦後の古代史ブームやオカルトのブームの影響も受けて生まれた偽書であることが論証されているにもかかわらず、今でも真書だとして信奉する者たちが残って活動しています。
これは『先代旧事本紀大成経』の「五憲法」などの場合と同じですね。偽の古史は、従来の史書や通説に満足できず、歴史の真実は実はそうではなかったと思いたい人々の要望を充たすように作られますので、熱烈に支持する人たちが出るのは当然なのであって、そうした人たちには偽書の明らかな問題点が目に入らないか、目についても何かしらの理由をつけて弁護するのです。
クラウタウさんはまた、1972年に聖徳太子に関する新説である『隠された十字架』(新潮社)から刊行し、古代史学界からは妄説として批判されながら毎日出版文化賞や大佛次郎賞を得て、国際日本文化研究センターの初代所長にまでなった梅原猛をとりあげます。
クラウタウさんは、古田と梅原の両人は違う面もあるものの、共通点によって歴史と偽史の間のグレーゾーンが形成されていることに注意します。そして、学界の通説に対する対抗意識を持ちながら、学問の権威自体は否定せず、それを戦略的に利用して偽史を生みだしていった例として、大山の太子虚構説に注目します。東大史学科の出身であって古代史の専門家として承認されていた大山の説を利用し、虚構説からさらに飛躍した想像の世界を構築してゆく著作が次々に生まれたのです。
本文の第一章は、オカルト雑誌として知られる『ムー』の2014年の「聖徳太子と失われたイスラエル10支族の謎」という特集の話で始まります。その記事を書いた久保有政(1955-)は、プロテスタントの牧師であって、古代日本にイスラエル人がやってきたと主張していました。
久保は、大山誠一が従来の聖徳太子観は間違っていたことを明らかにしたことに力を得て、太子は実際は神道、それも八百万の神を崇拝する神道でなく、唯一の神を奉じるキリスト教的な神道を土台として活動したと論じた由。これなどは、自らの信仰に基づき、学界の新説を自分の宗教的信念に引きつけ、大真面目で強引な解釈をした典型的な例ですね。
太子とキリスト教の関係については、明治になって最初の近代的な古代史家、久米邦武(1839-1931)が、唐代の長安にはキリスト教のネストリウス派である景教が来ていたことに注意し、太子の厩戸誕生伝説は『新訳聖書』の焼き直しと見たことが有名です。
その背景には、東西の宗教に共通基盤を見いだそうとする久米の摸索があったことが指摘されており、そのことはこのブログでも紹介しました。クラウタウさんはさらに、この久米説に対して初期の仏教史家であった境野黄洋(1871-1933)が反論し、逆に仏教の説話がユダヤ人にまで伝わっていった例が多いと論じたことに注意します。
境野は、釈尊のジャータカ(前世譚)が西に行ってキリストの馬槽の話になり、東に伝わって太子の厩戸誕生の話になった可能性を指摘したのです。クラウタウさんは、境野は学問だけでなく仏教改革運動もしていたため、敵対するキリスト教の影響という説は受け入れられなかったものと推測します。
このように、クラウタウさんのこの本は、聖徳太子に関する様々な意外な説を紹介するだけでなく、そうした説が生まれた背景、世間に受け入れられた事情、反論がなされた背景などについて考察を試みるのです。
さて、キリスト教徒であって西洋古典学に通じ、景教の歴史の研究者として知られた佐伯好郎(1871-1965)は、日本の地名とユダヤの言葉との類似から見た証拠とされるものをあげ、1908年に帰化人であった秦氏はユダヤ人だったと論じました。
その頃、イギリスから来た仏教研究者であったゴルドン夫人は、真言宗の大日如来解釈はヘブライ系の神の概念に近く、これは空海が長安で景教に接して学んだためだとしていました。ゴルドン夫人は、高野山に西安(長安)で発見された「大唐景教流行碑」のレプリカまで建立した人物です。このように、宗教に関わる意外な説、神秘的な説は、東洋・西洋の相互影響の中で生まれ、増幅していくことも多いのです。
この調子で紹介していくと、5回くらいの連載になってしまうため、以後は簡単にまとめます。まず、第二章では、元京都帝国大学法学部教授でイギリス政治史の研究者だった池田栄(1901-1991)をとりあげます。
池田は、戦時中は「聖徳太子教導国家と大東亜建設」といった調子の論文を書いていました。1949年に、この年は日本最初のキリスト教宣布者であるザビエルの来日から400年になる年として各地でイベントが行われると、池田はこれに反発しました。
池田は、佐伯説に基づいて秦氏は景教信者だったのであってその大酒神社はダビデの礼拝堂だったと推測し、ザビエル以前にキリスト教が伝わっていたと大阪の新聞上で述べたのです。この主張は米国の各地の新聞で紹介されたそうです。欧米のキリスト教徒などは、こうした情報を喜ぶのですね。
日本聖公会の聖職者だった池田は、現在も生きる「景教」としてアッシリアの東方教会の総主教に書簡を送り、「景教復興」事業まで始めた由。しかも、この景教復興後援会には、秦氏の氏寺である広隆寺の住職も理事として加わったというのですから驚かされます。
なお、この池田に出逢い、池田をモデルにした小説を書いたのは、池田の主張が掲載された「大阪時事新報」と経営者が同じで建物も同じだった「産経新聞」文化部に勤めていた記者でした。その記者は、歴史小説家に転じたのちも、秦氏と異教の関係について書き続けたのですが、その作家の筆名は「司馬遼太郎」でした。クラウタウさんのこの本は、こうした意外な事柄がたくさん記されています、
第三章では、1970年に神戸出身のユダヤ人と自称するイザヤ・ベンダサンの『日本人とユダヤ人』(山本書店)がベストセラーになってユダヤ人に対する関心が高まった翌年、内村鑑三の弟子で無教会主義のキリスト教者であった手島郁郎(1910-1973)が、佐伯の研究を踏まえて『太秦ウズマサの神―八幡信信仰とキリスト景教について』(東京キリスト教塾)を刊行したことについて検討します。
手島は、秦氏が奉じた八幡神は、モーセに啓示された神の名である「ヤハウェ」だと論じたのです。この主張は、彼のキリスト教改革運動と結びついていたうえ、この主張では、日本の古神道は日本的一神教であったヤハタ信仰と基本的に一致すると説いた由。
こうした主張が乱立した1970年代初頭に出版されたのが、法隆寺は聖徳太子の怨霊を鎮撫するための寺だと論じた梅原猛の『隠された十字架』でした。クラウタウさんは、上述のキリスト教説などの影響も受けていた梅原は、日本の古代史学界の研究成果を詳細に紹介せず、この分野の研究は著しく停滞しているため、自分が独自の視点によって新説を打ち出したというイメージを読者に植え付けたと指摘します。
そして、梅原説は従来の学説とは見方の違う新説などといったレベルのものではなく、まったくの事実誤認に基づく空想が多いことが古代史学者の反論によって示されたにもかかわらず、梅原はそうし批判は梅原説に対する本質的な反論になっていないと主張し続けたことも紹介されています。
第四章では、1970年代以後のオカルトブームという背景のもとで、梅原の影響を受けて聖徳太子を超能力者、それもボーイズラブとして描いた山岸涼子の漫画、『日出処の天子』と、ノストラダムスの予言を日本に紹介してベストセラーとなった五島勉が、中世には預言者とされていた聖徳太子を現代の預言者として描いた状況などを説明しています。
五島については、世界の終わりが来るという予言やその救済者などに関する記述が、複数の新興宗教に影響を与えたことを指摘します。そして、オウム真理教に直接の影響を与えたかどうかは不明であるとしつつ、麻原彰晃が逮捕の少し前に、聖徳太子が侍者を引き連れて現れて「日本をお願いします」と自分に頼んだ、と著書で述べていると指摘します。
サリン事件の後、五島は責任を感じたようで、聖書系の終末思想が世界中で何百というカルトを生みだしたと述べ、そうした「破滅=救済=選民」の予言を超える「日本独自の指針や予言」が必要だと述べるようになったと、クラウタウさんは説きます。
そして、「結」の「隠された聖徳太子の開示」は、コロナが流行した際、オカルト系のサイトに、聖徳太子がこれを予言していたという記事が載ったという話題で始まります。むろん、五島の影響ですが、「太子に仮託された予言書の権威を借りつつ、『未来』を語ろうとする姿勢は、令和の今日まで続いている」のです。
ユダヤ=キリスト教影響説は、新しい教科書をつくる会の二代目会長であった東北大学の美術史の教授で、現在は名誉教授の田中英道に受け継がれています(梅原にしても田中にしても、「大発見」をしたと称するのは、大山誠一を除いては古代史の専門訓練を受けていない学者ですね)。
田中は、最近は秦氏はフリーメーソンであって仁徳天皇陵古墳を造営したとも説いているうえ、聖徳太子は日本のキリスト教化をはかっていたユダヤ系の蘇我氏の計画に反対した結果、殺されたとしています。まさに邪悪なユダヤ人の陰謀という図式です。
クラウタウさんは、ユダヤ系の人間が日本の「変革」をはかっていたといった言葉使いは、日本の国体の「変革」を試みたとみなされる者たちへの厳しい処罰を定めた1925年の治安維持法と表現が似ていることに注目します。発想が似ているため、表現も似てくるのでしょう。
そうした非学問的で危険な本がかなり売れているのが現状です。つまり、学者の肩書きが利用され、出版社がそれに加担しているのです。クラウタウさんは、こうした状況の背後に、「娯楽としてのオカルトを求めるような文化が一九七〇年代にあった」ことを指摘します。
だからこそ、梅原の本が売れ、またそれに刺激されたオカルト的な説が次々に生まれたのです。しかも、学問成果とそうしたオカルト言説の境目は曖昧であり、時に交差することにクラウタウさんは注意するのです。
私は、三経義疏や古代の聖徳太子観、近代の国家主義的な太子観などを中心にして研究してきたため、精力的な文献調査をすることで知られるクラウタウさんのこの本については、知らないことがたくさんありました。偽史が生まれる背景やその危険さについて考えるうえでも有益ですので、一読をお勧めします。
なお、「あとがき」では、地味な分野である近代仏教学の研究者であったクラウタウさんを、オカルト研究に導いた先学であって、惜しくも先年亡くなった吉永進一さんの思い出と感謝が述べられています。
宗教学から東西の神秘思想研究に進んだ吉永さんは、とんでもなく博学であったうえ、気取らず、親しみやすい性格であって、仲間を集めて企画を実施するのも得意でした。
2019年に、既に病身となっていた吉永さんを駒澤大学に招き、クラウタウさんと心理学の谷口泰富先生にもご参加いただいて、儒教やオランダ医学も学んで東大初の仏教講義を行い、駒大の前身である曹洞宗大学林の総監を務めた原坦山と、西洋の神秘主義にも通じていた禅研究者で駒大初代学長、忽滑谷快天に関するシンポジウムを開催したことを思い出します(吉永さん・クラウタウさんの写真を含む記事は、こちら)。
【付記:2024年5月29日】
この本については、詳しいインタビューが28日に公開されました(こちら)。