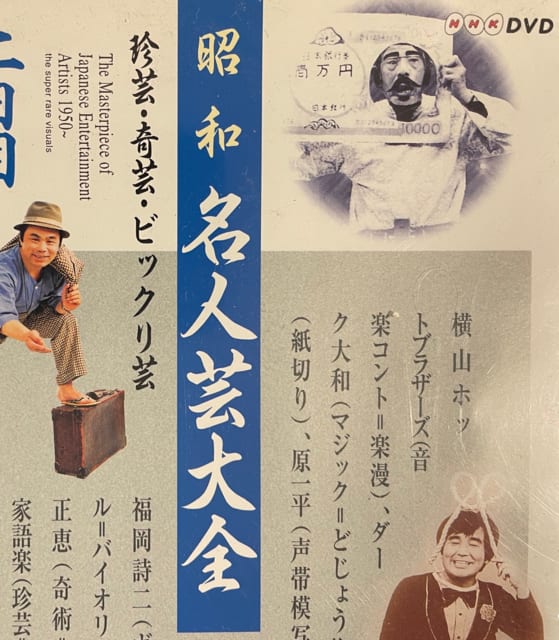金沢英之「天寿国繍帳銘の成立年代について-儀鳳暦による計算結果から-」
(『国語と国文学』 78(11)、2001年11月)
です。
天寿国繍帳の銘文では、「等已刀爾爾乃爾己等(とよとみみのみこと=豊聡耳尊)」、すなわち聖徳太子の母后である「間人公主」が、「歳在辛巳(620)十二月廿一癸酉」の「日入」時に亡くなったと記しています。しかし、当時使われていた元嘉暦では12月21日は「癸酉」ではなく「甲戌」であって、一日のずれが生じていることが早くから知られていました。
これについては、唐がその直前である618年に採用した戊寅暦によれば、21日は「癸酉」となるので問題ないとする説も出されましたが、提唱者である飯田瑞穂氏自身、可能性は低いと見ていました。
持統朝では儀鳳暦が採用されたものの、季節によって大陽や月の運行速度が変化することを考慮した複雑な計算法である定朔法は用いられず、年間を通して一定の速度として計算する簡便な平朔法が用いられました。この平朔法によると、十二月廿一日は、元嘉暦と同様に「甲戌」となり、やはりズレが残ります。
そこで、金沢氏は、より正確ではあるけれど複雑な定朔法で計算してみたところ、ズレは解消され、21日は「癸酉」となりました。このため、金沢氏は、銘文は後になって付加されたとする東野治之氏の説に賛同し、銘文のうち、前半の系譜部分は古い資料に基づくものの、「天皇」などの語が見え、儀鳳暦の定朔法を用いたと思われる日付の表記が見られる後半部分は、儀鳳暦が使われるようになった持統朝以後の作と推定したのです。この説は、根拠のある主張してかなりの支持を得ました。
その金沢説を疑ったのが、
北康宏『日本古代君主制成立史の研究』「附論三 天寿国繍帳銘文再読」(塙書房、2017年)
です。北氏は、推古天皇の孫娘であって晩年の太子の若い后となった橘大郎女が、太子の死を悲しみ、推古天皇にお願いして作ってもらった天寿国繍帳のこの銘文は、斑鳩近辺の豪族である膳氏出身の妃、菩岐々美郎女に対する強烈な対抗意識に基づくことに注意します。
菩岐々美郎女は、太子との間に8人の子をもうけており、最後は太子とともに病気で倒れ、一日違いで亡くなっていますので、后妃たちの中でも最も太子との関係が深かったことは疑いありません。法隆寺金堂の釈迦三尊像銘によれば、太子の母后が「辛巳年十二月」に病死してまもなく、菩岐々美郎女は太子とともに枕を並べて病床につき、「二月廿一日癸酉」に亡くなり、太子は翌日に亡くなったと記されています。
一方、天寿国繍帳銘では、膳妃のことなどは一言も触れず、「十二月二十一日癸酉」に母后が亡くなると、太子は母后と約束していたように後を追って「二月廿二日甲戌」の夜半に亡くなったと述べています。
北氏は、この母后の没日とされる「十二月二十一日癸酉」は、実は菩岐々美郎女の没日である「二月廿一日癸酉」を転用したのではないか、と見ます。つまり、太子が後を追ったのは、豪族出身の妃などではなく、皇后であった母后なのだと言えるように作為を加えたと推定するのです。
となれば、当然のことですが、前半で太子と橘大郎女の高貴な系譜が長々と述べられ、後半でそうした主張がなされるような銘文が、聖徳太子の神格化が進んだ後代になって作成されるのは考えがたいことになります。
北氏は、金沢氏の論文は、儀鳳暦(石井注:その定朔法)で計算すると1日のズレが発生しなくなるということを示しただけであり、儀鳳暦(の定朔法)で計算したとする証明にはなっていないと論じています。
この問題については、異様に精密な暦換算のフリーソフトとして名高く、LOD関連の賞も受賞している whenの開発者である suchowan (須賀隆)さんが、そのブログで取り上げています(こちら)。suchowanさんは、戊寅暦が伝わっていた可能性を否定したうえで、こう述べます。
そこまで手間をかけるものだろうか?
以上です。
suchowanさんは結論は保留していますが、太子の母后の没日だけ複雑な定朔法をもちいて計算したというのは無理そうですね。
漢字文献情報処理研究会の仲間である suchowanさんには、何度かご教示いただきましたが(有り難うございます)、平朔法を用いると、大の月が続く場合、二か月隔たった同じ日の干支は同じになり、大の月と小の月、または小の月と大の月が続く場合は一日違いになるため(同じになることは稀であるそうですが)、厳密に計算をしないのであれば、二か月前の廿一日をそのまま「癸酉」としてしまっても不思議ではないそうです。
そうなると、北氏の推測どおりである可能性もあることになりますね。いずれにしても、「天寿国繍帳銘は儀鳳暦を用いているから持統朝以後」とは確定できないことになります。