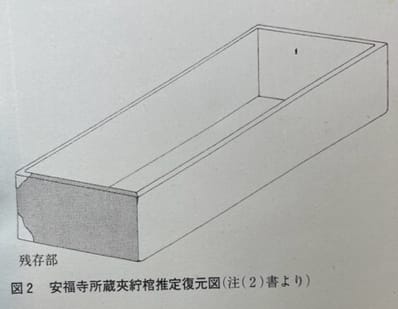7月29日に4回目のワクチン接種を予約してあったのですが、27日の法隆寺夏期大学での講義には間に合わず、ちょっと前にコロナに感染してしまいました。2日ほどで平熱に戻ったものの、隔離期間中ですので、奈良に行くことができなくなり、Zoomでしゃべって録画したものを流してもらう形になったのは残念なことでした。
講義の内容は、「聖徳太子は「海東の菩薩天子」たらんとしたか」(こちら)など、これまで書いてきたことを概略したものです。ただ、自分の研究について紹介する講演でも、尊敬する高崎直道先生は必ず一つ二つは新しい情報を加えておられました。遠く及ばないながらも、私もそれを模範とさせていただいているため、少々加えたことがあります。
その一つは、『日本書紀』用明紀が厩戸皇子の異称として「法主王」と記していることの意味です。この点については、これまでは三経義疏の学風である中国江南の成実涅槃学派の僧であって、「無忤」の振る舞いで知られ、朝鮮諸国から尊崇されていた梁・陳の宝瓊が若くして南㵎寺の「法主」となったことを例にあげていました。
つまり、「法主」とは講経の担当者、責任者を指すのであって、「法主王」のそうした「法主」である「王(みこ=皇子)」、講経の巧みな皇子という意味だと説明してきたのです。
用明紀で「法主王」と並んで記されている「法大王」という語にしても、実質は同じであって、講経の巧みな「大王(おおきみ)」ということですね。
「法王」の語も、これとほぼ同じであり、「法王」である釈尊のイメージが重ねられている場合も、「仏」とみなしているのではなく、やがて釈尊のような存在になるお方、といった意味だろうと説いてきました。「法皇」も発音は「法王」と同じであって意味も同様でしょう。ただ、「天皇」に準じる立場となっていたため、敬意をこめて「皇」の語を用いたものですね。
今回、加えたのは、『勝鬘経』講義で名高く、恐らく『勝鬘経義疏』の種本となる注釈を書いたと推測されている荘厳寺僧旻の例です。唐の道宣の『続高僧伝』僧旻伝によれば、
永元元年(四九九)、僧に勅し、局(かぎ)りて三十僧に請い、華林園にて夏に講ぜしむ。僧正、旻を法主為らしめんと擬すも、旻、之を止む。或ひと曰く、何が故ぞ。答えて曰く、此れ乃ち內、法師を潤すも、外、学士を益すあたわず。講者と謂うに非ず。
とあります。南斉の皇帝が30人の僧侶を招き、皇帝の御苑である華林園で講経をおこなわせた際、時の僧正はその中の荘厳寺僧旻を法主、すなわち、講経担当者としようとしたところ、僧旻はやめさせました。理由は僧侶相手に講義するだけであって、僧侶以外の知識人たちには無益なので、本当の「講者」とは呼べないから、というものでした。
この用例を重視すると、「法主」は、僧侶と在家信者を相手とし、感心させるような有益な講経ができる人、ということになります。なお、僧旻は『勝鬘経』の講義で名高く、聖徳太子の『勝鬘経義疏』は僧旻の注釈(現存せず、佚文のみ)を「本義」としたと推定されています。
『勝鬘経』はかなり理論的な経典であって、仏教学の専門家にとっても難しいものですので、推古朝当時、この講経を聞いて理解できた人が何人いたか疑問です。
ただ、『勝鬘経』は、国王夫妻の娘であって他国の王の妃となっている勝鬘夫人が仏を讃え、大乗仏教の教理を説いて釈尊から賞賛され、将来、王となり仏となると預言される経典ですので、欽明天皇の皇女であって、異母兄である敏達天皇の皇后となり、ついには天皇となって仏教を興隆した推古天皇は勝鬘夫人とイメージが見事に重なります。
また、『勝鬘経』は太子が手本とした中国南朝仏教が重視した経典です。その南朝仏教を代表する宝亮は、『涅槃経』を84回(題名解説だけなども含むか)、『勝鬘経』を42回、『維摩経』を20回、『大品般若』ないし『小品般若』を10回、『法華経』や『優婆塞戒経』その他の経典もほぼ10回講義してますが、南朝で最も尊重された『涅槃経』は36巻、『大品般若経』は20巻もあります。
つまり、『勝鬘経』と『法華経』の講経にせよ、三経義疏にせよ、上記の経典のうち、短いものを取り上げているのです。また、『優婆塞戒経』が「憲法十七条」や『勝鬘経義疏』で用いられていたことは、これまでブログで書いてきた通りです。
こうした点に注意しないと、『日本書紀』用明紀の「法大王」と「法主王」という言葉の意味は分からないのです。