親鸞が熱烈な太子信仰を抱いていたため、真宗は太子信仰が強く、研究も盛んです。来年は太子1400年遠忌ということで、真宗ではいろいろな行事が予定されているようですが、そうした中で、多角的な視点から太子と太子研究を見直す特集が刊行されました。
真宗大谷派の教学研究所が出している『教化研究』の166号です。
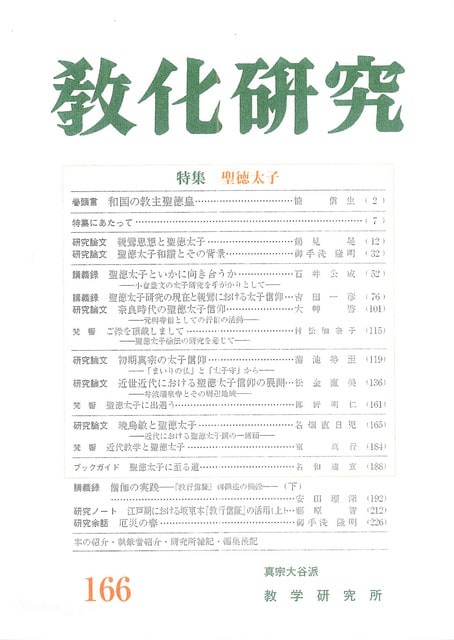
私の講義録は、太子について語るのは自分を語ることであって実は怖い行為であることについて説明した後、「厩戸王」という表現を戦後に作った小倉豊文の太子研究を戦前・戦中・戦後と時代順に検討し、誠実でひたむきな小倉の太子研究が、いかに時代の影響を受け、揺れ動いていたかについて述べたものです。
『教化研究』の表紙を見ればおわかりのように、太子いなかった派の吉田一彦さんも講義を載せてますが、私の「いなかった派」批判のうち、三経義疏は和習がたくさんあるため中国成立を説く藤枝説は成り立たないと私が指摘したことなど、自説にとって都合の悪い確定部分は無視したうえで、決択がついていない箇所だけとりあげ、石井反論は論証が不十分と言ってすませている感じがします。
吉田さんの太子論は、『日本書紀』の太子関連記述は様々な系統の資料、それも和習だらけの資料の寄せ集めであることに気づかず、唐に16年も留学した博学な道慈が書いたとする説を展開するなど、勇み足が目立ったものの(いなかった派は、その点を指摘されると、道慈は筆者ではなくプロデューサーだった説に切り替えましたが、文章チェックをしないプロデューサーって何なんでしょう?)、資料に基づく着実で有益な検討もかなりなされていただけに、上記のような論法は残念です。
今回の聖徳太子特集は、名和さんの「ブックガイド」を初めとして、聖徳太子研究・聖徳太子信仰研究を知りたい、始めたいという人には有益な論考が並んでいますので、お勧めです。
刊行されたばかりでまだ掲示されてませんでしたが、東本願寺出版のサイトで購入できるはずです(こちら)。
真宗大谷派の教学研究所が出している『教化研究』の166号です。
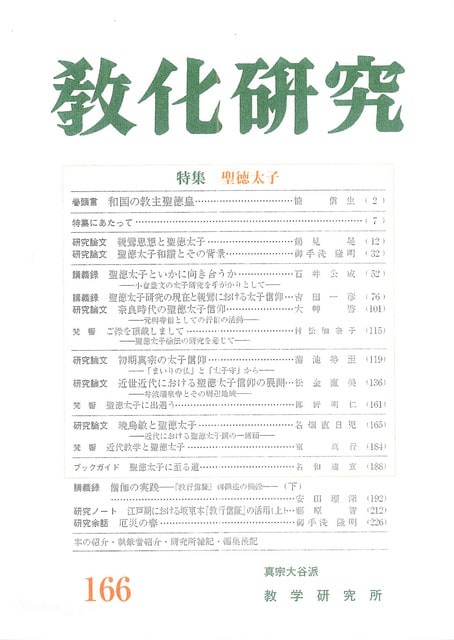
私の講義録は、太子について語るのは自分を語ることであって実は怖い行為であることについて説明した後、「厩戸王」という表現を戦後に作った小倉豊文の太子研究を戦前・戦中・戦後と時代順に検討し、誠実でひたむきな小倉の太子研究が、いかに時代の影響を受け、揺れ動いていたかについて述べたものです。
『教化研究』の表紙を見ればおわかりのように、太子いなかった派の吉田一彦さんも講義を載せてますが、私の「いなかった派」批判のうち、三経義疏は和習がたくさんあるため中国成立を説く藤枝説は成り立たないと私が指摘したことなど、自説にとって都合の悪い確定部分は無視したうえで、決択がついていない箇所だけとりあげ、石井反論は論証が不十分と言ってすませている感じがします。
吉田さんの太子論は、『日本書紀』の太子関連記述は様々な系統の資料、それも和習だらけの資料の寄せ集めであることに気づかず、唐に16年も留学した博学な道慈が書いたとする説を展開するなど、勇み足が目立ったものの(いなかった派は、その点を指摘されると、道慈は筆者ではなくプロデューサーだった説に切り替えましたが、文章チェックをしないプロデューサーって何なんでしょう?)、資料に基づく着実で有益な検討もかなりなされていただけに、上記のような論法は残念です。
今回の聖徳太子特集は、名和さんの「ブックガイド」を初めとして、聖徳太子研究・聖徳太子信仰研究を知りたい、始めたいという人には有益な論考が並んでいますので、お勧めです。
刊行されたばかりでまだ掲示されてませんでしたが、東本願寺出版のサイトで購入できるはずです(こちら)。













