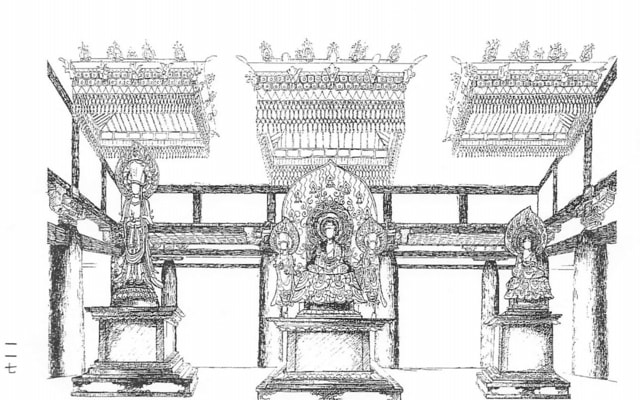来月の14日に四天王寺で講演をする予定です。題名は、
「聖徳太子はいなかった」説の誕生と終焉
このところ、講演や講義はリモートばかりでしたが、久しぶりに通常の対面の形でおこないます。定員200名なのに、9月初めに予約が満杯になった由。講演では、大山説が誕生する前の様々なトンデモ説にも簡単に触れる予定です。
イタリアンレストランで働いているうちに古代史に興味を持つようになり、1991年に『聖徳太子は蘇我入鹿だった』を出して話題を呼び、以後トンデモ本を書きまくっている関裕二とか、岡山大学の東洋史出身ながら、『聖徳太子の正体―英雄は海を渡ってやってきた』 (1993年)で太子は北方民族の首領だと説いた小林惠子とかですね(これについては、今年のエイプリルフールのおふざけ記事で対抗し、太子は英語を話すバイキングだったと書きました。こちら)。
こうしたトンデモ説の起源はどこかと考えてみたところ、敗戦後の騒がしい時代に大活躍した、破天荒作家、坂口安吾(1906-1955)の歴史物が大きな影響を与えているようです。
東洋大で仏教を学んだ後、作家となった安吾は、常識嫌いで精神不安定だったうえに薬物中毒となり、いろいろ問題を起こしますが、作品は個性的で類を見ないものばかりであり、私は学生の頃から大好きでした。没後に夫人が書いた追憶本なども買いました。
安吾の作品のうち、『明治開化 安吾捕物帖』(後に『勝海舟捕物帖』と改題)は、安吾お気に入りの人物だった勝夢酔の息子、勝海舟がいろいろな事件を推理する短編集です。普通の推理小説と違い、海舟のもっともらしい推理はことごとく外れるのですから、変わっています。
そうした迷探偵ぶりを歴史に関して発揮したのが、『文芸春秋』に昭和26年(1951)3月から12月まで連載し、また30年2月号から再開してその取材旅行から帰った翌日に急逝するまで続いた「安吾日本地理」シリーズです。その中の、
坂口安吾「飛鳥の幻」
(『坂口安吾選集』第二巻、創元社、1956年。現在は、『安吾の新日本地理』などの題名で文庫本が出てます)
は、「飛鳥の幻」となっているものの、吉野の話が長く続きます。安吾は、「神話と歴史の分水嶺は、仏教の渡来だろう」と書き、文字による記録の重要さを説いたのち、聖徳太子と馬子が協力して書いたとされる「天皇紀」、「国記」、各氏族の本記の考察に移り、これらが蘇我氏とともに亡びたという記述について、「一度疑ってみても悪くはなかろう」と述べます。
そして、東洋大で学んでいた際、日本仏教史となると『上宮聖徳法王帝説』や関連文献を読まされたと回想し、『法王帝説』は字数は少ないが面白いと言います。というのは、『日本書紀』が長々しく書いている箇所を、『法王帝説』は事実だけを「気持がいいほど無感情、実にあっさり」と書いているためだそうです。
その例として安吾があげるのが、蘇我入鹿が山背大兄一家を滅ぼし、後に入鹿とその父親である蝦夷が殺されて蘇我本宗家が亡びる事件です。この箇所について、『法王帝説』ではきわめて簡潔に書いているのに対し、『日本書紀』の記述は異様なほど長く、敵意に満ちているのです。
そこで安吾は、『法王帝説』のこの部分に「□□□」などの欠字が目立つのは、問題となる箇所を後人が伏せ字にしたのではないか、と推測します。そして、「山背大兄王及び十五王子を殺すとともに、蝦夷か入鹿のどちらかがハッキリ天皇位につき、民衆もそれを認めていたのではないかね」と述べ、そうした事実を隠そうとした証拠が上記の伏せ字なのではないか、と説くのです。
これは、大正期から戦時中にかけては検閲によって伏せ字にすることが多かったことから「推理」し、原本の写真版を見ずに活字本だけ見て想像したものですね。いつの時代も書き換えや削除は多いものの、もとの字数がわかるような形で伏せ字にするのは近代日本の検閲の工夫です。
『法王帝説』の簡潔な記述と違い、『日本書紀』のこの部分は非常に詳しいのですが、安吾はそれについて、「なんとまァ狂躁にみちた言々句々を重ねているのでしょうね」と述べ、ヒステリー的であって「ハッキリ血なまぐさい病気が、発作が、出ているようだ」と評します。
『日本書紀』全体の中で、ただ一箇所、調子が乱れていてざわめきたっているのがこの箇所であるのは、『日本書紀』成立の理由は天孫たる天皇の由来を説くためであるとし、蘇我天皇の存在を抹消しようとして、かくも感情的な記述をしたのだ、というのが安吾の推測です。「素人タンテイの心眼」なので怪しいと述べるのですが、『日本書紀』のこの箇所が大化の改新の詔と同様、怪しいことは確かですね。
そこで、安吾は蘇我氏の祖先について考察し、「蘇我氏の生態も、なんとなく大陸的で、大国主的であるですよ」と述べ、「私は書紀の役目の一ツが蘇我天皇の否定であると見る」ため、『日本書紀』の蘇我氏に関する記述は「そのままでは全然信用しないのである」と断言します。
「蘇我天皇」という言い方は、戦後になって天皇の子孫と称する人たちが次々に登場し、「熊沢天皇」などは、自分は現在の天皇まで続く北朝系に皇位を奪われた南朝系天皇の子孫であって皇位継承権があると主張し、騒ぎになったことを踏まえたものですね。
安吾の推測は、戦後になってそれまでの神格化された天皇像が否定されて言論が自由になり、安吾自身が手元の資料も十分でない状態で、「素人タンテイ」してみたものですので、問題も多いのですが、入鹿の暗殺前後の記述が異様であるのは確かです。安吾の主張は示唆に富んでおり、考慮に値するものです。
ただ、言論が自由といっても、戦時中の当局による検閲に変わり、敗戦直後は軍国主義的な発言を警戒するGHQの検閲がおこなわれており、安吾の「特攻隊に捧ぐ」は1947年に発禁となっています。
この時期に『堕落論』などを発表して戦中・戦後の常識を真っ向から批判し、くだけた率直な文体、魅力あふれる文体で大胆な主張を展開した安吾の作品は、戦後、大人気となりました。「新日本地理」シリーズも良く読まれ、現在までいろいろな版が刊行されています。
ただ、安吾の責任ではないのですが、聖徳太子の事績について戦前から疑い、著書が発禁となった津田左右吉の説が、戦後になって皇国史観を反省するようになった古代史学界で高く評価されるようになったのと同様、安吾のこうした推測は、話題作りを狙う素人の歴史ライターや、従来の歴史研究のパラダイムをひっくり返そうとした野心的な研究者たちに刺激を与えたのですね。
【付記】
「馬子=天皇」説などのトンデモ説の元祖、ということで記事を書き始め、確認が不充分なまま、「「蘇我馬子=天皇」説を提唱した~」という形の題名で早朝に公開してしまいましたので、題名を改めました。
「聖徳太子はいなかった」説の誕生と終焉
このところ、講演や講義はリモートばかりでしたが、久しぶりに通常の対面の形でおこないます。定員200名なのに、9月初めに予約が満杯になった由。講演では、大山説が誕生する前の様々なトンデモ説にも簡単に触れる予定です。
イタリアンレストランで働いているうちに古代史に興味を持つようになり、1991年に『聖徳太子は蘇我入鹿だった』を出して話題を呼び、以後トンデモ本を書きまくっている関裕二とか、岡山大学の東洋史出身ながら、『聖徳太子の正体―英雄は海を渡ってやってきた』 (1993年)で太子は北方民族の首領だと説いた小林惠子とかですね(これについては、今年のエイプリルフールのおふざけ記事で対抗し、太子は英語を話すバイキングだったと書きました。こちら)。
こうしたトンデモ説の起源はどこかと考えてみたところ、敗戦後の騒がしい時代に大活躍した、破天荒作家、坂口安吾(1906-1955)の歴史物が大きな影響を与えているようです。
東洋大で仏教を学んだ後、作家となった安吾は、常識嫌いで精神不安定だったうえに薬物中毒となり、いろいろ問題を起こしますが、作品は個性的で類を見ないものばかりであり、私は学生の頃から大好きでした。没後に夫人が書いた追憶本なども買いました。
安吾の作品のうち、『明治開化 安吾捕物帖』(後に『勝海舟捕物帖』と改題)は、安吾お気に入りの人物だった勝夢酔の息子、勝海舟がいろいろな事件を推理する短編集です。普通の推理小説と違い、海舟のもっともらしい推理はことごとく外れるのですから、変わっています。
そうした迷探偵ぶりを歴史に関して発揮したのが、『文芸春秋』に昭和26年(1951)3月から12月まで連載し、また30年2月号から再開してその取材旅行から帰った翌日に急逝するまで続いた「安吾日本地理」シリーズです。その中の、
坂口安吾「飛鳥の幻」
(『坂口安吾選集』第二巻、創元社、1956年。現在は、『安吾の新日本地理』などの題名で文庫本が出てます)
は、「飛鳥の幻」となっているものの、吉野の話が長く続きます。安吾は、「神話と歴史の分水嶺は、仏教の渡来だろう」と書き、文字による記録の重要さを説いたのち、聖徳太子と馬子が協力して書いたとされる「天皇紀」、「国記」、各氏族の本記の考察に移り、これらが蘇我氏とともに亡びたという記述について、「一度疑ってみても悪くはなかろう」と述べます。
そして、東洋大で学んでいた際、日本仏教史となると『上宮聖徳法王帝説』や関連文献を読まされたと回想し、『法王帝説』は字数は少ないが面白いと言います。というのは、『日本書紀』が長々しく書いている箇所を、『法王帝説』は事実だけを「気持がいいほど無感情、実にあっさり」と書いているためだそうです。
その例として安吾があげるのが、蘇我入鹿が山背大兄一家を滅ぼし、後に入鹿とその父親である蝦夷が殺されて蘇我本宗家が亡びる事件です。この箇所について、『法王帝説』ではきわめて簡潔に書いているのに対し、『日本書紀』の記述は異様なほど長く、敵意に満ちているのです。
そこで安吾は、『法王帝説』のこの部分に「□□□」などの欠字が目立つのは、問題となる箇所を後人が伏せ字にしたのではないか、と推測します。そして、「山背大兄王及び十五王子を殺すとともに、蝦夷か入鹿のどちらかがハッキリ天皇位につき、民衆もそれを認めていたのではないかね」と述べ、そうした事実を隠そうとした証拠が上記の伏せ字なのではないか、と説くのです。
これは、大正期から戦時中にかけては検閲によって伏せ字にすることが多かったことから「推理」し、原本の写真版を見ずに活字本だけ見て想像したものですね。いつの時代も書き換えや削除は多いものの、もとの字数がわかるような形で伏せ字にするのは近代日本の検閲の工夫です。
『法王帝説』の簡潔な記述と違い、『日本書紀』のこの部分は非常に詳しいのですが、安吾はそれについて、「なんとまァ狂躁にみちた言々句々を重ねているのでしょうね」と述べ、ヒステリー的であって「ハッキリ血なまぐさい病気が、発作が、出ているようだ」と評します。
『日本書紀』全体の中で、ただ一箇所、調子が乱れていてざわめきたっているのがこの箇所であるのは、『日本書紀』成立の理由は天孫たる天皇の由来を説くためであるとし、蘇我天皇の存在を抹消しようとして、かくも感情的な記述をしたのだ、というのが安吾の推測です。「素人タンテイの心眼」なので怪しいと述べるのですが、『日本書紀』のこの箇所が大化の改新の詔と同様、怪しいことは確かですね。
そこで、安吾は蘇我氏の祖先について考察し、「蘇我氏の生態も、なんとなく大陸的で、大国主的であるですよ」と述べ、「私は書紀の役目の一ツが蘇我天皇の否定であると見る」ため、『日本書紀』の蘇我氏に関する記述は「そのままでは全然信用しないのである」と断言します。
「蘇我天皇」という言い方は、戦後になって天皇の子孫と称する人たちが次々に登場し、「熊沢天皇」などは、自分は現在の天皇まで続く北朝系に皇位を奪われた南朝系天皇の子孫であって皇位継承権があると主張し、騒ぎになったことを踏まえたものですね。
安吾の推測は、戦後になってそれまでの神格化された天皇像が否定されて言論が自由になり、安吾自身が手元の資料も十分でない状態で、「素人タンテイ」してみたものですので、問題も多いのですが、入鹿の暗殺前後の記述が異様であるのは確かです。安吾の主張は示唆に富んでおり、考慮に値するものです。
ただ、言論が自由といっても、戦時中の当局による検閲に変わり、敗戦直後は軍国主義的な発言を警戒するGHQの検閲がおこなわれており、安吾の「特攻隊に捧ぐ」は1947年に発禁となっています。
この時期に『堕落論』などを発表して戦中・戦後の常識を真っ向から批判し、くだけた率直な文体、魅力あふれる文体で大胆な主張を展開した安吾の作品は、戦後、大人気となりました。「新日本地理」シリーズも良く読まれ、現在までいろいろな版が刊行されています。
ただ、安吾の責任ではないのですが、聖徳太子の事績について戦前から疑い、著書が発禁となった津田左右吉の説が、戦後になって皇国史観を反省するようになった古代史学界で高く評価されるようになったのと同様、安吾のこうした推測は、話題作りを狙う素人の歴史ライターや、従来の歴史研究のパラダイムをひっくり返そうとした野心的な研究者たちに刺激を与えたのですね。
【付記】
「馬子=天皇」説などのトンデモ説の元祖、ということで記事を書き始め、確認が不充分なまま、「「蘇我馬子=天皇」説を提唱した~」という形の題名で早朝に公開してしまいましたので、題名を改めました。