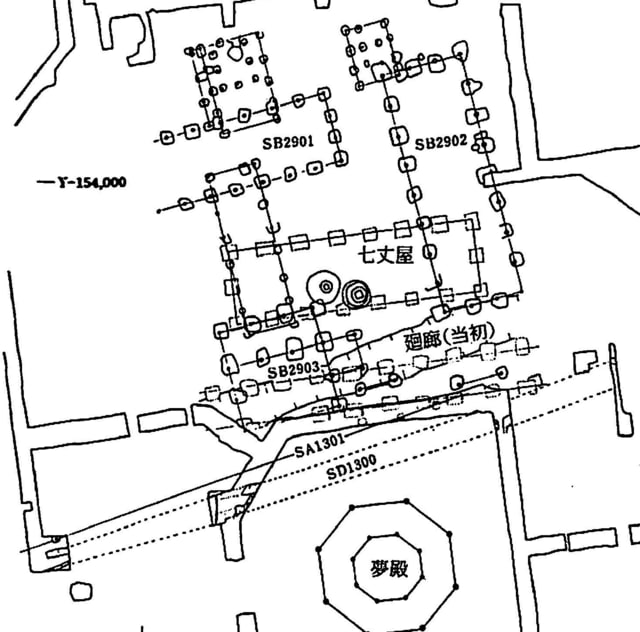その瓦は瓦窯で焼かれます。このブログでは、そうした瓦窯に関する論文をいくつも紹介してきましたが、その瓦窯とヤマト朝廷の直轄地である屯倉(みやけ)の関係に関して早い時期にすぐれた指摘をしていたのが、
上原真人「初期瓦生産と屯倉制」
(『京都大學文學部研究紀要』42号、2003年3月)
です。
上原氏は、飛鳥寺の造営から話を始めます。飛鳥寺の瓦は、百済の王興寺を造営したグループから来た4人の瓦博士、それも星組と花組と称される異なる系統の瓦を作成した2組の工人たちが指導して作成しますが、何しろ日本初のことですので、飛鳥寺に隣接する南東の丘に瓦窯が2基、作られました。以後の瓦窯が寺から離れた場所に設置されたのとは異なり、作業している工人の姿も見える距離です。
星組が作成した弁端点珠形式の瓦は、僧寺である飛鳥寺と対になる尼寺である豊浦寺の金堂でも用いられ、さらに斑鳩の若草伽藍金堂と創建瓦となります。若草伽藍では、その瓦当笵を用いたほか、やや丸みを帯びた花弁の先端に珠点を置く瓦の瓦当笵を新たに造りだしました。この瓦当笵は、かなり使われ、痛みが進んだ段階で四天王寺の瓦の作成に用いられました。
このほか、星組の系統の瓦は、河内新堂廃寺の創建瓦として用いられたほか、7世紀前半のうちに大和・摂津・河内の広い地域で用いられ、トレースできます。これは星組の工人たちが伝統を墨守する傾向があったためと吉川氏は説きます。
一方、花組の瓦は、豊浦寺で用いられたほか、和田廃寺、古宮遺跡、南山城の高麗寺などでも用いられているものの、主力ではなかったとされます。このため、花組は影が薄いとされるのですが、吉川氏は、中央では傍流でも、地方では広範に活動していたとし、目立たないのは技術的に柔軟であって、従来の須恵器の工人たちが動員された結果、変化が進んだためと見ます。四天王寺創建瓦を生産した楠葉平野山窯も、瓦と須恵器の生産を兼業していました。
問題は、飛鳥寺の創建瓦はすぐ側の瓦窯で焼かれたのに対し、豊浦寺に瓦を供給した山背の隼上り窯は、豊浦寺から北に50km も離れていることです。四天王寺の瓦を焼いた楠葉平野山窯は四天王寺から30km、豊浦寺や奥山廃寺に瓦を供給した明石市の高丘窯は80km、豊浦寺や奥山廃寺に供給した岡山の末ノ奧窯に至っては、180kmも離れています。そこまでいかないものの、数十km離れている例は他にもあります。
そこで吉川氏が注目したのは、これらの遠い瓦窯の地が、蘇我氏が管理していた屯倉の地とされる土地と見事に一致することです。つまり、早い時期に瓦を生産したのは、天皇・皇族の屯倉の所在地、あるいは屯倉の近くにあって水運の便の良い拠点近くの土地であって、上宮王家を含む蘇我氏や秦氏が関わっていた土地なのです。そう言えば、蘇我氏が台頭したのは、渡来人を使って屯倉を管理したことが一因でした。
これらの地に築かれた瓦窯は、特定の寺専用ではなく、他の寺の瓦も供給したほか、瓦窯周辺の地域の寺の瓦も作成したとします。屯倉は農業の生産地に設置されるのですが、吉川氏は、その近辺の山林、河川、海浜なども含めた領地支配となっており、窯業技術がもたらされて産業が発展したと見るのです。
ただ、初期にはその地域の寺は無く、飛鳥・斑鳩・河内などの寺に運ばれたため、瓦の生産は「貢納」という面を持っていたと、吉川氏は推測します。
これは重要な指摘ですね。瓦は最初期には寺だけ、後もしばらくは寺と政庁にだけ用いられましたので、蘇我氏、それを受け継いだ王権によって管理されていたことになります。瓦の生産は、最先端の国家技術だったのです。
仏教自体は渡来人によって公伝以前に各地に入っていたと思われますが、早い時期に瓦葺きの壮大な寺院を建設できたのは、またその瓦を供給できたのは、中国南朝と交流していた百済の国家技術を導入した蘇我氏とその関連氏族だけでした。
仏像や仏とおぼしき像が見える鏡などは、古いものが各地で発見されていますが、6世紀末から7世紀半ば頃の大きな寺院の遺跡や瓦窯などについては、蘇我氏、蘇我系である上宮王家、そして上宮王家と関係深く、その資産を受け継いだと思われる舒明天皇関連以外の地で発見されないのは、当然ですね。