 もしも本書のタイトルが「カラヤンの素顔」だったら、私は手にとっただろうか。没後20年を過ぎても尚その名前は燦然と輝き、「カラヤン」というブランドだけでも売れるのが、世界で最も有名であり偉大なる指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤン。さまざまな意味と感情をこめられて名前に”帝王”がつくカラヤンは、時にはやはり諸々の感情やおひれがついて”暴君”という冠もつけられたことがある。「素顔のカラヤン」は、1973年に日本人として初めてカラヤンに単独インタビューに成功して以来、すっかり帝王に気に入られて(信頼されて)通訳や秘書役を15年の歳月に渡り勤めるようになり、エリエッテ夫人やふたりの娘とも親交のあった眞鍋圭子さんが語る巨匠の一般にはあまり知られていない素顔である。
もしも本書のタイトルが「カラヤンの素顔」だったら、私は手にとっただろうか。没後20年を過ぎても尚その名前は燦然と輝き、「カラヤン」というブランドだけでも売れるのが、世界で最も有名であり偉大なる指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤン。さまざまな意味と感情をこめられて名前に”帝王”がつくカラヤンは、時にはやはり諸々の感情やおひれがついて”暴君”という冠もつけられたことがある。「素顔のカラヤン」は、1973年に日本人として初めてカラヤンに単独インタビューに成功して以来、すっかり帝王に気に入られて(信頼されて)通訳や秘書役を15年の歳月に渡り勤めるようになり、エリエッテ夫人やふたりの娘とも親交のあった眞鍋圭子さんが語る巨匠の一般にはあまり知られていない素顔である。巨星のようなカラヤンを書いた本、書かれた小話はとても多い。専門的な音楽家としても著作物も大事だが、本書のようにカラヤンのひととなりを紹介する本も音楽愛好家にとっては嬉しい一冊である。コックピットの中で自家用ジェット機を操縦し、自分の船の舵をきる日焼けしたカラヤン。おしゃれで身だしなみは常に完璧、見映えを意識したアングルでの映像撮影、スピード狂でポルシュを運転し、そばには婚約当時ディオールのミューズとして活躍して世界で最も美しいと言われた美しい夫人がよりそう。そして職業は、ベルリン・フィルを振る指揮者。指揮者として最も華やかな存在だったカラヤン。見方によっては、マスコミの格好の対象の派手な私生活にもみえる。
しかし、ドキュメンタリー映画『カラヤンの美』で撮影されていたザルツブルグ郊外アニーフでの自宅は、庭こそ広いが室内はその華やかな人生と比較して、むしろ簡素でおだやかな静けさに包まれていた。生前のカラヤンは、田舎の静かな暮らしを好んでいたという。そしてふたりの娘たちには、規律正しく贅沢はさせずに質素な生活を教育方針としていた。それこそ、素顔のカラヤンなのだろう。このような本は、一歩間違えれば暴露めいた秘話になってしまったり、世界のスーパースターといかに自分が親しかったのかというさりげないアピールをしつつ、まるで皇室のように非のうちどころのない絶対的存在のように崇め奉るような内容になるおそれもある。しかし、本書はさりげないエピソードを紹介しながら、シャイで口下手なために誤解を招くこともあり、晩年はベルリン・フィルとの厳しい確執もあったが、忍耐強く生真面目に誠実に生涯を”ミューズ”にささげたひとりの努力家のカラヤン像がうかんでくる。
そうだったのかカラヤン、いいヒトだった!!すっかり私も、音楽だけでなくカラヤンその人も好きになってしまったではないか。
本書の成功のポイントは、著者が女性だったことにあると思う。
眞鍋さんの文章は、外国暮らしの長い女性にあるように、日本語がとても丁寧で美しく品がよい。最近の女性作家のエッセイにあるノリがよいが手垢のついた単語が並ぶ文章とは雰囲気がまるで異なる。有能な方らしい機転と率直さや機敏さも想像されるのだが、女性らしいやわらかで純粋な感性と視点があたたかく人々を包み、読んでいるうちに心が洗われていくような気がする。エピローグの89年11月12日のサントリーホールでのカラヤン追悼会の模様では、すっかりこころがうるおってきた。それに、カラヤンの秘書やコーディネイト役をしていたので、ビジネス上の利害関係にはあまりなかったのもよかったのだろう。
そしてその私が最も好きなサントリーホールの設立には、カラヤンの適格なアドヴァイスが生かされている。ご存知のようにサントリーホールはベルリンフィルの拠点と同じ日本で初めてのヴィンヤード型である。当時の日本では、ウィーンの楽友協会のような”シューボックス型”がよいという意見が主流で、日本で初めてでもあり音響的に成功するのが難しいと言われていた。佐治敬三社長に質問にカラヤンはこたえた。
「今の世の中、再生装置がどんどん進歩しているから、よい音楽は家でも聴けます。だからこそ、聴衆がわざわざコンサートホールに足を運んで音楽を聴くのは特別なのです。コンサートでは、一緒にともに音楽をするのであり、それが現代のライブコンサートの意味ではないかと私は思うのです。だから、私はオーケストラを真中において、周囲から聴衆に囲まれて、聴衆と一体となって音楽をしようと思っています。」
私がこのホールを特に気にいっているのは、ヴィンヤード型だからである。また今では常設されているのが珍しくないパイプオルガン設置のアドバイスなど、サントリーホール設立の貢献には、全く感謝である。
「ああー、なるほど。そな、そうしましょ!」
後にカラヤン自身が「音の宝石箱」と名言を残したサントリーホールの形が決定した瞬間だった。83年1月30日のことだったそうだ。
■アーカイブ
・『カラヤンの美』
・『カラヤン生誕100年 モーツァルトヴァイオリン協奏曲』
・「指揮台の神々」











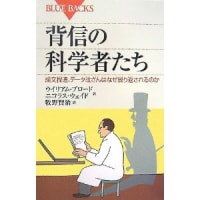

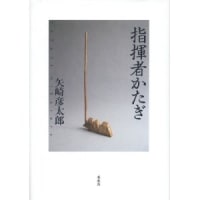
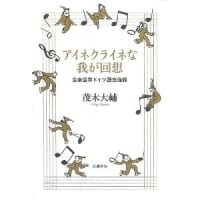
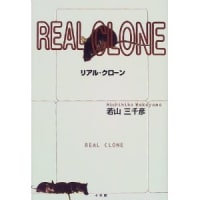
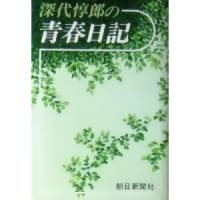
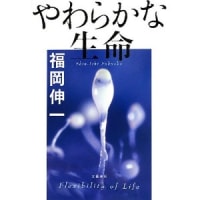
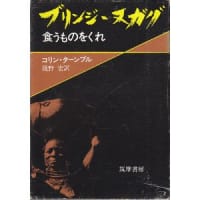
>私生活のために職権を利用しなかったことなど
ドキュメンタリー映画『カラヤンの美』でのカラヤンの印象は、これまで言われていた像と違っていました。本書を読んでよかったです。
>、この時相当な背中の痛みをおして指揮していたのですね
何回の大手術をされてきたなんて知りませんでした。you tubeですか、ほう~~っ、それは大事な情報をありがとうございます!