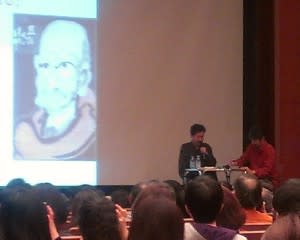■東京大学史料編纂所 第37回史料展覧会(2016年11月12日~13日)
おおよそ3年に一度、2日間だけ開催される史料展覧会。私は2010年の第35回以来になる(第36回は北海道にいた時期なので見逃している)。 今回は「史料を後世に伝える」がテーマで、史料の研究・編纂や収集・公開という史料編纂所の事業に関する展示品が、例年より多かった。嫌いなテーマじゃないけど、もう少し史料原本を見せてほしいなあとも感じた。戦時中に図書を疎開させたときの記録が興味深く、疎開先としては、長野県上田市と同伊奈郡が選ばれている。空襲が激しくなってきた昭和20年7月には、上田図書館内の図書をさらに小県郡室賀村と更級郡村上村に移したという記述を読んで、小県(ちいさがた)といえば、真田の郷ではないか、とにやりとする。あと、この時代は「個人宅の土蔵」というのがまだ残っていたんだなあ、と感慨深かった。
「江戸名所図会」「武江年表」で知られる斎藤月岑の日記は史料編纂所が所蔵しているのだな。第1冊は、ページの上部に小さな挿絵がたくさん描かれていて楽しい。そして『大日本古記録』には、ちゃんとその絵が採録されていることをはじめて知った。近年、重要文化財の指定を受けた「慈鎮和尚夢想記」と「蒋洲咨文」は今年の見ものだろう。前者は筆跡の特徴から慈円(慈鎮)筆と推定されているそうだ。後者は、明朝の使者・蒋洲が対馬国に宛てて倭寇禁圧を求めた文書。どでかい料紙に細密な文字で記されている。1977年に購入したが、修復の目途が立たないまま歳月を重ね、2007-08年にようやく処理を施され、2010年正式に資料番号を付して入架という、展示図録に記された経緯が泣かせる。修復待ちで寝かされている史料、ほかにもあるのかしら。2013年の第36回史料展覧会で初展示されたとのこと。
■国立公文書館 平成28年度第3回企画展『書物を愛する人々』(2016年10月29日~12月17日)
旧内閣文庫の貴重書が見られるので、うきうきして出かけたら、ほとんど人がいなくて拍子抜けした。やっぱり「徳川家康」とか「たのしい地獄」に比べると「書物を愛する人々」って全然受けないのだな~。それはともかく、ゆかりの蔵書家として名前があがっているのは、市橋長昭、毛利高標、木村蒹葭堂、太田道灌、狩谷棭斎、多紀元堅、渋江抽斎。市橋長昭は、国立公文書館の創立40周年記念貴重資料展(2011年)で覚えた名前。重要文化財の宋版漢籍が並んでいる。そのいくつかには「顔氏家訓曰」で始まる大ぶりな朱印が押されていて、前回も気になったのだが、狩谷棭斎の説によれば、これは書物の価値を高く見せようとして商人が押した「偽印」だという。ええ~そんなのありか。この展覧会は、蔵書印の説明が丁寧で、とても面白かった。欠画の説明も。
後半は、書物を守り伝える工夫を紹介。旧医学館所蔵の『黄帝内経素問』にはタバコの葉のかたちをした蔵書印が押されている。これはタバコに防虫剤の効果があったためというが、『義門読書記』の秩の内側には、本物のタバコの葉を入れた袋が張り付けられていて、びっくりした。そして、この展覧会、フラッシュを焚かなければ、どの資料も撮影自由というのが太っ腹ですごい。写真は、宋版『予章先生集』(黄庭堅の詩文集)。字が大きくて、墨の色がきれいだなあ。

■印刷博物館 『武士と印刷』(2016年10月22日~2017年1月15日)
第1部「武者絵に見る武士たちの系譜」と第2部「武士による印刷物」の二部構成。第2部だけだと地味すぎて人が来ないという判断だったんじゃないかと推測するけど、両者の関係が分かりにくくて、あまり成功していない。第2部は、戦国から江戸幕末まで、約70人の武士が刷らせたおよそ160点の印刷資料を展示する。家康の伏見版や直江兼続の直江版『文選』もあり。これらは、関ケ原と大坂の陣の間の時期に刊行されている。第1部は歌川国芳の武者絵が中心で、まだまだ私の知らないカッコいい作品があるんだな、とウットリ。
おおよそ3年に一度、2日間だけ開催される史料展覧会。私は2010年の第35回以来になる(第36回は北海道にいた時期なので見逃している)。 今回は「史料を後世に伝える」がテーマで、史料の研究・編纂や収集・公開という史料編纂所の事業に関する展示品が、例年より多かった。嫌いなテーマじゃないけど、もう少し史料原本を見せてほしいなあとも感じた。戦時中に図書を疎開させたときの記録が興味深く、疎開先としては、長野県上田市と同伊奈郡が選ばれている。空襲が激しくなってきた昭和20年7月には、上田図書館内の図書をさらに小県郡室賀村と更級郡村上村に移したという記述を読んで、小県(ちいさがた)といえば、真田の郷ではないか、とにやりとする。あと、この時代は「個人宅の土蔵」というのがまだ残っていたんだなあ、と感慨深かった。
「江戸名所図会」「武江年表」で知られる斎藤月岑の日記は史料編纂所が所蔵しているのだな。第1冊は、ページの上部に小さな挿絵がたくさん描かれていて楽しい。そして『大日本古記録』には、ちゃんとその絵が採録されていることをはじめて知った。近年、重要文化財の指定を受けた「慈鎮和尚夢想記」と「蒋洲咨文」は今年の見ものだろう。前者は筆跡の特徴から慈円(慈鎮)筆と推定されているそうだ。後者は、明朝の使者・蒋洲が対馬国に宛てて倭寇禁圧を求めた文書。どでかい料紙に細密な文字で記されている。1977年に購入したが、修復の目途が立たないまま歳月を重ね、2007-08年にようやく処理を施され、2010年正式に資料番号を付して入架という、展示図録に記された経緯が泣かせる。修復待ちで寝かされている史料、ほかにもあるのかしら。2013年の第36回史料展覧会で初展示されたとのこと。
■国立公文書館 平成28年度第3回企画展『書物を愛する人々』(2016年10月29日~12月17日)
旧内閣文庫の貴重書が見られるので、うきうきして出かけたら、ほとんど人がいなくて拍子抜けした。やっぱり「徳川家康」とか「たのしい地獄」に比べると「書物を愛する人々」って全然受けないのだな~。それはともかく、ゆかりの蔵書家として名前があがっているのは、市橋長昭、毛利高標、木村蒹葭堂、太田道灌、狩谷棭斎、多紀元堅、渋江抽斎。市橋長昭は、国立公文書館の創立40周年記念貴重資料展(2011年)で覚えた名前。重要文化財の宋版漢籍が並んでいる。そのいくつかには「顔氏家訓曰」で始まる大ぶりな朱印が押されていて、前回も気になったのだが、狩谷棭斎の説によれば、これは書物の価値を高く見せようとして商人が押した「偽印」だという。ええ~そんなのありか。この展覧会は、蔵書印の説明が丁寧で、とても面白かった。欠画の説明も。
後半は、書物を守り伝える工夫を紹介。旧医学館所蔵の『黄帝内経素問』にはタバコの葉のかたちをした蔵書印が押されている。これはタバコに防虫剤の効果があったためというが、『義門読書記』の秩の内側には、本物のタバコの葉を入れた袋が張り付けられていて、びっくりした。そして、この展覧会、フラッシュを焚かなければ、どの資料も撮影自由というのが太っ腹ですごい。写真は、宋版『予章先生集』(黄庭堅の詩文集)。字が大きくて、墨の色がきれいだなあ。

■印刷博物館 『武士と印刷』(2016年10月22日~2017年1月15日)
第1部「武者絵に見る武士たちの系譜」と第2部「武士による印刷物」の二部構成。第2部だけだと地味すぎて人が来ないという判断だったんじゃないかと推測するけど、両者の関係が分かりにくくて、あまり成功していない。第2部は、戦国から江戸幕末まで、約70人の武士が刷らせたおよそ160点の印刷資料を展示する。家康の伏見版や直江兼続の直江版『文選』もあり。これらは、関ケ原と大坂の陣の間の時期に刊行されている。第1部は歌川国芳の武者絵が中心で、まだまだ私の知らないカッコいい作品があるんだな、とウットリ。