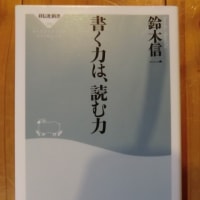秋も深まる某日、昔同じ職場で机を並べていた釣り友達のA君から電話があり、仕事で別府に出張するので久しぶりに一杯やろうかとの誘い。
A君は自分より1年後(あと)に退職し、現在は第2の就職先で活躍中、お互いに1年以上顔を合わせていないので懐かしさと釣り情報の交換もかねて一つ返事でOK.
A君はどちらかといえば防波堤でこじんまりと釣るタイプではなくて、渡し船で磯に渡って大物を狙う豪快な釣り師である。
釣り歴40年以上、釣技の方は釣りメーカー主催の数々のトーナメントに参加して上位入賞をするほどの折り紙つきで自分ごときははるかに及ばず、これまでも随分いろいろと教えてもらっている。
この夜も、JR別府駅近くの居酒屋で17時から20時まで3時間とにかく釣りの話ばかりした。大の男が酔いの勢いも手伝って口角泡を飛ばして大声で熱心に語り合うので店の人も驚いたかもしれない。
断片的になるが、会話の内容を忘れないように記録に留めておくことにした。
・釣りは、仕掛けの準備に始まり、釣っている間、そして釣った後の獲物と長時間ずっと尾を引いて楽しめるのでこれほど面白い趣味はそうそう見当たらない。
・釣りにはパーフェクトはない。釣行の後に、必ずあそこでこうしておけばという反省材料がある。何回行ってもその繰り返しである。それだけにものすごく奥が深い。
・釣りとは”海との対話”だ。釣果にはそれほどこだわらないこと、大自然に触れるのが主眼。大物をバラして楽しむ境地も一興か。
・仕掛けのポイントは何といってもウキ。ウキの選択が釣り方全てを支配する。A君はここ2年来、釣研(メーカー)の環付の「ど遠投」を錘の負荷に応じて0号、G2、B、3Bの種類を当日の風と潮の状況で使い分けている。このウキはこれから冬に向けて深場狙いに良さそうなので自分も早速、翌日に釣具店に走った。負荷Bを購入したがそれ以外は全て売り切れだった
・釣り道具のうちの花形的存在は竿。A君は現在ダイワ(メーカー)のメガドライ(中通し)を愛用している、自分は外ガイド付の”がまかつ”(メーカー)の竿を愛用。がまかつの竿の弾力による魚の引き寄せパワーはA君も一目置いている。なお、シマノ(メーカー)の中通し竿はイマイチの評。
・竿の次に来る花形的な存在は、リール。これはダイワよりシマノのほうが一日の長がある、自転車の多段ギアで驚異的なシェアを誇る技術が如実に生かされている。
・さて、釣りの腕とは何ぞや?
端的にいえば”魚のいる場所にエサを届けて食わせる技術”といえる。逆にいえば、どうしても釣れないときになぜ釣れないのかその原因をつきとめ、適切な対応ができるのが釣師の腕になる。
たとえば、魚がいないと思えばあっさりと場所を替わる、魚が居ても食わないと思えば適切な仕掛けに替える、その辺の見極めが第一ポイント。
第二のポイントは魚が居ても食わないときに、いろんなノウハウが必要となる。ノウハウとは釣り道具を含めた細かい選択の積み重ねと言い換えてもいい。以下、細かくいくと、
①釣り針の選択
釣り人と魚の唯一の接点になる釣り針に無関心は許されない。まずサイズがポイントで、魚が口に含むときに違和感を持たせないことが肝要。
小さいサイズは食い込みがよいが魚の口に掛かりにくい
大きいサイズは食い込みが悪いが魚の口にしっかり掛かる、
結局、一長一短だが小は大を兼ねるケースが多く小サイズが有利。また、魚が掛かった後では、それなりの強度も必要になる。
②錘(おもり)のサイズと打ち場所の選択
錘をハリスのどの部分に打つか(段打ち)、錘の大きさはどのくらいにするかがすごく大切で、ある意味では釣技の頂点に位置するといってよいほどセンスが問われるところ。これまで、錘の打ち方一つで釣果に雲泥の差が出ることをイヤというほど体験してきた。
ウキ、風の強さ、潮の流れ具合を勘案して微妙に使い分けてエサを魚のいる層に届け、そして魚がエサをくわえたときに糸の揺れで違和感を持たせない打ち方に留意。
③針素(ハリス)と道糸の選択
魚からの視認、風の抵抗などから細い糸を使うに越したことはないが、あまり細すぎると魚をバラシやすいので、予想できる魚の大きさによって最適の糸サイズを使い分ける。防波堤と磯ではサイズがグンと違ってくる。
④ウキ、竿、リールの選択は前述したので省略するが、ウキ下の長さをどの程度にするかも重要なポイント。
⑤マキエの種類、撒き方の選択
集魚剤の種類、オキアミ、アミの量の混ぜ具合に独特のノウハウがある。
次に、潮の速さに応じてマキエを打つ場所を選定し、海中でツケエと同調させていかに魚の口に持っていくのかが釣果を大きく左右する。
⑥ツケエ(釣針に付けたエサ)の選択
これも各人のノウハウがある。A君によると10月27日開催の県南クロ釣りトーナメントの優勝者は最後までツケエのノウハウを明らかにしなかったとのこと。たとえばオキアミ、サシアミを数日間ハチミツに漬け込む、ミリンにつけておくなどいろいろある。それぞれ各人ごとの秘中の秘となっている。
⑦魚を掛けてからの取り込み
竿の弾力利用の仕方、タモ網の掬い方のタイミングなどだが経験を積む以外に上達のコツはない。
⑧釣れる場所の情報取得
話の中でこれに一番時間を費やしたが実に参考になった。A君は自分が通い詰めているY半島を一時期、勤務地にしていたこともあり釣れる場所にも詳しい。箸袋の紙を丁寧に伸ばして図解してくれたのでよく分かった。同じ釣り場でも、釣れるポイントとそうでないところがある。海中の根に近いポイントが有利なことはいうまでもない。
とにかく、肝胆相照らす釣りキチ同士がお互いのノウハウを出し尽くして語り合うこの3時間は至福の時間だった。釣りにはこういう楽しみもあると思った。
惜しむらくは、A君が在職中のため平日に一緒に釣行できないことが残念。別れ際に”なるべく早く仕事を辞めて一緒に釣りに行こうよ”と無理を言いつつA君が乗った電車を見送った。