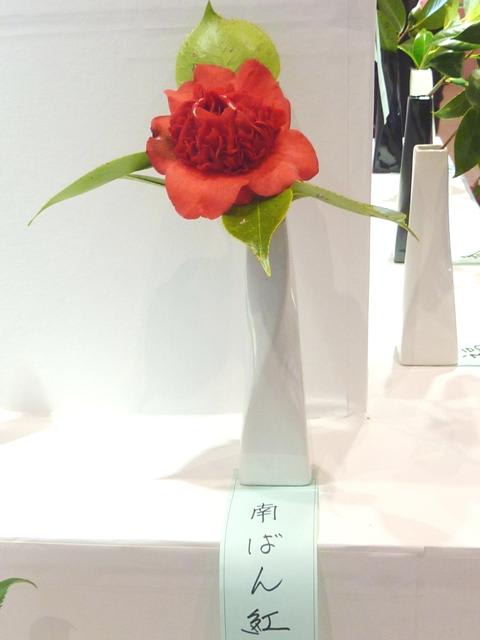昨日、白山麓の樹木公園に散歩に行って来ました、北陸の金沢周辺の桜の開花は三月末が予想されています、樹木公園は金沢より海抜の高いところに有ります、染井吉野の蕾は固くgoの開花予想では四月の五日~七日頃になるのではと思っています。
樹木公園には色々な桜が植えられていて、一足早い満開を迎えている桜もあります、最初に目に留まったのが河津桜でした、青い葉の新芽が出ているので満開を過ぎたのでしょう。
冬枯れた梢の中に黄色の花が咲いている木が有りました、山椒の黄色の花でした。
トサミズキの花
ヒュウガミズキの花
椿寒桜の花は満開でした、花が房状にかたまって咲いていてとても奇麗でした。
桜の花のイメージのチェリーピンクの色より濃い紅色の寒緋桜の花は遠くから目立ちました。
高い木の上に咲いていて、望遠で写してもこの程度でした、木には「大寒桜(おおかんさくら)」札が掛かっていました。
桜の木の下に咲いていたカタクリの花
湿地帯の近くには黄色の「ウマノアシガタ」が一輪だけ咲いていました。
終戦後に食べて事が有るような、食用にもなる「ヤブカンゾウ」が柔らかな芽を出していました。
野生の葱の様な「アサツキ」です、ここは公園の中なので採集できませんが、渓流釣りに行った山の物を摘んできて食べたことが有ります、酢味噌和えにしたら日本酒に良く合います。
日本の里山にはどこにも咲いているスミレです、童謡にも出てきますが春の代表的な草花ですね。
杉林の中のアオキに真赤な実が生っていました、青い葉に真赤な実が映えてとても奇麗でした。
春一番の花として知られている「ショウジョウバカマ」の花です、花は綺麗に咲いていますが葉が動物に食べられてい寂しい花になっています。
未だ冬景色かな?、と思って行った樹木公園には少しずつ春が近付いてきていました、もう暫くで染井吉野の花が樹木公園を埋め尽くすことでしょう、その頃には必ずお花見に行きます。
御訪問ありがとうございます。
(コメント欄は閉じさせていただいています)
樹木公園には色々な桜が植えられていて、一足早い満開を迎えている桜もあります、最初に目に留まったのが河津桜でした、青い葉の新芽が出ているので満開を過ぎたのでしょう。
冬枯れた梢の中に黄色の花が咲いている木が有りました、山椒の黄色の花でした。
トサミズキの花
ヒュウガミズキの花
椿寒桜の花は満開でした、花が房状にかたまって咲いていてとても奇麗でした。
桜の花のイメージのチェリーピンクの色より濃い紅色の寒緋桜の花は遠くから目立ちました。
高い木の上に咲いていて、望遠で写してもこの程度でした、木には「大寒桜(おおかんさくら)」札が掛かっていました。
桜の木の下に咲いていたカタクリの花
湿地帯の近くには黄色の「ウマノアシガタ」が一輪だけ咲いていました。
終戦後に食べて事が有るような、食用にもなる「ヤブカンゾウ」が柔らかな芽を出していました。
野生の葱の様な「アサツキ」です、ここは公園の中なので採集できませんが、渓流釣りに行った山の物を摘んできて食べたことが有ります、酢味噌和えにしたら日本酒に良く合います。
日本の里山にはどこにも咲いているスミレです、童謡にも出てきますが春の代表的な草花ですね。
杉林の中のアオキに真赤な実が生っていました、青い葉に真赤な実が映えてとても奇麗でした。
春一番の花として知られている「ショウジョウバカマ」の花です、花は綺麗に咲いていますが葉が動物に食べられてい寂しい花になっています。
未だ冬景色かな?、と思って行った樹木公園には少しずつ春が近付いてきていました、もう暫くで染井吉野の花が樹木公園を埋め尽くすことでしょう、その頃には必ずお花見に行きます。
御訪問ありがとうございます。
(コメント欄は閉じさせていただいています)