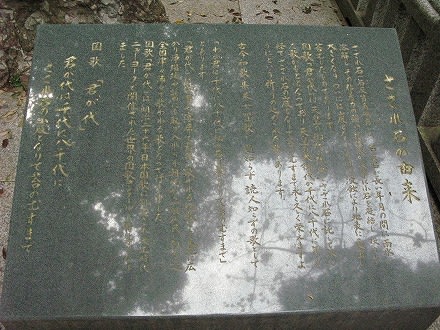DXを肴にして語る会が散会したあと、帰路を同行のTさんと共に世界遺産 白神山地の北側を通って日本海に抜ける「白神ライン」から秋田へのルートを通る事にした。大鰐町から一旦弘前市内を通って、県道28号線に入り、西目屋村から白神ラインに入ることになる。

折しも弘前市内では何かのイベントをやっているらしく、小さな渋滞が有った。そしてその先で見たのは、ここでも「よさこい」踊りだった。

弘前城追手門、実は弘前城は前日ホテルに入る前に時間が有ったので散策して置いたのだ。

お城の本丸天守は、復元ではなく昔の建物が残されていてその立派な姿に感服した。

県道28号に入り、可成りな道程を進むと西目屋村に辿り着く。岩木川の橋を渡っていたら川下で何やら賑やかな騒ぎ、どうやらカヌー大会らしい。

看板を見て納得、少し休憩を含めて観戦させて頂いた。

国体などの競技をテレビで見た事は有ったが実物を見るのは初めてだ。

ここは川幅が狭いが結構な急流が有ったりで、選手も真剣にパドルを操っている姿は見応えがあった。

更に岩木川を遡るとやがて美山湖、「白神ライン」の起点はこの辺りらしい。白神ラインは、延長約60キロメートル、美山湖を過ぎて間もなく「アクアグリーンビレッジANMON」までは舗装されているが、ここから先40Km以上は未舗装のダートだった。

途中には幾つもの峠があって、曲がりくねった上り下りが続いた。

ここは、赤石川の中流域を渡る橋のたもとに小さな駐車エリアだ。プナの森を散策するトレッキングコースが有るらしい。何台かの車が駐まっていた。 地図を見ると少し上流に赤石ダムがある様だ。赤石川は尺イワナが渓流釣り師の夢に出てくる秘境中の秘境なのだ。

あまりにも峠が多くて、幾つの峠を越えたのか記憶が曖昧になってしまった。

猿、野ウサギ、他には沢山の野鳥、などなど、突然目の前に表れて、こちらの存在にビックリして姿を消す。

時々、舗装路が表れる。「あぁ、これから先は舗装路?」思いがよぎった途端に再びダートになる。その繰り返しだ。

そして、看板の距離表示を見て、この峠が最後らしい。やがて道が穏やかな傾斜になり、周囲になにか人の臭いが感じられる所まで来て、やがて舗装路になった。そして深浦の町に差し掛かり、国道101号に出た時にはホッとした。「飯にありつける」昼も過ぎてすっかり腹が空いてしまった。

国道を暫く走っても食堂は無く、秋田県境まで来てしまった。ここからは秋田県だ。

後ろを振り返って見れば当然ながら青森県。

更に暫く進んだところに「道の駅 はちもり」があった。やっと飯にありつけた。空腹にイカ定食はご馳走だった。 ここを出たら間もなく雨が降り出した。天気予報は見事に当たりだ。雨の中を黙々と走り続けた。

「入道崎灯台」、男鹿半島の突端に位置する。
実は、ここが今日の目的地だった。前から何度も来ようと思って、近くまで来て、工事で通行止めだったり、何かの理由で一度も来られなかった所だ。 入道崎灯台には、海上保安庁の気象通報局(1669KHz)がある。釣りに出ると何時も聞いている幾つかの気象通報局を何時しか機会があったら尋ねて見たいと思う様になった。これまでに足摺岬、潮岬、野島崎、犬吠埼、鹿島、等々幾つかの気象通報局の併設された灯台を訪れてきた。今回入道崎を見て一つ目的を果たした。次は何処に行けるか楽しみだ。

残念ながら雨の中で、周囲の散策も出来ず、カメラに納めて帰路に就いた。ここからは、一番近い秋田道「昭和男鹿IC」までR101を走って、真っ直ぐ高速へ、一目山に雨の高速をすっ飛ばして我が家へ・・旅は終わった。帰路の総里程約700Km
来年のDXを肴にして語る会は秋田だ。来年は入道崎の続きを走れるかと期待。