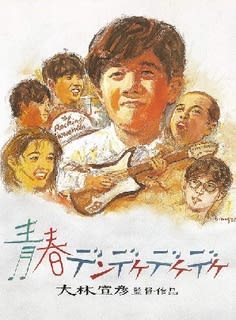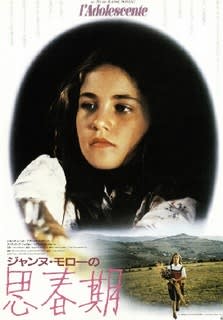(原題:LE JEUNE AHMED)ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督の視点は、相変わらず厳しい。思春期の危うさだけではなく、欧州全体を巻き込む移民問題や、イスラム原理主義の欺瞞性などのグローバルな課題をも見据え、結果84分の尺にまとめ上げた手腕は大したものだと思う。
ベルギーに暮らす13歳のアラブ移民の子アメッドは、つい最近までテレビゲームにハマっていたが、近所に住む“導師”と呼ばれるイスラム原理主義を唱える男と知り合いになってからは、イスラム教の聖典コーランに夢中になる。“大人のムスリムは女性を避ける”との教えを盲信し、放課後クラスのイネス先生との握手を拒み、父が出て行った後に酒の量が増えた母親を罵倒する。
そんなある日、イネス先生は歌を通じてアラビア語を学ぶ授業を提案するが、アメッドは激しく反対する。“聖なる言葉であるアラビア語はコーランで学ぶべきで、歌で学ぼうというのは神に対する冒とくだ”というのだ。そのいきさつを“導師”に話すと、“導師”はイネス先生を“背教者”と名指しすると共に、アメッドにジハードの実行を促す。アメッドはイネス先生のアパートを訪ね、ナイフを振りかざして襲おうとするが失敗。警察に自首し少年院に入れられたアメッドだが、イスラム教を理解し何とか更生させようとする少年院のスタッフの思いとは裏腹に、彼はイネス先生への殺意を捨てきれない。
本作の設定は先日観た「もみの家」と似ているとも言えるが、やはり宗教の邪な面に触れてしまった若者の社会復帰は難しい。アメッドは少年院が主催する農業奉仕活動に参加し、農場の娘に好かれたりもするが、ジハードに対するの執着は捨てられない。彼は農場の洗面所で歯ブラシを盗み、独房で柄の部分を鋭く尖らせる。このあたりの描写は強烈で、宗教の衣をまとった洗脳システムの恐ろしさを強く印象付けられる。
また、普段あれほど偉そうなことを言いながら、アメッドが検挙されると速攻で行方をくらましてしまう“導師”の胡散臭さを通して、原理主義の底の浅さを描くのも忘れない。ひょっとするとイスラム教徒からは異論の出る作品なのかもしれないが、ヨーロッパの状況は綺麗事など受け付けないほどに切迫しているのだろう。
ダルデンヌ兄弟の演出はストイックで力強い。急展開して活劇風のテイストを醸し出す終盤まで、観る者を惹き付ける。アメッド役のイディル・ベン・アディをはじめキャストは馴染みは無いが、それぞれ良い仕事をしている。そして、ラストに流れるシューベルトのピアノソナタが大きな効果を上げている。