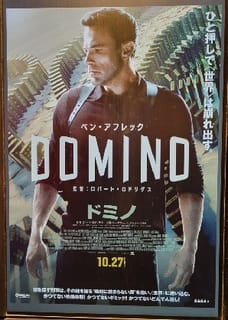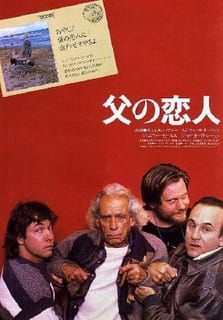(原題:EXTRACTION Ⅱ )2023年6月よりNetflixより配信された活劇編。前作(2020年)のラストでどう見ても主人公は助からないと思っていたが、この続編では冒頭に奇跡的に一命を取り留めて、過酷なリハビリの後“現場”に復帰する。パート1の評判の良さを受けて作られたシャシンだが、正直言ってドラマの組み立ては前回ほどではない。だが、主人公たちが程度を知らない大暴れを始めると、けっこう盛り上がるのだ。あまり難しいことは考えずに対峙するのが得策だろう。
オーストラリア人の傭兵タイラー・レイクの新たな任務は、ジョージアの残忍なギャングの家族が刑務所に監禁されているので、それを救うことだ。早速タイラーは仲間たちと共に東欧にある刑務所を急襲し、大々的な銃撃戦の末にその家族を救出してオーストリアのウィーンまで行き着く。ところがそのギャングに心酔する十代の息子の密告により、悪者どもは大挙してウィーンまで押し寄せてくる。
そのギャングの一味とタイラーは過去に確執があったらしいが、ハッキリとは描かれていない。また、たとえ言及されていたとしても大した扱いは期待できないだろう。前回に引き続き、タイラーの内面は詳しく描かれていない。彼の仲間の正体も不明だ。この映画は徹底してアクション描写に特化した作りになっており、一種のアトラクションと言って良いと思う。
カメラをほとんど切り替えない臨場感溢れる戦闘シーンにはやはり身を乗り出して観てしまうし、後半のウィーン市街地での死闘は活劇の段取りが実に上手く考えられている。例によって相手方の放った銃弾はなかなか当たらないが、タイラーたちの攻撃はことごとくヒットする。このあたりの御都合主義は“お約束”なので野暮は言うまい(笑)。それにしても、東欧のヤクザどもはシシリアン・マフィアなどと同じく血脈や義理を重視する傾向にあるのは興味深い。もちろん土壇場では欲得に走ってしまうのだが、このファミリー的な体裁がくだんの家族の長男がタイラー側に容易に与しない理由でもある。
連続登板になるサム・ハーグレイブ監督の仕事ぶりは相変わらずパワフル。無理が通れば道理は引っ込むとばかりに、ひたすらに力で押し込んでくる。この割り切り方もアリかもしれない。主役のクリス・ヘムズワースとパートナー役のゴルシフテ・ファラハニは好調で、ほぼ不死身な存在でありながらそれなりに傷付いているのは、けっこう観ていて身が切られる思いがする。
トルニケ・ゴグリキアーニにアダム・ベッサ、ダニエル・バーンハード、イドリス・エルバら脇の面子も悪くないし、オルガ・キュリレンコとティナティン・ダラキシュヴィリの女性陣も画面に色を添える。ラストは次作もあることが示されるが、公開されればやっぱりチェックするだろう。