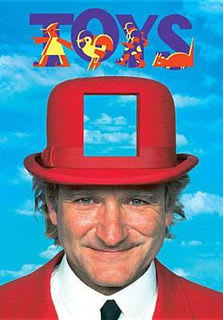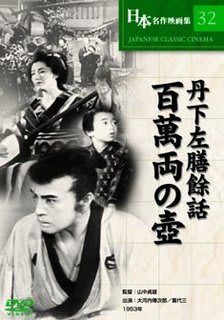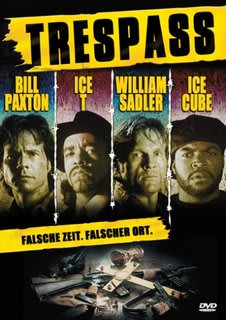(原題:TULLY )確かに主演女優の奮闘は大いに評価出来るが、話自体はどうしようもなく、観終わって釈然としない気持ちばかりが残った。ただ、上映時間が約1時間半と短めであることは有り難い。この題材で2時間以上も引っ張ってもらっては、徒労感は増したことだろう。
ニューヨークの郊外に住む主婦マーロは、仕事や家事を何とかこなしてきたが、3人目の子供が生まれてついに頑張りも限界に達してしまう。しかも、夫は家庭をあまり顧みない。見かねた兄は、夜だけのベビーシッターを雇うことを提案する。マーロの元に派遣されたのは、若い女タリーだった。彼女は外見と喋り方こそ今風だったが、仕事は完璧にこなし、マーロの話し相手にもなってくれる。タリーのおかげでマーロは次第に元気になっていくが、実はタリーにはある“秘密”があった。
勘の良い観客ならば、タリーの“正体”に中盤あたりで気付くだろう。何しろ、彼女は夜明け前には必ず帰って行くし、マーロ以外と会うことはほとんど無いのだ。しかし、終盤でその“正体”が明かされると、それまでの展開にまったく筋が通らなくなる。
どうしてマーロが元の輝きを取り戻していったのか説明出来ないし、兄がベビーシッターの費用を負担しているという事実が宙に浮いてしまう。さらに2人が夜中にニューヨークの歓楽街に遊びに行くエピソードも、説得力に欠けるものになる。
また、長男が問題行動ばかり引き起こしてマーロや学校当局を困らせたり、ダンナがベッドで彼女を無視してテレビゲームに興じている様子は、観ていて不愉快だ。ラストは一応決着させたつもりなのだろうが、よく考えてみると全然解決していない。“家庭の問題は夫婦で何とかしましょう”という、紋切り型の言い分を差し出されているようで、脱力するばかりである。
ジェイソン・ライトマンの演出は可も無く不可も無し。だが、主演のシャーリーズ・セロンは凄く頑張っている。「モンスター」(2003年)での肉体改造を上回る、20kgもの増量。生活に疲れた女を生々しく演じている。すでに中年に達している彼女にとって、この役作りは相当にハードだったと思われるが、その努力には頭が下がる。ただし、他のキャストはタリー役のマッケンジー・デイヴィスが印象に残る程度で、あとは大したことがない。
なお、エリック・スティールバーグのカメラによる映像は透明感がある。ロブ・シモンセンによる音楽は悪くなかったが、それよりも既成曲の使い方が上手かった(シンディ・ローパーのナンバーや、「007は二度死ぬ」のテーマ曲など)。