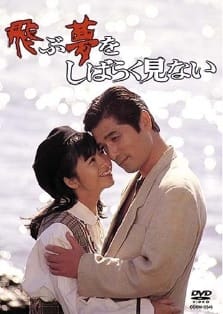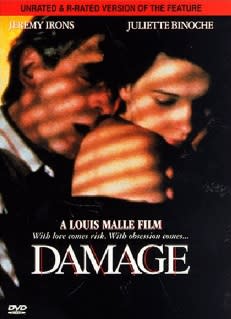楽しく観ることができた。もっとも、軽佻浮薄なエクステリアに対して拒否反応を示す観客も多いと思うので、幅広くは奨められない。だが、背後にある作者の確固たる視点と主張には共感する。オフビートかつシリアスな青春映画として評価したい。
夜ごと遊び回る大学生を中心としたグループに、チワワと名乗る若い女が突然強引に参加する。彼女はその吹っ切れた言動で、たちまちグループ内のマスコット的存在になる。ある晩、政治家への闇献金の600万円を持ったままクラブに来店したゼネコン幹部から、チワワは金を強奪しようとする。派手な追いかけっこの末に金を手に入れたグループの面々は、その金で熱海まで繰り出して豪遊する。
だが、金が底をつき、彼らは日常に戻ると、以前のように頻繁に会うことは無くなった。そんなある日、チワワがバラバラ遺体となって東京湾で発見されるというニュースが流れる。残りのメンバー達はそれぞれが彼女との思い出を語るのだが、気が付いてみると、誰もチワワの本名や境遇を知らないのだった。岡崎京子が94年に発表した短編コミック(私は未読)の映画化である。
映画はメンバーの一人であるミキが、チワワの死後に狂言回し的な役どころで他の連中にチワワとの関係を聞き出していくという形式で進む。彼らの話の中から浮き上がってくるチワワ像は、とにかく“完璧”に近いということだ。
ルックスはもとより、かなりの芸達者。グループに加入する前も、メンバーと疎遠になった後も、芸能界にしっかりとコミットし、モデルや歌手としてのオファーが絶えない。表情や仕草はキュートで、無鉄砲な振る舞いも、実に絵になる。しかも気取ったところが無く、料理の腕は一流だ。言うなればこれは、ミキ達(および作者)の考える“若さ”のメタファーであろう。
若さは免罪符であり、若ければ誰でもチワワのように無敵で万能。先のことなど考える必要は無い。しかし、いつかは時間と経験が積み重なり、若さは消えていく。その厳しい現実に、儚く去っていったチワワの姿を重ね合わせるとき、切ない感慨が湧き上がってくる。
二宮健の演出は極彩色の画面をバックに、うねるようなグルーヴを伴って展開する。ヘタすれば悪趣味に終わるところだが、まるで違和感を覚えない。これは一種の才能だろう。キャストの中ではミキを演じる門脇麦が光る。さすがの演技力で、彼女が映画の中心にいる限り、破綻することは無いと思わせる。
成田凌や寛一郎、玉城ティナ、村上虹郎、松本穂香、栗山千明など、他の面子も良好。浅野忠信が相変わらずの変態ぶりを見せつけているのも嬉しい(笑)。そして本作の一番の収穫は、チワワに扮する吉田志織である。外見は可愛いが、その裏にある狂気性を醸し出し、まさに圧巻。今年度の新人賞の有力候補だ。