90年作品。この映画は何と、大手総合商社の一つであったトーメンが製作している。思い起こせば80年代から90年代初頭にかけて、映画作りとは縁の無いようなカタギの(?)企業が次々と映画業界に参入していたものだ。当時は景気が良かったのでそんなケースは珍しくもなかったのだが、今考えると随分と賑やかな話である。現在ではまずあり得ないだろう。
1858年、江戸幕府は日米通商条約を結び、長らく続いた閉鎖的な外交体制は終わりを告げた。上野国出身の商人である中居屋重兵衛は、商売の傍ら佐久間象山の弟子になり、あらゆる学問を学ぶ。彼はいつか世界を相手に商売をしたいと思っていた。やがて重兵衛は横浜に進出し、外国商館に引けを取らない豪壮な館を建築する。
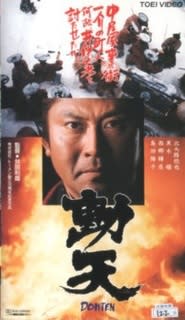
そんな時、便宜を図っていた外国奉行の岩瀬肥後守が幕府の政策を批判したためにリストラされ、家禄没収の処分を受ける。さらに重兵衛も、贅沢すぎる銅瓦で館の屋根を茸いたことによって当局側からマークされる始末。それでも盟友の勝海舟と世界進出の夢を語る重兵衛であったが、幕府による横浜への弾圧は益々厳しくなる。1860年、意を決した重兵衛は水戸烈士たちを陰から支援し、井伊大老を襲撃する計画を立てる。
商社の製作による映画であるせいか、主人公の重兵衛を一介の商人ではなく何やらオールマイティなヒーローに仕立て上げているのには苦笑する。大仰に見得を切ってチャンバラ映画の主人公よろしく振る舞う様子は、まるで往年の東映時代劇の世界である。
さらには、活劇場面を連発することによって強引な筋書きの欠点を糊塗しようというスタンスは、昔の日活アクションばりだ。そういえば監督の舛田利雄は“日活の舛田天皇”と呼ばれていたほど、このジャンルに精通している。
だが、製作された時点を勘案しても、この映画は現在に通じるものが無い。骨太なテーマ性は不在で、単にビジネスマンである主人公の利害を追認しているだけだ。この企画は東映京都撮影所にも舛田利雄にも金銭的な恩恵をもたらしたと思うが、スポンサー及びその業界をヨイショするための仕事なので、あまり気が乗っていなかったと思われる。観た後は実に印象が薄いのも、そのためだろう。
主演の北大路欣也をはじめ、黒木瞳、島田陽子、西郷輝彦、高橋悦史、江守徹など配役は豪華。さらに音楽は池辺晋一郎で谷村新司が主題歌を提供しているという、大盤振る舞いだ。しかしバブル後はトーメンは次第に勢いを無くし、ついには豊田通商に吸収合併されてしまう。時の流れを感じずにはいられない。
1858年、江戸幕府は日米通商条約を結び、長らく続いた閉鎖的な外交体制は終わりを告げた。上野国出身の商人である中居屋重兵衛は、商売の傍ら佐久間象山の弟子になり、あらゆる学問を学ぶ。彼はいつか世界を相手に商売をしたいと思っていた。やがて重兵衛は横浜に進出し、外国商館に引けを取らない豪壮な館を建築する。
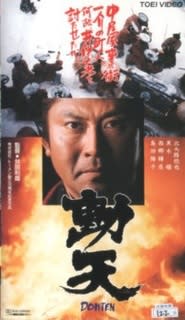
そんな時、便宜を図っていた外国奉行の岩瀬肥後守が幕府の政策を批判したためにリストラされ、家禄没収の処分を受ける。さらに重兵衛も、贅沢すぎる銅瓦で館の屋根を茸いたことによって当局側からマークされる始末。それでも盟友の勝海舟と世界進出の夢を語る重兵衛であったが、幕府による横浜への弾圧は益々厳しくなる。1860年、意を決した重兵衛は水戸烈士たちを陰から支援し、井伊大老を襲撃する計画を立てる。
商社の製作による映画であるせいか、主人公の重兵衛を一介の商人ではなく何やらオールマイティなヒーローに仕立て上げているのには苦笑する。大仰に見得を切ってチャンバラ映画の主人公よろしく振る舞う様子は、まるで往年の東映時代劇の世界である。
さらには、活劇場面を連発することによって強引な筋書きの欠点を糊塗しようというスタンスは、昔の日活アクションばりだ。そういえば監督の舛田利雄は“日活の舛田天皇”と呼ばれていたほど、このジャンルに精通している。
だが、製作された時点を勘案しても、この映画は現在に通じるものが無い。骨太なテーマ性は不在で、単にビジネスマンである主人公の利害を追認しているだけだ。この企画は東映京都撮影所にも舛田利雄にも金銭的な恩恵をもたらしたと思うが、スポンサー及びその業界をヨイショするための仕事なので、あまり気が乗っていなかったと思われる。観た後は実に印象が薄いのも、そのためだろう。
主演の北大路欣也をはじめ、黒木瞳、島田陽子、西郷輝彦、高橋悦史、江守徹など配役は豪華。さらに音楽は池辺晋一郎で谷村新司が主題歌を提供しているという、大盤振る舞いだ。しかしバブル後はトーメンは次第に勢いを無くし、ついには豊田通商に吸収合併されてしまう。時の流れを感じずにはいられない。
























