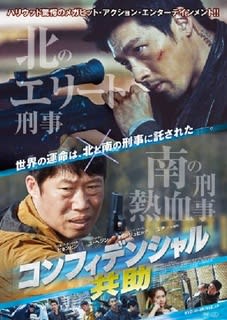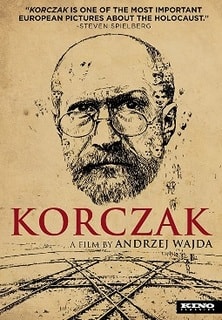監督の山崎エマはニューヨークを拠点に活動する映像作家で、彼女が海外向けに日本の高校野球を紹介するために作ったドキュメンタリーである。その意図はほぼ達成されているが、深くは掘り下げられていない。しかし、この場合はそれがさほど欠点にはなっていないと思う。それどころか、考えるヒントを見出せることは認めて良い。
本作の“主人公”は、全国有数の激戦地である神奈川県の横浜隼人高校の水谷哲也監督だ。100人以上の部員を擁し、全員を専用寮に入れて公私ともに面倒を見ている。彼は野球を人間的成長の手段だと思っており、事あるごとに部員にそのことを強調する。映画は彼と横浜隼人高校野球部を一年に渡って追い続け、その間に夏の甲子園第100回記念大会へ挑むための地方予選の様子も描かれる。
水谷監督の“弟子”に当たるのが、花巻東高校の佐々木洋監督だ。言うまでもなく大谷翔平や菊池雄星といった逸材を育てた指導者だが、すでにその業績は水谷監督を凌駕しているあたりが面白い。この2つのチームを中心に、日本の高校野球とはアメリカから輸入されたベースボールではなく、“野球道”というべきものに進化し、単なるスポーツを超えた特別なものであることが示される。
ただ、佐々木監督が劇中で言うように、高校野球は守るべきものはたくさんあるが、変えなければならない点も多々あるのだ。花巻東高校の野球部は新年度から坊主頭を廃止するらしいが、それはその第一歩であろう。
とはいえ、いわゆる野球留学は目に余り、地元出身の選手が一人もいないチームもある。本作で描かれる2つの野球部も越境入学は当たり前で、練習試合や合宿のために遠隔地に出掛けられる余裕があり、とても“普通の”環境ではない。そして部員が多いということは、ほとんどの選手が補欠で終わることを意味する。水谷監督はそこを“人間形成にレギュラーも補欠も関係ない”とフォローはするのだが、普通に考えれば大会に出られないのではクラブ活動をやっている意味は無いと思う。
そして、水谷監督も佐々木監督も有能ではあるのだが、世の中にはいまだに根性論や体罰が罷り通る運動部が存在していることは確かだ。そのことを考えると、やるせない気分になる。あと関係ないが、甲子園球場が大阪府にあるという表示は間違いだ。いまひとつ情報の精査が必要である。そして横浜隼人高校のユニフォームが阪神タイガースとそっくりなのには笑ってしまった。水谷監督は大の猛虎ファンらしい。