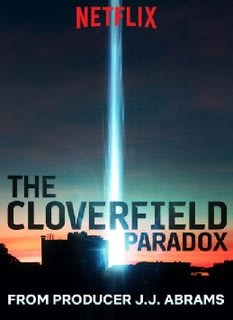(原題:Kolya )96年チェコ=イギリス=フランス合作。同年のアカデミー外国語映画賞をはじめ、第9回東京国際映画祭グランプリ、97年ゴールデン・グローブ賞外国語映画賞など多くのアワードを獲得した作品だが、実際観てみると薄味でインパクトは小さい。しかしながら丁寧には作ってあり、決して駄作でも凡作でもなく、存在価値があることは確かだ。
88年のプラハ。フランティ・ロウカは昔はチェコ・フィルの首席奏者まで務めた名チェリストだったが、女性関係で身を持ち崩し、気が付けば50歳過ぎて独身で、今では葬儀場で演奏するなどして糊口を凌いでいた。ある日、友人のブロスが彼に、チェコ人としての身分証明書が欲しいロシア女ナディズダとの偽装結婚を持ちかけた。けっこうな額の礼金にひかれ承諾したフランティだが、ナディズダは結婚式の直後に5歳の連れ子コーリャを置いたまま恋人のもとに遁走してしまう。
金は手に入ったが、思いがけず子供の世話をするハメになったフランティは、ロシア人嫌いの母親からは邪険に扱われ、当局から呼び出しを食らうなど災難続き。それでもコーリャと一緒に暮らしていると、何となく父親らしく振る舞うようになってしまう。そんな中、ベルリンの壁が崩壊してプラハでも民主化運動が高まり、フランティの周囲は慌ただしくなる。
監督のヤン・スベラークはじっくりと撮っているのは分かるのだが、ドラマとしては盛り上がりに欠ける。フランティはチェロを運搬するための車を欲しがっていたようだが、そこに執着しているような描写は見られない。偽装結婚に加担したのもそれが大きな要因だが、そこはもっとケレンを効かせた扱いが望ましい。
後半、フランティはコーリャにヴァイオリンを買い与えるのだが、ここもサラリと流し過ぎだ。いくらでも感動的になりそうなモチーフながら、大きな仕掛けは見られない。終盤に至っては駆け足で撮ったという印象で、印象が希薄のままエンドマークを迎えたような感じだ。
しかし、この時代の空気感や風俗がよく出ているのは評価して良い。長らく東側特有の暗鬱な空気に包まれたこの国が、冷戦終結によってようやく明るい兆しが出てきたのも束の間、チェコとスロヴァキアに分裂してしまうという先の見えない状況に陥る。フランティら住人たちも戸惑うが、そこはストーリーをいたずらに悲劇に向かわせないのは冷静な判断かと思う。
主演のズディニェク・スベラークをはじめ、子役のアンドレイ・ハリモン、リブシェ・シャフラーンコバ、イリーナ・リヴァノヴァといったキャストは皆公演だ。また、往年の名指揮者ラファエル・クーベリックが本人役で出ているのも嬉しい。