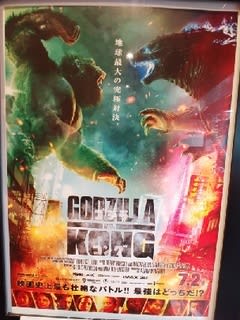今年度の日本映画を代表する青春映画の快作だ。とことん前向きなストーリーに、それに対して違和感をまったく覚えない作劇の妙。厳選されたモチーフの数々と、屹立した登場人物たちの大盤振る舞い。そして何より、映画の背景になっているのは夏の眩しい陽光だ。明朗な青春ものの御膳立ては完璧に整えられ、先日観た「サマーフィルムにのって」のような、夏を題材にしていながら全然夏っぽくない低調なシャシンとは完全に差を付ける。
地方都市の高校に通う朔田美波は水泳部に属しているが、弱小チームで大会では成果を出せない。彼女はTVアニメ「魔法左官少女バッファローKOTEKO」の大ファンだが、ある日校舎の屋上でKOTEKOのイラストを墨で描いている男子生徒を発見し、思わず声を掛ける。彼は同学年の門司昭平で、もちろん件のTVアニメにハマっている。
すっかり昭平と意気投合した美波が彼の家で見つけたのは、彼女の実父(母親は再婚している)から送られてきた謎の御札とそっくりなシロモノだった。その御札は新興宗教団体が発行しており、実父はどうやらそこの教祖らしい。美波は幼い頃に行方が分からなくなった父親に会いたくなり、昭平の兄で自称・探偵の明大の助けを得て、実父の藁谷友充の居場所を突き止める。田島列島による同名コミックの映画化だ。
とにかく、ヒロイン美波の明朗なキャラクターに圧倒されてしまう。頑張る時には辛そうな表情をせずに笑ってしまうという得な性格。大会では活躍出来ないが、殊更に思い悩むこともなく、好きなことに対しては一直線だ。普段なら“そんな明るさ一辺倒の女子高生なんかいるわけがない”と突っ込むところだが、本作ではそれが説得力を持つようにドラマの背景が巧妙にセッティングされている。
それはつまり、出てくる人間がすべてポジティヴなスタンスを持っているということだ。全員が自分の人生を受け入れている。いろいろ不満もあるだろうが、これが今の自分なのだと割り切り、どうやればよりマシな明日を生きられるかを考える。それは絵空事だと批判することは容易いが、本来はこういう肯定性・楽天性こそが人生の本質なのではないかという、作者の主張が見て取れる。
沖田修一の演出は闊達そのもので、ギャグの繰り出し方も万全。主演の上白石萌歌を初めてスクリーン上で見たが、姉の上白石萌音よりもスポーティーでしなやかな肢体が印象付けられる、なかなかの素材である。表情も実に豊かだ。昭平役の細田佳央太も悪くないが、明大に扮した千葉雄大がケッ作で、これは彼の新境地と言えそう。
古舘寛治に斉藤由貴、子役の中島琴音なども見せ場はたっぷりだが、何と言っても友充を演じる豊川悦司が素晴らしい。相変わらずの変態ながら(笑)、突如現れた実の娘に戸惑いながらも関係性を見出そうとする役柄を、うまく引き受けていた。芦澤明子のカメラによる夏の情景をバックに、ラストのラブコメ的な決着の付け方と絶妙のエピローグに、観ていて思わず表情が緩んでしまった。これはオススメの映画だ。