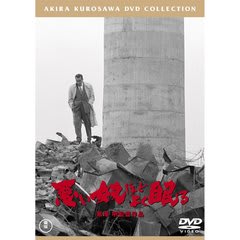(原題:Wonder Boys )99年作品。カーティス・ハンソン監督が本作の前に撮った快作「L.A.コンフィデンシャル」の好調ぶりがここでも持続しているようで、一時たりとも退屈させない上出来のドラマに仕上げられている。
ペンシルヴェニア州の地方都市にある大学で教鞭を執る文学部教授のグレイディは、若い頃は文壇の風雲児として知らぬ者はいなかったほどの存在だったが、今は長いスランプから抜け出せず、7年前から書き始めた大長編小説も完成する気配がない。折も折、妻は家を出て行き、しかも不倫相手の学長夫人サラから妊娠を告げられてしまう。さらには新作を催促する編集者テリーもやってくる始末。
そんな中、テリーとパーティに出かけたグレイディは、教え子のジェームズが巻き起こした(学長がらみの)大きなトラブルに遭遇する。何とか場を収めようと右往左往する彼らだが、やがてジェームズがかつてのグレイディのような天才ライターであることを知るようになる。
さすがこの監督は“大人”である。インテリ人種の織りなす屈折した騒動の数々を、見事に抑制された語り口とスムーズな展開で見せきっている。複数のクセの強い登場人物をムラなくフォローし、それぞれのハッピーエンドを迎えるまで少しも描写力を緩めない演出の粘りには感服した。
人生の転機は、見つけようと思えばいつでもどこでも探し当てられるものだというポジティヴな視点を、決して大仰にならずにソフィスティケートなタッチで提示する。その絶妙なさじ加減には舌を巻くばかりだ。
主演のマイケル・ダグラスは、マジメくさった顔をしてシッカリと笑いを取っていく妙演。昔は一世を風靡したが、オッサンになって才能が枯れた今は身の振り方も掴めないダメ男ぶりが絶品だ。ジェームズ役のトビー・マグワイア、テリーに扮したロバート・ダウニー Jr.、サラ役のフランシス・マクドーマンドと、脇も芸達者が揃っている。ダンテ・スピノッティのカメラも素晴らしく、これはこの時期を代表するアメリカ映画の収穫と言えそうだ。