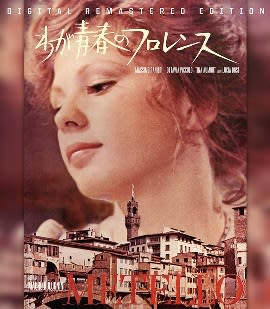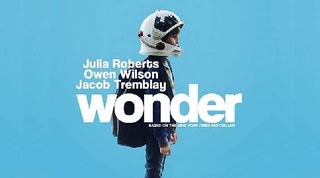明らかな失敗作だ。何より、このネタで上映時間が2時間13分もあるというのは、絶対に無理筋である。余計なシーンが山ほどあり、素人目で見ても30分は削れる。さらにメインプロットは陳腐だし、演出テンポは悪いし、キャスティングに至っては呆れるしかない。プロデューサーはいったい何をやっていたのかと、文句の一つも言いたくなる。
都内の大手企業に勤める黒田みつ子は、何年も恋人がおらず、気が付けば31歳で独り暮らしだ。しかし彼女は今の生活に満足している。なぜなら、みつ子は脳内に“A”という相談役みたいな人格を作り出し、話し相手になると共に的確なアドバイスを捻りだしてくれるからだ。
ある日、みつ子は取引先の若手営業マンである多田に恋心を抱く。しかも多田はみつ子の近所に住んでいるのだ。ところが彼女は恋愛に御無沙汰で、しかも相手は年下ときているから、なかなか一歩が踏み出せない。それでも“A”の励ましもあって、何とか前に進もうとする。綿矢りさの同名小説の、大九明子がメガホンを取っての映画化だ。
とにかく、みつ子が悶々と悩んでいるシーンが長いのには閉口する。架空人格の“A”との会話はあるのだが、それでも芸の無い一人芝居を長時間見せられるのは辛い。みつ子に扮するのは“のん”こと能年玲奈だが、彼女の演技は一本調子でメリハリが皆無だ。
承知の通り、能年は事務所関係のトラブルによって長い間演技の仕事が出来なかった。俳優にとって最も経験を積んでおかなければならなかった時期を、棒に振ってしまったわけだ。気が付くと同じ「あまちゃん」組でも松岡茉優や有村架純に大きく差をつけられている。特に同じ原作者で同じ監督の「勝手にふるえてろ」(2017年)での松岡の演技と比べると、その開きは明白だ。
さらに言えば、彼女はとても役柄の30歳過ぎには見えないし、多田に扮する林遣都の方が能年より年上である。みつ子の同級の親友である皐月を演じる橋本愛に至っては、まだ20歳代前半だ。まったくもって、このいい加減な配役には呆れるばかり。
皐月に会うためにみつ子がわざわざイタリアまで足を運ぶシークエンスや、東京タワーで先輩のノゾミが好意を寄せている男に告白するの何だのといったくだりは、明らかに不要であり無駄に上映時間を積み上げるだけ。終盤の、みつ子と多田のアヴァンチュール(?)の場面も極めて冗長だ。みつ子が飛行機恐怖症だというモチーフも、何ら有効に機能していない。
大九監督の仕事ぶりには覇気が見られず、「勝手にふるえてろ」のような思い切った仕掛けも無い。臼田あさ美に若林拓也、前野朋哉、山田真歩、片桐はいりなどの脇の面子もパッとしない。わずかに良かったのは“A”の声を担当する中村倫也と、女芸人の吉住ぐらいだ。バックに流れる大滝詠一の「君は天然色」が空しく響く。




都内の大手企業に勤める黒田みつ子は、何年も恋人がおらず、気が付けば31歳で独り暮らしだ。しかし彼女は今の生活に満足している。なぜなら、みつ子は脳内に“A”という相談役みたいな人格を作り出し、話し相手になると共に的確なアドバイスを捻りだしてくれるからだ。
ある日、みつ子は取引先の若手営業マンである多田に恋心を抱く。しかも多田はみつ子の近所に住んでいるのだ。ところが彼女は恋愛に御無沙汰で、しかも相手は年下ときているから、なかなか一歩が踏み出せない。それでも“A”の励ましもあって、何とか前に進もうとする。綿矢りさの同名小説の、大九明子がメガホンを取っての映画化だ。
とにかく、みつ子が悶々と悩んでいるシーンが長いのには閉口する。架空人格の“A”との会話はあるのだが、それでも芸の無い一人芝居を長時間見せられるのは辛い。みつ子に扮するのは“のん”こと能年玲奈だが、彼女の演技は一本調子でメリハリが皆無だ。
承知の通り、能年は事務所関係のトラブルによって長い間演技の仕事が出来なかった。俳優にとって最も経験を積んでおかなければならなかった時期を、棒に振ってしまったわけだ。気が付くと同じ「あまちゃん」組でも松岡茉優や有村架純に大きく差をつけられている。特に同じ原作者で同じ監督の「勝手にふるえてろ」(2017年)での松岡の演技と比べると、その開きは明白だ。
さらに言えば、彼女はとても役柄の30歳過ぎには見えないし、多田に扮する林遣都の方が能年より年上である。みつ子の同級の親友である皐月を演じる橋本愛に至っては、まだ20歳代前半だ。まったくもって、このいい加減な配役には呆れるばかり。
皐月に会うためにみつ子がわざわざイタリアまで足を運ぶシークエンスや、東京タワーで先輩のノゾミが好意を寄せている男に告白するの何だのといったくだりは、明らかに不要であり無駄に上映時間を積み上げるだけ。終盤の、みつ子と多田のアヴァンチュール(?)の場面も極めて冗長だ。みつ子が飛行機恐怖症だというモチーフも、何ら有効に機能していない。
大九監督の仕事ぶりには覇気が見られず、「勝手にふるえてろ」のような思い切った仕掛けも無い。臼田あさ美に若林拓也、前野朋哉、山田真歩、片桐はいりなどの脇の面子もパッとしない。わずかに良かったのは“A”の声を担当する中村倫也と、女芸人の吉住ぐらいだ。バックに流れる大滝詠一の「君は天然色」が空しく響く。