「雷声」の意味をWEB辞書で調べると(1)かみなりの音。雷鳴。(2)かみなりのように大きな音や声。別の辞書には(3)かみなり声:雷鳴のようにあたりに響き渡る大声ともある。
こんなことを調べたのは「ことばの歳時記」の「上洛」の項に「雷声」の同音異義語のことを金田一先生が書いていたからだ。
静岡市から講演を依頼された先生。約束の日を待っていたら、電報がきて(時代を感じる)その文面に「二ヒゴライセイヲコウ」とあった。自分の講演を御雷声とはけったいな敬語をつかうなと勝手に感心し、それにしても約束の日は三日ではなかったか、一日繰り上がったのかしらんと思いながら、二日に出かけたのだそうだ。
そうしたら、なんと講演はやっぱり三日の予定で、ゴライセイとは「御来静」、つまり静岡へ来いという意味だと判ったのだとか。たぶん、静岡市の担当者は大先生に平身低頭で謝ったはずだが、その結末については触れられていない。
「来静」という成語は土地の人間にとっては聞きなれたごく親しいことばなのだろうが、他所の人たちにとっては、思いもつかないことばともなる。
国語学者で、方言地理学や社会言語学の研究で知られた柴田武はこうしたごとばを採集していたそうで、それによると往来表現では、名古屋へ来るのは「来名」(これも誰かに雷鳴と間違われそうだ)、大阪は「来阪」というように、上下の一文字をとって漢字の熟語をつくるというのが原則だというが、京都のように「上洛」という全然違った文字をもってくる場合もある、と、ここで項のタイトルになった「上洛」がでてくるわけだ。
上洛というと、思い出すのはやはり織田信長だろう。金田一先生もおなじらしい。足利将軍家の足利義昭から幕府再興の呼びかけを受けた信長は、稲葉山の戦いで斎藤氏を駆逐し尾張美濃を領する戦国大名として1568年10月に上洛し、京の三好氏を撃破して室町幕府の再興を果たすのだ。
上洛という語感はいかにも大時代的だが、上京としたのでは東京に行くのかと紛らわしい。さて、今の京都に来いという場合、京都人は何と表現しているのだろう。「ゴライキョウ」というのだろうか。どうも座りが悪そうだ。
最新の画像[もっと見る]











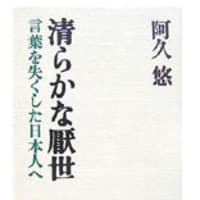






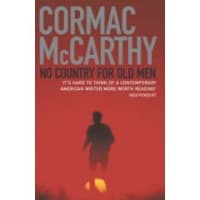
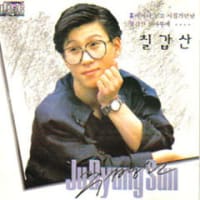
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます