4月17日。一日中強い雨が降った。コロナ情報は、全国で4799人(延531615人)の感染と37人(累9642人)の死亡が確認されている。このうち、愛知県では230人(延30021人)が感染と発表があった。感染者数3万人超えである。死者はなかった。
お互いファーストネームで呼び合おうという日米首脳会議が開催された。「ジョー」談は「ヨシ」にして両国の懸案のすべてが話し合われたと思いたい。
雨の中を金山から神宮前に向かって万歩。眼鏡が曇るからマスクは外した。対向する歩行者もほとんどいないから睨まれることはなかろう。
途中にある老舗茶舗の前には新茶のうす緑色の幟が雨に打たれていた。もうそろそろ茶摘みの季節になるわけだ。金田一春彦先生の「ことばの歳時記」、4月16日の項は「摘み草」である。
花を摘むこと、茶を摘むことは、「はなつみ」「ちゃつみ」なのに、若草を摘むことは「つみくさ」というのはこれいかに、というのが先生の話のポイントである。
日本語の順序なら目的語が動詞の先にくるはずだから「摘み草」ではルール違反になる。金田一説ではこうだ。
「摘み草」ということばは、もとは「草を摘む」という動作を表すことばではなく、「摘んだ草」という名詞的な意味だったのではないか。「花作り」が花を作ることであるのに対して、「作り花」は作った花のことだ。
本来が名詞のことばを動詞として「摘み草をする」というように使う人たちが出てきて、それによって「摘み草」ということばの今の使い方が出来上がった。「哲学する」「科学する」といった類の言い方は昔もあったのだという。
さっきまでお仲間の韓国人Jさんのブログを訳していたのだが、韓国にも「漢字語+ハダ」という日本語とまるで同じ名詞を動詞化する語法があるなあと思った。
「哲学する」「科学する」という日本語表現はちょっとくだけた口語的ニュアンスも感じられるが、韓国語の「哲学ハダ」「科学ハダ」はきわめて正統的な用法だ。韓国語の「ことばの歳時記」なぞはないものだろうか。きっと面白い筈だ。











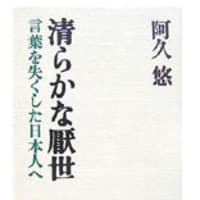






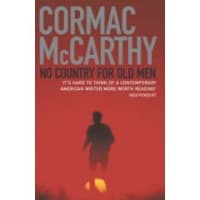
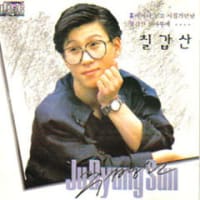
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます