6月11日のコロナ状況は、全国で1937人(延772590人)の感染と64人(累14503人)の死亡が確認された。愛知県では149人(延49656人)の感染と6人(累881人)の死亡の発表があった。
WHOが今月から主唱して使い始めたコロナウイルス変異株に対する命名(呼称)はギリシャ文字のアルファベット順となっている。発見地名をつけていた従来の命名法ではいろいろと偏見も起こるというのだが、これを最初に聞いて、トランプ前米大統領の「武漢ウイルス」という政治的な強調口調のことを思い出した。
新命名法だと、いわゆるイギリス株のB117系統が「アルファ」、南アフリカ株のB1351系統は「ベータ」、ブラジ株のP1系統は「ガンマ」、インド株のB16172系統は「デルタ」と呼ばれることになった。
ただ、考えてみると、感染症の学者ならともかく、一般大衆にとっては「無機的なアルファベットを使われれるよりも、地域呼称の方が理解がはやいし、緊張の度合もちがいそうだ。なにも国家差別や人種偏見があってのことではない。それが証拠に、これまでマスコミの報道はアルファベットと地名の双方を並記して(読みやすく)してくれている。
そんな変異株の増殖と跳梁が気になるところだが、今日の中日夕刊に「インド株の感染力1.8倍」というニュースを見つけた。
京大と北大のチームの推計によると「インド株はイギリス株よりも感染力が強く、従来のウイルスと比べて1.8倍に高まった」という結果が出た。インド株の感染者数は増加傾向にあり、7月上旬にも現在主流のイギリス株と逆転するという試算だ。
チームが計算した実効再生産数(一人の感染者が平均何人にウイルスをうつすか)によると、イギリス株は従来株の1.45倍だったが、インド株は1.8倍、イギリス株と比べても1.2倍高かった。
変異種の割合についての試算では、7月上旬にイギリス株とインド株との割合が入れ替わり、7月中旬にはインド株が半数を超えて、7月末には8割程度に達するという予測だ。
インド株の割合が増えれば感染スピードも上昇することになり、従来型が主流だった時と比べて拡大スピードが1.5倍になる可能性も出てきた。こうなると今は鎮静するかに見える国内の流行規模が再燃して、さらに大きなものに拡がる危険性を孕んでいるというのである。
アメリカCDCのファウチ博士がワクチン接種が進むアメリカ国内でも若者たちが狙われるインド株の急激な拡大に備えよと警告しているし、中国南部の広州では懸命の防疫作戦にもかからわず新規の感染者がジワジワとその数を伸ばしつつあるという。インド株の所為だとは報道されていないが、その疑いは大きいだろう。
中日の記事は最後までインド株で通したが(インドが怒ったとしても)これでいいのだろう。WHO式にデルタ株と言い替えたら、記事の緊張感が薄まってしまうような気がする。











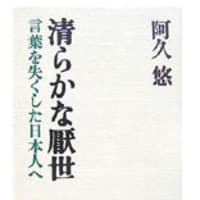






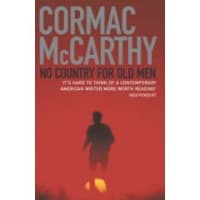
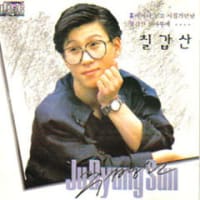
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます