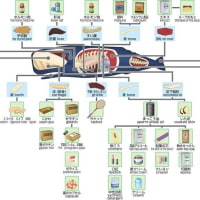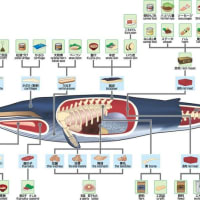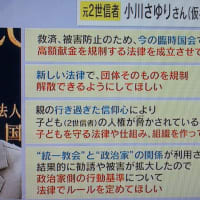3月24日(土):  *この表紙のカセット写真は、本作品中における重要なアイテムになっている!
*この表紙のカセット写真は、本作品中における重要なアイテムになっている!
439(450)ページ中、現在361ページ 所要時間4:40 図書館
著者51歳(1954生まれ)。 2017年ノーベル文学賞受賞(63歳)。
図書館の返却が迫っている。この週末に読むしかない。縁だけでも結ばせていただこうと、1ページ30秒を目安に読み始めた。実際には遅くなっているが、それでも俺としては速い方だ。細部を確認し、味わうわけにはいかないが、物語りの流れは大体理解できた。どちらかと言えば、読みやすい本である。
正確なのかは分からないが、翻訳の日本語が非常に慎ましやかで丁寧で優しい文章になっている。読んでいて心地よい感じである。読み続けていると、抑制的なシーンの背後に非常に大きな心の動き、やり取りが表現されていて、その細やかさに“はっ!?”とさせられ、「でもそうだよなあ。そんなことってあるよなあ…」と得心させられるシーンが随所に出てくる。これは著者の作品の特徴なのかもしれない。当たり前のことをきちんと捉えてわかりやすく表現できるってことは、実はもの凄いことなのかもしれない。
物語りは、全23章を、第一部「寄宿舎ヘールシャムの子ども時代」(10歳~13歳ぐらい?)。第二部「巣立つ前、若者たちのコテージ共同生活時代」(17~21歳ぐらい?)。第三部「使命遂行時代:介護人、提供者(複数回で終末)」(20代前半~30代前半)と割合分かりやすい構造で展開する。語り部は、主人公の一人で、介護人を11年超も務めてきたキャシー(女性31歳)を回想者として、親友のルース(女性)、トミー(男性)らとともに、<成長>と僅かに<成熟>の日々が精緻に細やかに波を立てながら語られていく。
感想4+は、ひとえに俺が時間をかけて味わえてない恨みの表現であって、“特5”は付かないが普通に感想5のつく作品だと思う。図書館の本は付箋も控えめになり、もちろん線を引くなど論外なので、やはり悔しさは残る。しかし、本書は、それなりの速度であっても、それなりに感情表現や物語りの流れの丁寧さを味わえる読みやすさと作品としての“品格”が備わっている。
昨年のノーベル文学賞受賞でカズオ・イシグロの代表作として話題になったことで、「臓器提供のクローン人間の子供たちの成長と30歳前後までという限られた人生を生きねばならない葛藤が描かれた作品」という大筋の概要はよく知られている。しかし、本作の中では、子どもたちは正式にあからさまに臓器提供するために存在するクローン人間だと教え込まれるシーンは出てこない。むしろ彼ら・彼女らを取り巻くヘールシャムの先生や職員の彼らに対する態度や視線から何となくいつの間にか、「自分たちが施設の外にいる<親>ともいうべきポシブルの細胞から生み出され、将来の役割は社会に必要とされる臓器“提供者”になることであり、幾度かの臓器提供の後に終末を迎えるべき存在である」ということを読み取っていく。介護者というのは、臓器提供者になる前に提供者の身のまわりの世話や、心の支えとなり、最後には同様の臓器提供者として生を終える存在(“段階”)である。
本書では、臓器提供者となる子どもたちや若者が、将来の夢・目標を持てないことに対する多少の不満は持ちつつも、自らが子どもを産む能力を奪われ(セックスはOK)、提供者として早すぎる終末を迎える存在であること自体に対する不満や反発は問題とされていない。むしろ自らの最期を30歳前後で線引きされた子どもたちがその中で精一杯生きる姿・様子・精神が抑制的だが丁寧に描き出されていく。
でも、クローン人間の提供者の子どもたちや若者と現実の人間との違いは、簡単な家庭(恋人同士)までしか認められないことを除けば、70年前後の人生か、30年前後の人生かの違いのみである。つまり、寿命を除けば、ほとんど違いが無い。著者がTV放送の「白熱教室」でも言っていた如く本書のテーマは、結局「人間」であり、短い人生という制限を設けることによって、その人間としての生のあり方がより濃密に描き出されているということになるのだろう。
と、ここまでは肯定的な評価ではあるが、失礼だが本作品だけだと「これでノーベル文学賞か…」という気も少しする。もっと味わって読むべきだし、他の作品もあと3冊ぐらいは読むべきなのだろう。
【内容紹介】自他共に認める優秀な介護人キャシー・Hは、提供者と呼ばれる人々を世話している。キャシーが生まれ育った施設ヘールシャムの仲間も提供者だ。共に青春 の日々を送り、かたい絆で結ばれた親友のルースとトミーも彼女が介護した。キャシーは病室のベッドに座り、あるいは病院へ車を走らせながら、施設での奇 妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に極端に力をいれた授業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちの不思議な態度、そして、キャシーと愛する人々 がたどった数奇で皮肉な運命に……。彼女の回想はヘールシャムの驚くべき真実を明かしていく――英米で絶賛の嵐を巻き起こし、代表作『日の名残り』を凌駕する評されたイシグロ文学の最高到達点。解説/柴田元幸。
【出版社からのコメント】著者のどの作品をも超えた鬼気迫る凄みをこの小説は獲得している。現時点での、イシグロの最高傑作だと思うーー柴田元幸(本書解説より)
英米でベストセラーとなったカズオ・イシグロの最新長篇『わたしを離さないで』は、発売後ただちに《タイム》誌のオールタイムベスト100(1923~2005年発表の作品が対象)に選ばれる快挙を成し遂げただけでなく、《ニューヨーク・タイムズ》《パプリッシャーズ・ウィークリ ー》《シアトル・タイムズ》《グローブ・アンド・メール》の主要紙誌においても2005年のベストブックの一冊に選定された。また、ヤングアダルトの読 者に読ませたい成人図書に与えられるアレックス賞を受賞したほか、ブッカー賞、全米批評家協会賞、コモンウェルス賞、BBCブッククラブ賞の最終候補に もなるなど、2005年に発売された英語圏の小説でもっとも話題になった一冊だ。 --このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。
※ここまで中途、450ページ中の361ページまで 所要時間4:40 感想4+ 以下は読了後に記す。
以下、3月25日(日)夜半(26日am1:45)記す:
439(450)ページ中、362ページ~450ページ(第20章~第23章)を読了 所要時間6:40(4:40+2:00) 図書館
感想は、4+から5+に変わった。残りの80ページを読み上げて、そこにそれまで漠然と思い描いていた作品世界全体の構造が明瞭に明らかにされ、主人公たちの思いや使命完了にともなう行動・ふるまいを知ることができた。当然、読者である俺の思いも腑に落ちて、大きなけりが付いた、ということだ。
本当のカップルになるべきはキャシーとトミーであったのに、自分がそれを引き裂いてしまった、とルースは謝罪し、「本当に愛し合っていれば使命の執行を3、4年猶予してもらえる」からと、ヘールシャムの責任者マダムの住所を託されたキャシーとトミー。
ルースの使命終了(死)の1年後、キャシーが、3度目の提供を終えたトミーの介護人になることで二人は結ばれる。何度もセックスをし、日常を共にする中で本来結ばれていたはずの日々を取り戻そうとするが、それが手遅れであったことも思い知る。そして、もう一つの課題、愛し合うカップルとして“使命の猶予”を得るために、二人は既に閉鎖されたヘールシャムの責任者だったマダム(マリ・クロード)を訪ねる。
二人は、そこでヘールシャムのエミリー先生とも再開し、“使命の猶予”は全くのウソであることを知るだけでなく、ヘールシャムでの質の高い生活のあり方自体の<真相>を知らされることになる。すなわち、「臓器提供用に“試験管の中のえたいの知れない存在”から開発されたクローン人間の子どもたちや若者にも高い精神性や能力があることを示すことで彼らの置かれた劣悪な存在としての地位・環境を少しでも引き上げようとする“運動”の象徴がヘールシャムであったこと。その“運動”がクローン人間の存在を医療的に絶対必要としながら、一方で彼らの存在を強く忌避・恐怖する社会全体との如何にきわどい闘いであったか、そしてある事件をきっかけに、エミリー先生やマダムたちの“運動”は敗北し、ヘールシャムも閉鎖されたのだ」という<真相>を知らされることになる。
4度目の提供を前にしたトミーは、最期を見られたくないと、キャシーを介護人からはずす。トミーは使命を完了し、キャシーもまもなく提供者になる。閉鎖されたヘールシャムの記憶は、トミーとルースの記憶と同様、キャシーの頭の中にとどまり、誰に奪われることもない。
・ヘールシャムの現状が噂になることもあります。ホテルになっている、学校だ、廃墟だ……。でも、わたしは、これだけ車で走り回っていても、自分で探そうと思ったことはありません。いまどうなっているにせよ、あまり見たいとも思いません。437ページ
主人公の一人であるキャシーの回想の中でこの一節を読んだ時、「ああ、ヘールシャムは著者であるカズオ・イシグロにとって、幼少期を送った日本の“長崎”と同じ位置づけなのだ」と感じた。ただそれだけの気付きだが、この作品にも“記憶”を大切にする著者の思いはあふれているのだ、と思った。
 *この表紙のカセット写真は、本作品中における重要なアイテムになっている!
*この表紙のカセット写真は、本作品中における重要なアイテムになっている!439(450)ページ中、現在361ページ 所要時間4:40 図書館
著者51歳(1954生まれ)。 2017年ノーベル文学賞受賞(63歳)。
図書館の返却が迫っている。この週末に読むしかない。縁だけでも結ばせていただこうと、1ページ30秒を目安に読み始めた。実際には遅くなっているが、それでも俺としては速い方だ。細部を確認し、味わうわけにはいかないが、物語りの流れは大体理解できた。どちらかと言えば、読みやすい本である。
正確なのかは分からないが、翻訳の日本語が非常に慎ましやかで丁寧で優しい文章になっている。読んでいて心地よい感じである。読み続けていると、抑制的なシーンの背後に非常に大きな心の動き、やり取りが表現されていて、その細やかさに“はっ!?”とさせられ、「でもそうだよなあ。そんなことってあるよなあ…」と得心させられるシーンが随所に出てくる。これは著者の作品の特徴なのかもしれない。当たり前のことをきちんと捉えてわかりやすく表現できるってことは、実はもの凄いことなのかもしれない。
物語りは、全23章を、第一部「寄宿舎ヘールシャムの子ども時代」(10歳~13歳ぐらい?)。第二部「巣立つ前、若者たちのコテージ共同生活時代」(17~21歳ぐらい?)。第三部「使命遂行時代:介護人、提供者(複数回で終末)」(20代前半~30代前半)と割合分かりやすい構造で展開する。語り部は、主人公の一人で、介護人を11年超も務めてきたキャシー(女性31歳)を回想者として、親友のルース(女性)、トミー(男性)らとともに、<成長>と僅かに<成熟>の日々が精緻に細やかに波を立てながら語られていく。
感想4+は、ひとえに俺が時間をかけて味わえてない恨みの表現であって、“特5”は付かないが普通に感想5のつく作品だと思う。図書館の本は付箋も控えめになり、もちろん線を引くなど論外なので、やはり悔しさは残る。しかし、本書は、それなりの速度であっても、それなりに感情表現や物語りの流れの丁寧さを味わえる読みやすさと作品としての“品格”が備わっている。
昨年のノーベル文学賞受賞でカズオ・イシグロの代表作として話題になったことで、「臓器提供のクローン人間の子供たちの成長と30歳前後までという限られた人生を生きねばならない葛藤が描かれた作品」という大筋の概要はよく知られている。しかし、本作の中では、子どもたちは正式にあからさまに臓器提供するために存在するクローン人間だと教え込まれるシーンは出てこない。むしろ彼ら・彼女らを取り巻くヘールシャムの先生や職員の彼らに対する態度や視線から何となくいつの間にか、「自分たちが施設の外にいる<親>ともいうべきポシブルの細胞から生み出され、将来の役割は社会に必要とされる臓器“提供者”になることであり、幾度かの臓器提供の後に終末を迎えるべき存在である」ということを読み取っていく。介護者というのは、臓器提供者になる前に提供者の身のまわりの世話や、心の支えとなり、最後には同様の臓器提供者として生を終える存在(“段階”)である。
本書では、臓器提供者となる子どもたちや若者が、将来の夢・目標を持てないことに対する多少の不満は持ちつつも、自らが子どもを産む能力を奪われ(セックスはOK)、提供者として早すぎる終末を迎える存在であること自体に対する不満や反発は問題とされていない。むしろ自らの最期を30歳前後で線引きされた子どもたちがその中で精一杯生きる姿・様子・精神が抑制的だが丁寧に描き出されていく。
でも、クローン人間の提供者の子どもたちや若者と現実の人間との違いは、簡単な家庭(恋人同士)までしか認められないことを除けば、70年前後の人生か、30年前後の人生かの違いのみである。つまり、寿命を除けば、ほとんど違いが無い。著者がTV放送の「白熱教室」でも言っていた如く本書のテーマは、結局「人間」であり、短い人生という制限を設けることによって、その人間としての生のあり方がより濃密に描き出されているということになるのだろう。
と、ここまでは肯定的な評価ではあるが、失礼だが本作品だけだと「これでノーベル文学賞か…」という気も少しする。もっと味わって読むべきだし、他の作品もあと3冊ぐらいは読むべきなのだろう。
【内容紹介】自他共に認める優秀な介護人キャシー・Hは、提供者と呼ばれる人々を世話している。キャシーが生まれ育った施設ヘールシャムの仲間も提供者だ。共に青春 の日々を送り、かたい絆で結ばれた親友のルースとトミーも彼女が介護した。キャシーは病室のベッドに座り、あるいは病院へ車を走らせながら、施設での奇 妙な日々に思いをめぐらす。図画工作に極端に力をいれた授業、毎週の健康診断、保護官と呼ばれる教師たちの不思議な態度、そして、キャシーと愛する人々 がたどった数奇で皮肉な運命に……。彼女の回想はヘールシャムの驚くべき真実を明かしていく――英米で絶賛の嵐を巻き起こし、代表作『日の名残り』を凌駕する評されたイシグロ文学の最高到達点。解説/柴田元幸。
【出版社からのコメント】著者のどの作品をも超えた鬼気迫る凄みをこの小説は獲得している。現時点での、イシグロの最高傑作だと思うーー柴田元幸(本書解説より)
英米でベストセラーとなったカズオ・イシグロの最新長篇『わたしを離さないで』は、発売後ただちに《タイム》誌のオールタイムベスト100(1923~2005年発表の作品が対象)に選ばれる快挙を成し遂げただけでなく、《ニューヨーク・タイムズ》《パプリッシャーズ・ウィークリ ー》《シアトル・タイムズ》《グローブ・アンド・メール》の主要紙誌においても2005年のベストブックの一冊に選定された。また、ヤングアダルトの読 者に読ませたい成人図書に与えられるアレックス賞を受賞したほか、ブッカー賞、全米批評家協会賞、コモンウェルス賞、BBCブッククラブ賞の最終候補に もなるなど、2005年に発売された英語圏の小説でもっとも話題になった一冊だ。 --このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。
※ここまで中途、450ページ中の361ページまで 所要時間4:40 感想4+ 以下は読了後に記す。
以下、3月25日(日)夜半(26日am1:45)記す:
439(450)ページ中、362ページ~450ページ(第20章~第23章)を読了 所要時間6:40(4:40+2:00) 図書館
感想は、4+から5+に変わった。残りの80ページを読み上げて、そこにそれまで漠然と思い描いていた作品世界全体の構造が明瞭に明らかにされ、主人公たちの思いや使命完了にともなう行動・ふるまいを知ることができた。当然、読者である俺の思いも腑に落ちて、大きなけりが付いた、ということだ。
本当のカップルになるべきはキャシーとトミーであったのに、自分がそれを引き裂いてしまった、とルースは謝罪し、「本当に愛し合っていれば使命の執行を3、4年猶予してもらえる」からと、ヘールシャムの責任者マダムの住所を託されたキャシーとトミー。
ルースの使命終了(死)の1年後、キャシーが、3度目の提供を終えたトミーの介護人になることで二人は結ばれる。何度もセックスをし、日常を共にする中で本来結ばれていたはずの日々を取り戻そうとするが、それが手遅れであったことも思い知る。そして、もう一つの課題、愛し合うカップルとして“使命の猶予”を得るために、二人は既に閉鎖されたヘールシャムの責任者だったマダム(マリ・クロード)を訪ねる。
二人は、そこでヘールシャムのエミリー先生とも再開し、“使命の猶予”は全くのウソであることを知るだけでなく、ヘールシャムでの質の高い生活のあり方自体の<真相>を知らされることになる。すなわち、「臓器提供用に“試験管の中のえたいの知れない存在”から開発されたクローン人間の子どもたちや若者にも高い精神性や能力があることを示すことで彼らの置かれた劣悪な存在としての地位・環境を少しでも引き上げようとする“運動”の象徴がヘールシャムであったこと。その“運動”がクローン人間の存在を医療的に絶対必要としながら、一方で彼らの存在を強く忌避・恐怖する社会全体との如何にきわどい闘いであったか、そしてある事件をきっかけに、エミリー先生やマダムたちの“運動”は敗北し、ヘールシャムも閉鎖されたのだ」という<真相>を知らされることになる。
4度目の提供を前にしたトミーは、最期を見られたくないと、キャシーを介護人からはずす。トミーは使命を完了し、キャシーもまもなく提供者になる。閉鎖されたヘールシャムの記憶は、トミーとルースの記憶と同様、キャシーの頭の中にとどまり、誰に奪われることもない。
・ヘールシャムの現状が噂になることもあります。ホテルになっている、学校だ、廃墟だ……。でも、わたしは、これだけ車で走り回っていても、自分で探そうと思ったことはありません。いまどうなっているにせよ、あまり見たいとも思いません。437ページ
主人公の一人であるキャシーの回想の中でこの一節を読んだ時、「ああ、ヘールシャムは著者であるカズオ・イシグロにとって、幼少期を送った日本の“長崎”と同じ位置づけなのだ」と感じた。ただそれだけの気付きだが、この作品にも“記憶”を大切にする著者の思いはあふれているのだ、と思った。