12月28日(水):

474ページ 所要時間11:40 蔵書(1990年18版の文庫本)
著者49歳(1916-2003:86歳)。日本の経済学者。専門は
労働経済学。1982年日本学士院会員。東京大学名誉教授、北京大学名誉教授、遼寧大学名誉教授、東北師範大学名誉教授、中国社会科学院名誉高級研究員。昭和36年、東京大学経済学博士。博士論文は「日本賃労働史論」。キリスト教功労者。 ※ウソかホントか知らないが、昭和30年代五味川純平の空前のベストセラー『人間の条件』のモデルだったとか…。
3か月ほど前に360ページ(5:20)までたくさん付箋をしながら流し読みをしていたが、残り100ページで放置してしまっていた。今日改めて読み継ぐにあたり、1ページ15秒のペースで初めから眺め直しにかかったが、まるで初めて読む本のような印象で「この付箋は何だったんだ」と焦らされた。もちろん1ページ15秒なんてペースは無理だし、流れは分かっているが細かい部分については読み切れない。今日の再読は、6:20を要したので、合計11:40である。
本書は
テキストである。目次は、日清戦争(1894)から始まり、日本帝国の明暗、産業革命、労働運動の初幕、内地雑居、藩閥・政党・政商、社会主義への歩み、考えるホワイトカラー、東亜の嵐、日露戦争、反戦の闘い、勝利の悲哀、「普請中」の日本、三井と三菱、日韓併合、大逆事件、明治の終焉(1912)で終わる。改めて見れば、
わずか18年間の短い期間だが、内容はとっても盛沢山だった気がする。激動の時代だったのだ。最後は、明治天皇の死ではなく、大正2年(1913)9月4日の田中正造翁の死で締め括られている。小村寿太郎と原敬と社会主義者たち、及び韓国併合の過程が特に印象に残っている。幸徳秋水は、思っていた以上に激しく生きていた。大逆事件での徳富蘆花の「謀反論」もよかった。
この
中央公論社「日本の歴史」シリーズは、戦後歴史学の記念碑的シリーズであり、名著が多い。
戦後20年(1965)頃記されたものであり、明治以降の近現代史の巻々は、戦後71年の現代では望めない、戦争の時代を肌身に感じ、実際に生き抜いてきた著者たちのリアルな感性が記述に息づいている。近代史における戦争に対する痛切な反省を持した世代による歴史はやはり良い内容だと素直に感じることができる。歴史書というものが、新しいほど良くて、古ければ価値を失うというわけではないことを今回も再認識できた。伊藤博文と李鴻章、伊藤博文と山県有朋、伊藤博文と大韓帝国皇帝高宗、伊藤博文と明治天皇、原敬日記など当時の臨場感に富む記述が多く、難しくはないが詳細で丁寧な記述が良い。
読みながら、たった一人の著者が、これだけ複雑な時代を描き切るのは並大抵ではないとつくづく思ったが、逆に一人の著者が書き切っているからこそ、継ぎ接ぎではない全体としてまとまった歴史になっている。これ一冊あれば、この時代の情報はほぼほぼいい感じで手に入るようになっている。
著者は、
明治天皇をカリスマ天皇と位置付け、天皇亡き後に備えることが山県を中心とする官僚勢力にとって大きな課題であったとする。明治帝亡き後、どんな人間が天皇になっても大丈夫なように、天皇と国民の距離を大きく引き離して、儀式と儀礼のかなたに天皇の存在を消し去ろうとしていた動きを記している。これなどは、カリスマ性を帯び始めた平成の天皇を国民から切り離し奥御殿の中に閉じ込めようとする安倍晋三の姿と重なる。
あくまでも人間の風景としてだが、山県有朋と安倍晋三は、コンプレックスからくる権力への執着や、陰湿な人間性がよく似ている。俺は大嫌いだ。その点、伊藤博文は明るくて、風通しと見晴らしがよくて良い。安重根による3発の銃弾による死は伊藤自身にとっては人生の完結として良かった気がする。
第二次山県内閣における軍部大臣現役武官制の記述が見当たらないことだけが気になって不満が残った。俺の見落としか?
【裏表紙紹介文】
富国強兵策により急激な近代化と工業化を推進した日本は、国運を賭した日清・日露の両戦役に勝って列強の仲間入りを果たす。だが、そこに成立した大日本帝国はしだいに民衆との亀裂を深め、深刻な危機に直面する。この危機に対する体制再編の過程で、明治は幕を閉じる…。














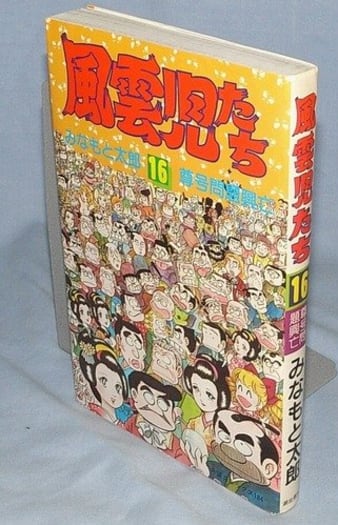 10月25日(日): 205ページ 所要時間 1:40 蔵書 著者42歳(1947生まれ)。漫画家。 どうも読書のカウントにマンガ本......
10月25日(日): 205ページ 所要時間 1:40 蔵書 著者42歳(1947生まれ)。漫画家。 どうも読書のカウントにマンガ本......






