 |
文藝春秋 2009年 04月号 [雑誌]文藝春秋このアイテムの詳細を見る |
物議をかもした村上春樹のエルサレム賞受賞についての
彼の考えと、受賞スピーチ原稿の全文が掲載されています。
ワタシ的には彼の考えについてはいちいち共感を覚え、納得もできるんですが、
一方でああいう彼のスタンスやポジションに反感や異論をもつ人もいるだろうなと想像もするのです。
普段は小説という形で彼はこの世のことについて書いているのですが、本書でのインタビュー「僕はなぜエルサレムに行ったのか」では珍しく直裁に彼の根本思想のようなものについて述べていて、それはそれなりに小説を読みかじっていたワタシが漠然と抱いていた彼の本質であろうと思うものをよく表現していて、興味深いテキストになっています。
そのなかで特に中心的な部分は、彼が常に「個とシステム」をテーマにしていると述べるくだりでしょう。そのとおり、彼の小説を読むと、そこにはシステムを前にした、あるいはシステムに巻き込まれた者というテーマを感じます。
でもそれは感じるだけで、論理的にどうこう述べられているというものではありません。ある意味冷静なくせに非常に情緒的にそのテーマに迫ってくるのです。
そこには回答はありません。だからとても無責任に思えることもありますが、すべてに責任を取るというあり方もまたそれは、理念ではとらえきれない人間の真実をナントカとらえようとする彼の小説界では、逆説的に無責任な態度といえましょう。
システムと個という関係の中では常に個の側に立つ、という彼の信念も、じゃあそのためにどうすればいいのかということ、もしくは、そもそもシステムと個とは対立概念ではなく、あらがいようもない関係性を生きるということのなかにこそ個があるということこそがシステムを揺らぎ立たせているのだと言うことを、一旦は不問にしてしまい、個をぽつねんと切り出しているような、やはり無責任な保留の上に構築されているような気もしてなりません。
でもその彼の無責任を、褒めることこそないけれど、まさに自分自身もそうした保留の上に生活を成り立たせて行く他無いのだと言う点で、同病相哀れむ的な共感を抱いてしまうのです。
それは共感という以上のものかもしれません。彼の考えていることが、言葉にはできないけれどもでもわかる、そして彼の今回のテキストは、一字一句が予測されたものに思え、いちいち理解でき、いちいち共感してしまう。こうした無責任な仮借を生きる者たちこそが、彼の読者であり、彼の小説の登場人物でもあるのでしょう。
村上春樹を支えている読者層は、どのようなメンタリティであるのかを知りたい場合、このテキストを読むとよくわかるのではないかと思うのです。
あるいは結局よくわからない、と思う方も多数おられることでしょうけれども。。
まずはニュートラルな気持ちで、ぼんやりと読んでみてはいかがでしょう。
立ち読みでいいんで・・















 amazon
amazon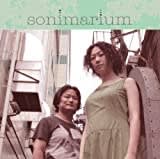 amazon
amazon
この辺りと、
「対立概念ではなく、...無責任な保留の上に構築」 ―
は「ノルウェーの森」でさえ感覚的に分かるのですが、それはなるほど作風として効果を生んでいても、「共感を覚え、納得もできる」かどうかとは異なりますね。
恐らく、そこが開いたままになっているのが「反感」の原因となっているのでしょう。異論はどうですかね?
共感と納得が、客観的というか論理的な基盤の上に築かれないんですよねきっと。
普遍性や論理性を求めていくと肩すかしを食ってしまう。
それでもそうした者を放棄しているわけではなくて、なんとか形にしたいと思っているが、それが出来ないということを含めて自分であることに誠実であろうとしているのだと思うのです。
誠実故の不誠実みたいな形で情緒的に迫って来るくせに、解決は各自にゆだねられる、いやゆだねられているのかすらはっきりとしない。そういう屈折した開き方が、ダメな人にはダメなんでしょうねえ・・
と、いつも考えだすとぐちゃぐちゃな言葉になってしまうのです。
おっしゃる通り村上の作風は、システムの中での個を強く意識するスタイルが特徴的ですよね。村上は、そこに諦観とある種の距離を置くというスタンス、それは読者として共感するに足るものでありましたが。では村上が次の次元に移行していこうという時に、漂う個であることをやめ踏み出すための一歩を模索するというところで、村上は限界点を自ら感じるといったところなのでしょうか。
でもその戦う姿そのものが自分は見たいかなと思います。
想像力が何を成し遂げるかというところで。
コメントどうも~
漂う個であることは彼の小説では宿命的なありかたであって、そこに限界があろうと、その限界を生きる他無い者の不完全さ、矮小さを描くことで存立せざるを得ない、、という感じでしょうかねえ
わけわかりませんけどね^^;
そこを限界と思い一歩踏み出すべきなのかどうか。そこがワタシにはわかりません。。