雫石鉄也の
とつぜんブログ
SKAT.17

第55回宣伝会議賞実行委員会 編 宣伝会議
大変にシンプルな本である。コピーとCMのコンテが並んでいるだけの本だ。しかし、それが5336本も並んでいると壮観である。でも、ま、コピーとか広告に興味がない人が読んでも退屈なだけ、というか、そんな人はこんな本を手にしないだろう。小生は、この宣伝会議賞に応募しているので興味深く読んだ。
で、気がついたのだが、例えばXという商品のコピーを書くとき、このXのメーカーがA社、B社、C社が製造販売していて、小生はA社製のXのコピーなら、B社、C社にない特長を訴求したコピーでないとダメと、応募コピーを書くとき悩んで頭を絞って書いていた。ところが、そうではないんだ。A社のXのコピーを書くときには、B社やC社のXを気にしないで、Xそのものの魅力特性を素直に書けばいいんだ。
例えば、第55回宣伝会議賞のグランプリは、クレディセゾンのクレジットカードのコピーで「現金なんてお金の無駄づかいだ」というモノ。このコピーなら別にクレディセゾンだけではなく、JCBやVISAでも使えるコピーではないか。なんだ、そういうことか。よし、次回はがんばろう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
2018年に読んだ本ベスト5
小生はローテーション人間である。なんでもローテーションだ。酒のローテーションもある。もちろん読書のローテーションもある。海外のSF,国産の非SF,海外の非SF,国産のSF、漫画、ノンフィクション。これがローテーションの軸。今年の阪神タイガースの先発ピッチャーでいえば、メッセンジャー、岩貞、西、ガルシア、藤浪、秋山といったところか。この合間に大藪春彦、山田風太郎、西村寿行といった作家を中心に適宜、新刊や古書を読む。
さて、昨年読んだ本ベスト5は以下の通りである。
1位 零號琴 飛浩隆 早川書房
すごいすごい。飛さんの腕力に感服。和風超巨大ワイドスクリーン・バロックだ。
2位 ヒストリア 池上永一 角川書店
痛快爽快愉快。600ページ超を一気読み必須。スーパーヒロイン知花煉の生き様に酔いしれよ。
3位 上方落語の戦後史 戸田学 岩波書店
上方落語を愛する者なら終生座右に置くべき必読書である。初代桂春團治から稿を起こし、桂米朝の人間国宝認定まで。上方落語の一大興亡史。上方落語と日本SFの不思議な縁もある。
4位 破滅の王 上田早夕里 双葉社
戦前の中国。その細菌に感染したら治療薬はない。細菌を食べる細菌。この恐るべき細菌に取り組み若い科学者。結局は科学を信用するしかない。
5位 孤浪の血 柚月裕子 KADOKAWA
たいへんに骨太で男っぽい小説である。「仁義なき戦い」ファンには特にお勧め。
次点 ダ・フォース ドン・ウィンズロウ 田口俊樹訳 ハーバーコリンズ・ジャパン
上が広島ならこっちはニューヨークだ。ニューヨークのデカは「清濁併せ呑む」なんというんではやっとられん。ニューヨークのデカは「濁濁全部呑む」だ。
さて、昨年読んだ本ベスト5は以下の通りである。
1位 零號琴 飛浩隆 早川書房
すごいすごい。飛さんの腕力に感服。和風超巨大ワイドスクリーン・バロックだ。
2位 ヒストリア 池上永一 角川書店
痛快爽快愉快。600ページ超を一気読み必須。スーパーヒロイン知花煉の生き様に酔いしれよ。
3位 上方落語の戦後史 戸田学 岩波書店
上方落語を愛する者なら終生座右に置くべき必読書である。初代桂春團治から稿を起こし、桂米朝の人間国宝認定まで。上方落語の一大興亡史。上方落語と日本SFの不思議な縁もある。
4位 破滅の王 上田早夕里 双葉社
戦前の中国。その細菌に感染したら治療薬はない。細菌を食べる細菌。この恐るべき細菌に取り組み若い科学者。結局は科学を信用するしかない。
5位 孤浪の血 柚月裕子 KADOKAWA
たいへんに骨太で男っぽい小説である。「仁義なき戦い」ファンには特にお勧め。
次点 ダ・フォース ドン・ウィンズロウ 田口俊樹訳 ハーバーコリンズ・ジャパン
上が広島ならこっちはニューヨークだ。ニューヨークのデカは「清濁併せ呑む」なんというんではやっとられん。ニューヨークのデカは「濁濁全部呑む」だ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
SFマガジン2019年2月号

SFマガジン2019年2月号 №731 早川書房
雫石鉄也ひとり人気カウンター
1位 彼岸花 伴名練
2位 博物館惑星2・ルーキー 第六話 不見の月 菅浩江
3位 知られざるボットの世界 スザンヌ・パーマー 中原尚哉訳
4位 キミノスケープ 宮澤伊織
5位 四十九日恋文 森田季節
6位 本物のインディアン体験へようこそ レベッカ・ローンホース
佐田千織訳
7位 幽世知能 草野原々
連載
小角の城(第51回) 夢枕獏
椎名誠のニュートラルコーナー(第64回)
インデギルカ号 椎名誠
先をゆくもの達(最終回) 神林長平
マルドゥック・アノニマス(第24回) 冲方丁
マン・カインド(第7回) 藤井大洋
幻視百景(第18回) 酉島伝法
百合特集
百合特集である。百合=女性と女性の関係を扱う。と、いうのだそうだ。小生はそっちの方はまったく不勉強で知らない。女性と女性というとレズビアンか。と、早合点する人もいるかも知れぬが、レズも百合のいちジャンルで、性的なモノばっかりではないのではないのかな。
かような「百合」なる世界があることはまったく知らなかった。じゃによって表紙を見たとき「百合特集」?なんのこっちゃ。SFマガジン編集部もいよいよ本格的にとち狂ったかと思った。ところがおじんたる小生の認識不足であった。「百合」なるモノが好きな人が多いんですな。このSFマガジン2019年2月号は発売と同時に売り切れ。重版したそうだ。SFマガジンとしては初音ミク特集以来の大ヒットとなった。
で、内容だが、なかなか充実して読みごたえのある号であった。特に1位の「彼岸花」が傑作である。形式としては日記体の小説だが、血の臭いのする日記であった。「百合特集」知らない世界を垣間見せてくれた。なるほど「百合」とSFは親和性が高いことが判った。で、こんどは「薔薇」特集ってのはどうだ。「百合」を特集して「薔薇」がないとは片手落ちではないか。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
弧狼の血

柚月裕子 KADOKAWA
期せずして日米の悪徳警官モノの読み比べとなってしまった。「ダ・フォース」がニューヨークなら、こちらは広島だ。
昭和時代の広島ヤクザの生態を活写した映画といえば「仁義なき戦い」だが、作者の柚月さんは、この映画の大ファンとか。その「仁義なき戦い」の流れに乗って創られたのが傑作「県警対組織暴力」この小説は、この映画へのオマージュともいうべき小説ともなっている。で、いまからこの小説を読まれる諸賢にご注意申し上げたいのは、「県警対組織暴力」を観ないで、読まれる方がいい。深作欣二+菅原文太のイメージは強烈だから、どうしても本作の副主人公大上巡査部長に菅原文太のイメージがちらついてしまう。本作は映画化されていて大上役は役所広司が演じているが、役所の方が菅原より大上のイメージに近い。
本作の大上も「県警対組織暴力」の久能徳松も「ダ・フォース」のデニー・マローンも同じことをいっている。
「ワシらの仕事はヤクザを撲滅することじゃない。『戦争』をさせないようにしてカタギに迷惑かけないようにするのじゃ」
暴力団は絶対になくならない。現実に組はあるんだから、せいぜい大人しくしてもらおう。組と組の「戦争」を無くすにはどうする。一方の組がなくなればいいんだ。と、いうわけで大上や久能、マローンは特定の組に肩入れする。これを警察と暴力団の癒着というが、暴力団と接触しないで暴力団の情報は得られない。情報がなければ取り締まりもできない。
大変に骨太で男っぽい小説である。知らないで読めば、男性作家だと思われるだろう。柚月裕子さんは女性名を名乗っている男性作家ではなく、女性である。しかも大変に美しい女性。柚月さんは覆面作家ではないから、そうはならなかったが、もし覆面作家なら、ジェイムス・ティプトリー・Jrのような騒ぎになっていたかもしれない。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
零號琴

飛浩隆 早川書房
う~む。すごい、すごいぞ飛浩隆。ワシはナニをそんなに感嘆しているのか。飛浩隆がすごいのは、SFファンのあいだでは周知のことではないのか。めったに本を出さないけれど、出したら必ず早川の「SFが読みたい」のランキングで上位に来る。
すごいのは飛さんの腕力である。「街全体が1つの楽器」というアイデアで600ページを超える大長編を仕上げるのだから、これはもう豪腕としかいいようがない。腕力でこのぶっとい本をグイグイ読ませるんだから、すごいとワシが感嘆するのを理解していただけたであろう。
惑星「美縟」の首都「盤記」で大きなお祭が行われる。伝説の楽器「美玉鐘」を復活させ、幻の音楽「零號琴」を演奏しようという。この超巨大プロジェクトにさる大富豪に呼ばれて参加するのは、特殊楽器技芸師とその相棒第四類改変態。おりしも「盤記」では街中が「假面」を付けて行われる「假劇」の開催が間近なのだ。
いつとも、どことも知れぬ世界で繰り広げられる、摩訶不思議、奇妙、玄妙な物語ではあるが、上の皮一枚めくると、そこに見えるのは、ジャック(異郷)ヴァンスであり手塚治虫であり宮崎駿、特撮もんでアニメなのだ。ともかく漢字の持つイメージ力を最大限生かしたワイドスクリーンバロックといってもいいだろう。SFを読む悦びをたっぷりと味わわせてくれる。満腹である。飛さん、どうもごちそうさまでした。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
世界一美味しい煮卵の作り方

はらぺこグリズリー 光文社
料理のレシピ本である。小生も料理をするが、この本で紹介されている料理と小生の料理はまったく違うジャンルの料理である。小生の料理は趣味の料理である。釣り、ゴルフ、ギャンブルと男の趣味もいろいろあるが、小生の趣味はこれら男の趣味のうちの一つだ。ゴルフ好きがクラブを磨くところを、小生は包丁を研ぐ。釣り好きが明日の釣行の算段を考える代わりに、明日のメニューを考える。
ところが、この本の料理はどうも趣味の料理ではないようだ。一人暮らし(たぶん男)が、手間も費用もかけず、なおかつうまいメシを食いたい。で、どういう料理があるかを紹介した本である。
小生の料理は趣味であるからして、手間をかけて、その手間を楽しむという側面がある、この本の料理は手間を極力かけずに調理すべく研究を重ねた料理である。いわゆる「ずぼら料理」というジャンルの料理本といってもいい。ずぼら手抜き料理を標榜するおばさんもいるが、ずぼらどころか大変に熱心勤勉である。一生懸命ずぼらの方法を研究開発している。
この本の著者もそうである。いかに手を抜いて料理をするか、大変な手をかけている。手を抜くために手をかける。パラドックスである。そんなに一生懸命研究するのだったら、その手間を調理にかければいいと思うが。
そんなレシピが100本載っている。いずれも研究結果である。結果よりも、失敗、挫折、試行錯誤、といったそのレシピに至る研究の過程を紹介してくれた方が面白いと思うんだが。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
七人のイヴⅢ

ニール・スティーヴンスン 日暮雅通訳 早川書房
と、いうわけで、第3巻を読んだ。うれしかった。なにがって?この本を読み終わった時。ああ、これで、この苦痛から解放される。もう退屈なつまらん本を読まなくていい。別の本が読める。
月が壊れて破片が地球に降り注ぎ、人類は宇宙に出ている人たち以外は全滅。それから5000年後、生き残った人たちは、人口も増え、不毛の星の地球の復活も成されようといている。人類は新しい文明を築き始めた。
と、こう書くとSFファンなら食指が動くだろう。小生も動いた。だから1巻2巻だけで止めときゃいいのに3巻まで読んだわけ。大失敗であった。面白くない。まず、モイラン、テクラン、レッド、ブルーなどのカタカナ言葉がなんの説明もなく出てくる。これは翻訳者の不親切でもあると思うが、なんのことやらさっぱり判らぬ。
壮大なスペクタクルな話であるのに、細かい描写ばかりで、肝心のストーリーがいっこも動かん。ま、いわば、小津安二郎に「日本沈没」「ゴジラ」「ベン・ハー」「十戒」などのスペクタクル映画を監督させたよう。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
SFマガジン2018年12月号

SFマガジン2018年12月号 №730 早川書房
雫石鉄也ひとり人気カウンター
1位 トランスフューマンガンマ線バースト童話集 灰かぶり姫 三方行成
2位 時の扉 小川哲
3位 失われた時間の守護者 ハーラン・エリスン 山形浩生訳
4位 愛を語るより左記のとおり執り行おう 澤村伊智
5位 奇妙なワイン ハーラン・エリスン 中村融訳
6位 おお、汝信仰うすき者よ ハーラン・エリスン 柳下毅一郎訳
連載
小角の城(第50回) 夢枕獏
椎名誠のニュートラル・コーナー(第63回)
団体偵察旅行 椎名誠
先をゆくもの達(第6回) 神林長平
マルドゥック・アノニマス(第23回) 冲方丁
幻視百景(第17回) 酉島伝法
ハーラン・エリスン追悼特集
ワシら古いSFファンとしては、こんな追悼特集が組まれるとは思いもしなかった。あのエリスンが死んで、みんなに悼まれる。あのエリスンである。と、いっても若いSFファンにはよく判らないであろう。
ハーラン・エリスンといえば、短篇の名手であり、先鋭的なアンソロジーを組む優れたアンソロジスト。といった、仕事のことよりも、アメリカSF界一のごんたくれ。鼻っ柱が強く、だれにでもケンカをふっかける。大物作家にも遠慮はしない。アイザック・アシモフにもケンカを売って、それがアシモフに気に入られたり。からんできたフランク・シナトラにも遠慮はせずにケンカを買った。
表紙はエリスンの肖像写真。この写真は良かった。エリスンのごんたくれぶりがよく判る良い写真だ。
追悼特集は、本邦初邦訳作品、追悼エッセイ、評伝、年譜といった追悼企画では定番のモノだが、この中で最も面白かったのはなんといっても年譜。まさに抱腹絶倒の面白い年譜であった。これはエリスンそのもののキャラの面白さなのか、編集した牧眞司がうまいのか。エリスン作品3編はあまり面白くなかった。
ハーラン・エリスンが亡くなった。なんかさみしい。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ダ・フォース
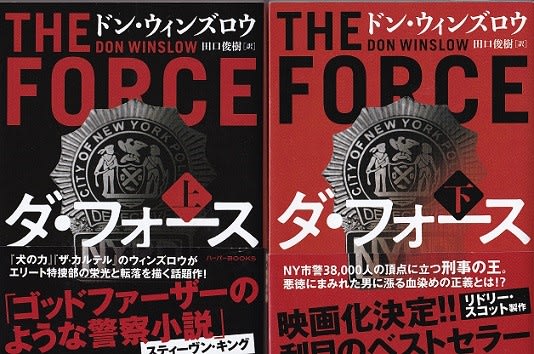
ドン・ウィンズロウ 田口俊樹訳 ハーパーコリンズ・ジャパン
ウィンズロウの作品で「犬の力」を深作欣二映画でいうのなら「仁義なき戦い」とするのなら、この作品は「県警対組織暴力」にあたるのではないか。
しかし、まあ、なんですなあ。ほんとのニューヨークは知らないが、この作品のニューヨークはひどいところだ。街中に麻薬があふれかえっている。麻薬組織やギャング、マフィアなどの組関係者と警察はずぶずぶ。公営住宅はヤクザの巣。そんなニューヨークの治安を預かるニューヨーク市警のマンハッタン・ノース特捜部は最精鋭の刑事たちの集団。その特捜部の現場のボスが主人公デニー・マローン部長刑事。
マローンは骨の髄から刑事。親の代からのデカで、警官になる以外生き方をしらない。まさにデカの中のデカ。そんなマローンが逮捕された。
マローンたち特捜部の目標は「現状維持」ニューヨークから犯罪を撲滅しようなんてバカなことは考えない。各組、各組織の勢力が均衡してて、それなりに平和を保つこと。それに全力を注ぐ。一番さけたいのは戦争。どっかの組が力を持つと制覇をめざして戦争を始める。それを防ぐため敵対する組に特捜部が力を貸すこともある。
こういうデカだから、マローンたち特捜部のデカは「清濁併せ呑む」なんてきれいごとはいわない。「濁濁全部呑む」である。
麻薬組織のボスを射殺。麻薬を押収して、その麻薬を別の組織に転売。金は特捜部のデカたちで山分け。なんてことを平気でやる。そんなマローンたちの天敵はFBIと市警の内部監査部。これらに情報を密告することは「ネズミ」として、ニューヨークの全ての警官からバカに軽蔑される。
ここ神戸は大きな組の本部がある。街中でときとぎ、そういうおじさんたちを見かける。古い友人で警察官がいる。その友人の結婚式に出た。お仲間の警察関係者も多く出席していた。その人たちと、組のおじさんたちと同じ臭いがした。こっちに来たのが警官。あっちに行ったのが組のおじさんと聞いたことがある。マローンは警官であるが、やっていることはヤクザといっしょ。正義ってなんであるのか問いかけてくる小説である。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
ダック・コール
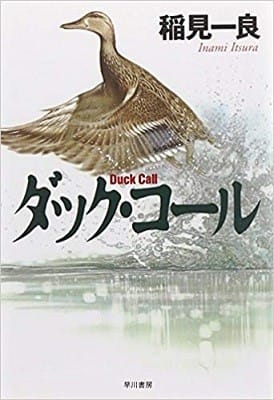
稲見一良 早川書房
先代笑福亭松喬享年62歳。稲見一良享年63歳。くしくもこの二人肝臓がんで早世している。60代前半で逝ったこの二人、これから、今から楽しみというときに亡くなった。先代松喬さんはいわば軽笑福亭ともいう軽妙洒脱な芸風。60代から70代にかけての先代松喬さんを見たかった。
稲見一良はがんを発症して作家活動を始めた。少年の心を持った大人の作家であった。稲見一良の本格的なジュビナイルを読みたかった。
年齢。女は通り過ぎる、男は積み重ねる。と、思う、小生は。女は年齢を通り過ぎる。40歳の女の中には10代や20代の女はない。男は年齢を積み重ねる。40歳の男は、10代20代30代の男の上に積み重なってできている。だから40代や50代の男の中には10代の男が残っているのだ。稲見一良は、その大人の男の中の少年を呼び起こしてくれるのだ。
プロローグ、モノローグ、エピローグをはさんで六つの短篇が収録されている。
「望遠」社運をかけたCM撮影。日の出の決定的瞬間を撮影しなくてはならない。その時、貴重な鳥が飛んだ。千載一遇のチャンス。
「パッセンジャー」サム、鳥の群れとあう。ものすごい数の鳥の大群だ。きれいでおいしいハト。リョコウバトだ。
「密漁志願」癌を患い退職した初老の男。稼ぎの良い女房。豪華なキャンピングカーで毎日狩猟。素人狩猟で銃は使わない。おかっぱ頭の少年ヒロと友だちに。ヒロ、パチンコの名人。男、ヒロに弟子入り。「男爵の森」に侵入、そこの鴨をみんな密猟しようと計画する。ラストはうるっときた。
「ホイッパーウィル」マンハントもの。この作品集でいちばんハードボイルド。主人公は元442連隊の日系人。脱獄犯4人を追う。いずれも凶悪犯。3人は捕まえた。あと1人。この最後に残った脱獄犯。ナバホ族の酋長の流れをくむ勇者。大人しくもの静かな彼はなぜ脱獄したのか。人種差別するヤツ。しないヤツ。なんでもいいから動くものを撃ちたいヤツ。
「波の枕」漁師源三、船が火事で漂流。一枚の板にたどり着く。その板にはグンカンドリとオサガメが。人間と鳥と亀が大海原を行く。
「デコイとブンタ」俺は鴨のデコイ。いじめられっこ少年ブンタと会う。友だちになる。俺とブンタは遊園地の観覧車に乗る。
いずれの作品も鳥が重要なモチーフになっている。たいへんに静謐にして叙情性の富んだ作品。男の子の宝箱のような作品集である。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
今宵もウィスキー

太田和彦編 新潮社
田村隆一、景山民夫、山田風太郎、山本周五郎、開高健、山口瞳といった昭和な人たちの酒にまつわるエッセイが17編。
小生は酒は日本酒、ビール、ウィスキーしか飲まない。このうちウィスキーが一番好きかな。バーの小説を書いてるくせに、バーではあまり飲まない。家飲みがほとんど。ウィスキーグラス片手に上方落語or阪神タイガースを観ている時が至福の時間である。
そんな小生が本書を読んだ。正直、期待はずれであった。ウィスキーそのものがテーマの中心にあり、ウィスキーが前面/全面にでたエッセイはなかった。これらの人たちの生活、活動、想い出の中に、小道具の1つとしてウィスキーが出てくるわけ。小生はウィスキーそのものにまつわるアレコレを期待して本書を読んだのであるが、期待はずれであった。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
三日月をけずる

服部誕 書肆山田
「右から二番目のキャベツ」から1年ぶり。詩集である。小生は詩を読む習慣はないが、この本は楽しく読めた。
詩集といいつつも、いかにも詩詩とした詩ではなく、エッセイともショートショートともいっていいから、詩アレルギーの小生にも読みやすかった。
著者は芦屋市の出身。芦屋で育った。著者と知遇を得て40年以上経つ。小生と著者はチャチャヤング卒業生。あのころは別のペンネームで芦屋から投稿していた。芦屋といっても北のいわゆるお屋敷まちではなく、南の方である。阪神電車の打出駅の近く。
と、いうことで、本書には打出、宮川、第2阪神国道(43号線)、鵺塚、おさるの公園などが出てくる。小生は神戸は東灘の住民、芦屋と市境を接している区である。だから上記あげたところは散歩圏内である。地元民意識が刺激されて興味深い。
阪神大震災を題材としている作品もいくつかある。上の芦屋の南部は大きな被害を受けた地域だ。小生は東灘で震度7を経験した。これらの作品は大変に共感を受ける。
この詩集、私詩の詩集といってもいいだろう。次の著作が楽しみである。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
七人のイヴⅡ

ニール・スティーヴンスン 日暮雅通訳 早川書房
てえことでございまして、2巻目である。あれから2年、いよいよ「ハードレイン」が始った。地球はオレンジ色の炎に包まれた。人類は、ほんまに宇宙の「クラウドアーク」の1500人だけになった。
小生の大好物にスペクタクル映画がある。大災害、大惨事、大事故、ともかく「大」のつく出来事を、わが身は安全な状態に置いたまま、わがことのように「体験」できるのが映画の醍醐味だろう。大地震なら、わがこととして経験した。小生、阪神大震災で震度7を経験した。阪神高速が横倒しになるのを見た。
と、いうようなスペクタクルを期待してこの小説を読むと期待はずれだ。地球に炎の雨が降り注ぎ、そこに残った人類は全員死滅。これが映画であるのなら、ここのところは大スペクタクルで見せ場である。ところが本書では、かようなスペクタクルはいっさいなし。またクラウドアークの人たちにも地球に大切な人がおったであろう。それに関する愁嘆場もなし。
だから、地球規模の大災害人類絶滅。迫真の筆さばきでそれを描写してくれるとたいへんな大エンタティメントとなるのだが、この小説、そんなもんはいっさいなし。また、死に別れした地球の大切な人に対する惜別もまったくなし。地球はぶっ壊れた。みんな死んじまったとさ。それだけ。クラウドアークの連中は感情ってもんがないんか。で、生き残った連中は何をやっていたかというと内紛。クラウドアークの元司令官派とアメリカの元大統領派にわかれてケンカ。こんなアホは男がやりそうだけど両方とも女性。結局クラウドアークに生き残ったのは女性ばかり。
う~む。もひとつ乗り切れない小説であった。3巻目への期待だけで読んだのだが、正直、しんどかった。1巻目の帯にオバマとかビル・ゲイツだとかいうエライ人たちが面白がったとか書いてあるけど、このおじさんたち、ほんまにこれが面白かったのやろか。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
SFマガジン2018年10月号

SFマガジン2018年10月号 №729 早川書房
雫石鉄也ひとり人気カウンター
1位 検疫官 柴田勝家
2位 博物館惑星2・ルーキー 第5話 白鳥広場にて 菅浩江
3位 冬の時代 柞刈湯葉
4位 火星のオベリスク リンダ・ナガタ 中原尚哉訳
5位 サヨナキが飛んだ日 澤村伊智
連載
小角の城(第49回) 夢枕獏
椎名誠のニュートラルコーナー(第62回)
裏側探検隊 椎名誠
先をゆくもの達(第5回) 神林長平
マルドゥック・アノニマス(第22回) 冲方丁
マン・カインド(第6回) 藤井大洋
幻視百景(第16回) 酉島伝法
特集・配信コンテンツの現在
最新のヒューゴー賞やネビュラ賞の紹介、非英語圏SFの紹介、そういう企画を最近はやらない。これはSF専門誌として怠慢である。で、今号はこういう特集企画である。小生、SFは文芸とこころえる。よってSF専門誌たるSFマガジンは文芸誌であろう。編集部内にはSFマガジンは文芸誌であるとの自覚症状のある者もいるようだが、なにゆえ、かような文芸とはなんら関係のない特集を企画するのか、これひとつの不思議。とはいいつつも、小生、近い将来、配信コンテンツのお世話にならないといけないだろう。
土曜の夜、ウィスキーをちびちびなめながら、映画を観るのが無上の楽しみである。テレビ放映を録画したモノか、ツタヤでDVDで借りてきて観ている。ところが近くのツタヤが閉店になった。聞くところによればツタヤの店がどんどん閉店になっているとか。近い将来、自宅で映画を観るには配信コンテンツに頼らなければならないだろう。よって気に食わん企画であるがひととおり目を通した。こんなことやるより、今年のヒューゴー賞ネビュラ賞を読みたいぞと思いながらである。困ったものだ。そこがトセーニンのつれえところよ。
特集企画は気に食わんかったけど、読みきり短篇5編はいずれも面白かったので許してやろう。
「検疫官」その国は「物語」がご禁制。たとえ身の上話でも物語性があるモノはご法度。主人公は国内に「物語」が入り込むのを防ぐ。もちろん、この国では小説を書くのも読むのもダメであろう。小説書き/小説読みの、ある意味私小説ではないだろうか。
「博物館惑星2・ルーキー 第5話 白鳥広場にて」その立体造形物は自律性のある粘土でできている。鑑賞者は自由に触れる。なにをしてもいい。その「作品」になにをなすりつけても、なにを押し込んでもいい。そいつは自分で考え自分で思う形になる。これが「芸術」か。
「冬の時代」遠未来。日本列島寒冷化。氷と雪でおおわれた。少年二人が南へと旅をする。
「火星のオベリスク」80歳の老建築家。最後の仕事。火星にオベリスクを建立する。火星は無人のはずだが・・・。
「サヨナキが飛んだ日」娘がサヨナキのとりことなった。良い子だった娘をとったサヨナキが憎い。緊迫感のある筆致はなかなか読ませる。1位にしたいがサヨナキ=スマホがあまりにそのままなので5位にした。
うん。今号は特集はいただけないが、短篇が面白かったので満足である。連載を減らして読み切り短篇を増やしてくれ。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
苦海浄土 わが水俣病

石牟礼道子 講談社
水俣は風光明媚で海の幸に恵まれた土地であった。不知火海では豊富に魚が獲れた。また水俣は企業城下町である。大手の化学工業メーカーチッソ。水俣はチッソでもっている街でもある。昭和30年代に、この水俣に異変が起こった。猫が消えた。水俣は猫がいない街になった。そして人間に奇病が発生する。手足がしびれる、聴覚障害、言語障害、まともに歩けなくなる、意識混濁、狂騒状態、そして死。最初はこの奇病、原因が判らなかった。どうもチッソの工場から出る排水が原因らしい。しかし、それをいうことは水俣でははばかられる。チッソあっての水俣なのだ。
いっかいの主婦であった石牟礼が故郷で起こった悲劇を克明に記録したのが本書である。しかしこの作品はノンフィクションではない。第一回大宅壮一賞に選ばれるが石牟礼は辞退している。
本書は水俣の水俣病という現象を記してはいない。本書の語り手は「わたし」石牟礼本人が自分の言葉でこの病気を記している。それは水俣病患者という存在を描写してはいない。「わたし」が山中九平、並崎仙助、坂上ゆき、たちの依り代となって、自らが罹患した病を語っているのである。だから本書で語られる言葉はまぎれもなく真実だ。が、しかし、ドキュメンタリーやノンフィクションでは決してない。石牟礼道子という稀有の文学者を通過して世に出たまぎれもない「文学」である。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |



